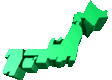

���{��蒼���_?
�}�X�R�~�푈�̎��� �� �}�X�R�~�̌��� (3)
�@���{�E��蒼���_�@?�@
�@���NjL��
![]()
![]() �@
�@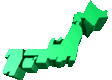

![]()
![]()
�@�܂��܂����̂������哱�@?
�@�����E���������v�̖��ɐ旧���ċ}���サ�ė����A��������������A����c���E�팸���B
�@���̍팸�ĂƂ����̂́A�ǂꂾ���̋K�͂̂��̂Ȃ̂��낤?�@�����ɂ������E�����Ƃ��ē`����ė�����̂ŁA���̍팸�̑Ώۂ���e���A�������l�����Ƃ��������ł͂Ȃ��A �ґ�(=���t�̍\��)�����܂߂��A�����̑̐������ʂ������Ō����������̂Ȃ̂��낤��?
�@�����A�����팸�̖ړI���A�����̖����̂��߂̗��v�ɊҌ�����錩�ʂ��Ɗm�M�������A����̘g���o���オ�������œ��c�����O�i�I�Ȓ���ł���Ƃ��������c�J(���܂�)�̐��ɉ����ꂽ�c�����I�ȁE��̐��̂Ȃ����Łc�ɂ��S�炸����ɂ���Đ��܂�闘�v���A���̍����ɂ͊֗^���Ȃ��A�������E�����ɂ��Ȃ�̉e�����y�ڂ��Ȃ��f�ʂ�̃t���[�E�p�X��(��������)�c�Ђ�����A�r�₦�鎖�̂Ȃ��E�ی��̂Ȃ������������琶�܂�锜��Ȏ؋��̌����߂ɉ�c
�@�������A�����ɂ͂܂�ŏ���œ����̏��N�x�ł����邩�̂悤�ȑ����̒��ōX�Ȃ����ň����g�ݍ��܂�c�o�ς̏z���ɂ͑S���Ƃ����ėǂ��قǍv�������A�����哱�͂܂��܂����̂��c�Ƃ������ł���c����͂����������Ȃ̂��A�Ƃ���!?�@
�ɂ݂��Љ�ۏ���v??
�@1000(�])���~�Ƃ������邱�̑���Ȏ؋���(=�����s�c���E2011�N����)�A���x�̑�k�Ђɂ͒��ڊ֗^���Ȃ��A���̑唼�����łɂ���ȑO����̐ςݏグ���痈������ł���c������k�Ђ̂����ɂ��ăJ���t���[�W�����A���ł̗��R�E�ړI�̈�Ƃ��������(����)��ȂNj�����鎖���낤�� ?�@�����A���ꂪ�������Ȃ�A�����ȂǕK�v�Ȃ��̂ł� !?�@��͂�A�����Ȃ����������܂��˂��~�߂鎖�������ł���A�����ł͂Ȃ��̂��c!?�@
�@(�ǂ�Ȃɑ傫�Ȑk�Ђł����Ă��A���������A�ꌅ����B���N�O�ɂ́A800���~�ł������̂��A���ł́A1000�]���~�ɂ܂łӂ����ł���A�X�ɁE�X�ɑ����čs���c!)�@
�@������̔���Ȃ������̒��ɂ��c����������(��k��)�ł���A���ł͎d���Ȃ����낤�Ƃ�������������邯��ǁc�����͂��ׂāA�ꎞ��(����)���̊��������ɂ���S�����̈�ɉ߂��Ȃ��̂ł����āc�@
�@�����Ԏg���Ă����u�ɂ݂��Љ�ۏ���v�v�Ƃ͂ǂ������Ӗ����낤�H�@
�@�����ɂ���ɕ��S�������鎖�����́A�u���v�v�ƌĂ��̂��낤�H�@�����̒l�グ�Ƃ����v���Ȃ��B���v���̂��̂̈Ӗ��ƖړI�����{�������Ă���̂ł́H�@�N�����E��Ñ��̗�����ێ������������A�Ƃ����v���Ȃ��B�@��Ƃ̎傪�����̂����̂��߂Ɏ؋�������Ă����Ȃ���A���������ɉƑ��ɋ�����Ƃ����͈̂�ʂɂ悭���邢���Ȃ���̂����ł���A���́A�����������̂��߂ɂ킴�킴�����Ƃ��K�v�Ȃ̂��낤�H�@�����͉��v�ł��Ȃ�ł��Ȃ��c�y��͂��̂܂��̂����������̌J��Ԃ����A���̂悤�Ȕ���Ȏ؋��̂ł́H
�@
�@��̂��́c���܂��܂��Ő��x�����̂܂܂ɁA���̉��v���Ȃ���Ȃ��܂܁A����ł��������N�x�́c���̃c�P���A���ɂȂ��ĉ���Ă����Ƃ������ɋC�t���Ȃ��c����ǂ��납�A������܂�����Ɂc�ĂьJ��Ԃ����Ƃ��Ă���!
�@�������A����ł̓������̂��̂������̂ł͂Ȃ��A�u���ׂĂ̋Z�ɂ́@��������v�ƌ�����悤�ɁA����͂�������������}���Ă����̂ł���A�{�s�҂����̍߂ł͂Ȃ��c
�@�v�́A����Ȏ����i�K�ɂ���V���x�ɑ��āA��p�҂̎��������A����Ɏ��s������d�˂Ȃ��痝�z�I�p�Ɏd���ďグ��Ƃ����w�͂�ӂ����A�Ƃ������ł���c
�@�����������Â����o�̊����������}�C���h�E�R���g���[���̃I���p���[�h�ɁA�����܂ł̒����ԁA�����������͊��S�ɂ͂܂荞��ł����B�@�����ɂ͑S���g�Ɋo���̂Ȃ��A�����哱�ɂ�邱���̗���𑁂��ς��Ȃ���A�؋��͑���������!!�@
�@������k���ɂ��Ă��A�����͑S�������Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@�����́A������������ׂĂ̌��ʂł����āc����ɂ��S�炸�A���E�����ɂ��蓊������B
�@�C�O�ŋN����u�e���v��u���������v�̔��[���A�����Ƃ��Ă͓����ł���c���{�l�ׂ̍₩�ȐS�������A�������Ƃ肠�����J���t���[�W�����ė����������B
�@����A�ނ���c�Ȃ܂�����Ȏ}�t�́i�����ɂ��j�S�������Ȃ�������A�i�����哱�ɂ��j����Ȕ���Ȏ؋������܂�Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�����̒��r���[�ȐS�������t�ɁA�O���[�o���Љ�ւ̑O�i��W���E������ōs���B
�@
�@�ߋ��Ƃ͈Ⴂ�A���{�̌o�ώj��A�܂��A������ƊE�ɂ�����W�听�̂��̎��c����Ȓ��ɕ��サ�����́A(���������)�w����ňāx(=���}���u��)�ɂ́A�ɗ͐T�d�ȍ\���ƌ��ӂ��Ղނׂ����낤�ƁA���͎v�������?
�@����(�V��)�̂��тɍ����𗈂��̂́A�y��(�o���_)���������肵�Ă��Ȃ��؋� ?
�@(��ɂ���ɂ�)�S��(����)�Ƃ��Ă������E�Ԏ��̃o�����X�������d�v�������w�����E���������B�@�Ƃ肠�����O�ɂ͌����Ȃ����c�̂قǂɂ͘I���ŁE�P���ł͂Ȃ�����ǁc�܂���A����őS�̎�`�E���͎�`�̂悤�ȁB
�@�@
�@�\�����ɂ́c����?�ȓk�}��g���(=�����}���ӁE�����}�̐��c)�A�}�X�R�~���܂ފe�E����]�w�����������c���h�ȃ^�C�g�����f���E���͂��Ăт�����c
�@���������̗��ł��c�}��E���s�����u���c�����������̂��̒����c�����k���Ɖ����E�ǂ����Ⴄ��? �Ƃ������悤��������̂悤�ȁE�삯�����̂悤����������J��Ԃ��c����ł������ƁA����ێ��ɖ�N�ƂȂ�c����ł́A�匠�D���ɖ�N�ƂȂ�c(���ƌ����āA�����ٖ��Ƃ����قǂ̎u�����������Ȃ��c)
�@
�@�������A����ɂ��v���C�h�������Ȃ��Ǝv���l���������邾�낤�c���������l�����ɂ́A���̏�������Ă��炤(���})�����Ȃ��Ƃ����c���ꂪ�A�̂���J��Ԃ��ė����A���{�̐��E(=�����哱)�̎������B
�@���́c�����̈��|�I�����ɂ���Đ��������w�X�����c���@�āx(=���S���v�Ƌ��Ɏ����E�{�i�I���������v�̐�N)�B�@
�@�ɂ��S�炸�c���E�^�}(����})�ɂ���ēڍ�����(=�u�������v�ɐ�ւ��E�y�����ꂽ)�B
�@�����č��A���̗^�}�ɂ���đł����Ă�ꂽ�w����ňāx���A�����ŋc�������E�����ō����������ނ��钆�ŁA�������E�^�}�ɂ�����������悤�Ƃ��Ă���c
�@�����Ă���Ɂc���E�^�}�ɂ�������߂����A���������v�Ă��щz�����u����c���팸�āv�B�@��������ɂ���Ȃ���A���������āE������Ƃ��đ���Ǝ����Ƃ̉��l�]���������Ƃ����̂��낤�B
�@��������A�C�f�I���[�O����ݏo���Љ�\���B����ł͂�����̕��ɁA������Ȗ������������ł���̂����m��Ȃ��B
�@�g�D�E�����ɏ悹��ꂽ���ɂ��C�t�������������^�����A�������������_�B�u�O�𐭎��v�̎n�܂�Ȃ̂����m��Ȃ��B�@
�@��l(������)�̂��߂ɉ����̕ۏؐl�ɂł��Ȃ����悤�ȁc�܂�ŁA�T�������p���o���̂��̂Ƃ������悤�ȁc ���ʁA���̗���(���E��=����)�������Ă��܂����c�ȂǂƂ������̂Ȃ��悤�A�P�Ȃ�ڐ�̌o�����o�ł͂Ȃ��A�������Ƒ����o��(=��Ƃ̎�Ƃ��āA���Ăɖڂ�ʂ�)��ÂɎ��g��łق����B
�@�l�b�g�̎���(=�}�X�R�~�푈)���}���A������ی����̓��{�c�ɂ��C�t�����A�ڐ�̍�������(=�����������琶�܂��؋�)�ɂ����ڂ��͂��Ȃ��א��҂̈��z�����A�C�O(�A�����J�Ȃǁc)�ł͂ǂ������Ă���̂��낤�c�����A����ȏ㗘�p����E�U���Ȃ��悤�A�����E�����F����肾�B
�@���́A�����ɂ��n�����Ǝd�����ɂ��Ă��c
�@���̖ړI�Ƃ�����͉̂��������̂��c!?�@���߂������R������\�������`���ゾ���̂��̂������̂��A�Ƃ����������Ă��܂��B�@���Ǝd�������I�����邽�тɔ�����ꂽ�A
�@�u�����͉������Ă��A�Ă��ɐ��c���͂����ɂ͂Ȃ��B�v
�@�Ƃł������������ȁA�}�X�R�~���B�܂��A���Ǝd�����̊��S�I���錾?���Ȃ���A���̖�E�������ꂽ���̒S���c���̕������́A������X���i���Ǝ��ꂽ���̕\��B���ɂ��Ďv���c�����͑S�č����ɑ���p�t�H�[�}���X�������̂��A�Ƃ����v���Ă��d���̂Ȃ��悤�ȁc!�@
�@���ʁA�c���ꂽ���̂͑傫�ȋ^�₾���������A�Ƃ������ɂł��Ȃ�c�����͂܂��܂��A��E�����E���z���̒������܂悢���������A�Ƃ������ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���B
�@
�@�U��Ԃ�c���̒��r���[�����Ǝd�������̂���(=��������Ƃ������N�v��ł͂Ȃ��E�P�Ȃ邨�`���́��P���v��j�������哱�������̂����m��Ȃ��c(�J���t���[�W��?)
�@�v���Ɂc���{�̏ꍇ�A�u�������v�Ƃ����̂́A�w�K�̉���(�������ɂ���č쐬���ꂽ����������)�ɂ���ē�������(�Ȃ�킢)�ł���c
�@����c��(�n���c�����܂߂�)�Ƃ����̂́c���Ȃ��Ƃ��Љ��(����)��̌����A���̒��œ�������(=���_�́E�w����)������̕���Ƃ��E�G�l���M�[�Ƃ��Đ������čs���A�����ɂ���đI�ꂽ�A�L���Ӗ��ł̃��X�N���Ȃ�킢��(=�����`)�B
�@(���Ȃ݂ɁA�����������̊��o�ł����Ɓc�ꌾ�ł����A�O�c�@�́w�����h�����x�A�Q�c�@�́w���h�����x�Ƃ������悤�Ȋ�������A�ǂ�����ȒP�ɂ͕]���o���Ȃ����̂�����c)
�@
�@�����͂Ƃ��������A�����_�ɂ����ď��Ȃ��Ƃ����ꂭ�炢�͔F�����Ă����Ȃ��Ɓc�����哱(=�����`)�ɂ��鍡�̓��{�̏ł�(����A���{�Ɍ���Ȃ��c���␢�E�̌���!)�A�������͖{���ɂƂ�ł��Ȃ��Ƃ���ɕ���o����Ă��܂��悤�ȋC�����邯��ǁc�ǂ����낤? �@
�@����c���E�n���c�����N�������܂��܂ȕs�ˎ����c���͂Ƃ����A���ׂĂ͌������ɂ���č쐬���ꂽ���T�E���Ґ��x�𗘗p���钆���琶�܂�錾���ł���c���̗ǂ������͂Ƃ������A�����ɂ͑��̏ꍇ�A���������݁E����ł���ꍇ�������B
�@�w�ǂ��������̒��Ԃ͕K����̉�����x�Ƃ����c(�����哱?�@�����哱?)�A�ėՂ̃L���X�g�̂�(���Ƃ�)�����߂ĕ�����ŗ���悤���A��������̍���̏��B
�@�����������琶�܂�邻���c�P�ɂ́A���܂�ɂ��c���Ȃ��̂�����悤�Ɏv����c!!
![]() �@�@
�@�@
�@����ł́A�����ւ̈�ɏW������i�ƍ����Ȃ�A�L���l�E�����l�̏o�g�n�����Ă��A�����͂��Ƃ��A�E�O���Ɏ���܂ł̂قƂ�ǂ��A�ُ�Ȓ��Ɂu�����ɏW���v���Ă���B
�@�����āc���̗���ɉ����Ă��A�S���I�ɍL��������A�n���Y�Ƃ̐��ށE�x�ƁE�p�ƁE�p�X�c���Ƃ̋�ƁE�p���c������A�����ЊQ�ɓ������B
�@�����͂��̉Ǝ傪�A����p�Ƃ����Y���������Ȃ�����c�܂������肪������Ȃ�����c�܂��X�܂ɂ��Ă��A�x�ƂƔp�Ƃ͈Ⴄ�̂ł���c��Ƃ͔p���Ƃ͈Ⴄ�̂ł���c�Ⴆ�w�Œ莑�Y���x�Ȃǂ́A���̂܂ܔ[�ł���Ă���킯�����������ɗ^����e���͏��Ȃ��A�����̋���ɋC�t���Ȃ��A�Ƃ��������낤���H�@
�@�ꎞ�������A�яZ��̌��z���c���ł́A�傫�Ȍ����̈�p�ɓ��肪�|�c���Ɠ_�����Ƃ������Ȃ�A�Ɖ��S�̂����X�Ƃ�������ȂǂقƂ�nj������Ȃ��A�Ƃ������悤�ȁB�@
�@���Ȃ݂ɁA�Œ莑�Y���Ƃ͉����낤�H�@
�@�̐S�̈�ʏ����ɂ́A��������Ɣc������Ă��Ȃ��c���̑��݂������m��Ȃ��l�������A�S�}���Ƃ��邻���������?�@���L���c�Ֆږ��i���������j�Ȃǂ�h�����߂ɁH�@
�@�Ⴆ�Γy�n�̍w�������āE�V�z(�܁E�����}���V����)�����ď��߂Ēm��Ƃ����l�������A�S�}���Ƃ���Ƃ��c!?�@�����͎x�������ɂ���A����E����̎Љ�ۏ�(�N���E���)�Ɖ���ς��Ȃ��c���Ƃ���x����Ƃ��E���[�ȂǏo���Ȃ��̂�����!
�@
�@�܂������A�u��������v�ɂ��A�c�����w�L�����ԏ�x�ɐ�ւ���_�Ƃ���R�����čs�����c�������A�n���l���̌����E����Љ���}�������A�Ԃ̗��p�҂��������čs�����ŁA�u���ԏ�v���������������ς������Ă���B�܂�A�����y�n�ł��A�����̕~�n�ƁE���ԏ�(�c��)�Ƃ��Ă̕~�n�ł́A�Œ莑�Y�ŗ����Ⴄ�̂ł���B������A����̖��Ȗ�肾�B
�@�����Ƃ�����́A���̗ǂ������͂Ƃ������A�C�O�̐�i���ɂ����݂���ŋ�������������ǁc�����I�ɁA�u����Łv�Ƃ̈��ʊW?�͂ǂ��Ȃ�̂��낤�c?
�@���ɂ��c���^�ŁE�����Łc���ꂾ�����Ƃ��Ă��A���G�ŁE����� ! �Ђ�����������̂��߂�?�Ƃ����v���Ȃ��悤�Ȃ�����ꍇ�E��z�肵���A�ꐡ�̌����Ȃ��K���E�@�����ׁX(���܂���)�Ɛݒ肳��Ă��邻�����c
�@�Ƃ��������c�����܂ł�(�\�����ɂ�)�����̂��߂ɐݒ肳�ꂽ�A����ȍׁX�Ƃ����K���E�@���E�ŋ����c�t�ɁA�����̖c��ȏ�I�E�����I���S�ݏo���Ƃ����A���z�� !�@���Y�ɂ���ẮA���N�E���N�̐\���c
�@���^�ŁE�����ŁE�萔���E���܂��܂Ȍo��̂��߂ɁA�ꐶ���̍��Y�ƃG�l���M�[���g���ʂ������c�ȂǂƂ����b���A�悭�����B
�@�����E�����Ƃ��Ă��c���͗���ł��Ȃ��̂��c!?�@�����͂������A�����̐łɌ���Ȃ�!
�@���Ȃ݂ɐ���A�����ٌ�m���������u�@�����v���`�����X�Ɍb�܂ꂽ�B�@
�@�����O�ƁE��ł́c���̒��ɂ���������ρE�Œ�ϔO�E��ʏ펯�̂悤�Ȃ��̂��A�K�����ƕ��ꗎ�����悤�ȁB
�@�m���ɂ������A�Ǝv���Ƃ���͑��������B
�@���ʁA�������ɂ́A�Ⴆ����������Ȃǂ́A�u�ɗ́E���Ԉϑ�(�@�����k��)�����Ȃ��ŁE������ʂ��ĉ�������A�ٔ��Ȃǂ͍Ō�̎�i�v�Ƃ����F��������A�펯�����ꂽ�悤�ȂƂ��낪���邯��ǁB
�@
�@�������c��������ɗ��ƌ����͂Ȃ��Ȃ������͍s�����A�K���Ƃ����ėǂ��قǁA�L���ȗ���ƕs���ȗ���̐l�Ԃ��������肵�āc�����Ԃł̉����͖����Łc���ʂƂ��āA�o��̖ʂł��A�����Ɩ@�����k���Ƃ̓�d�����ɂȂ鎖�������B�u���߂��疯�Ԉϑ��ɂ��ׂ�������!�v�c����Șb�́A�S�}���ƕ����B
����ɂ́A�����̓����̕��s���E�Љ�펯�̌��@�̖�肪����Ƃ��Ă��B
�@
�@�Ⴆ�c�����́u�ːЂ����A�������d������v�����ł��� ? �@�������c�u���݂̐e���@��Ă̐e��v �u�����e�ʂ��@�߂��̑��l�v �Ƃ������t������悤�ɁA�����c�Ɍ���Ȃ��c���̒��ɂ́A���������E���̕����D�悳��鎖���������ς��݂�Łc�ǂ����E�������A��ؓ�ł͍s���Ȃ����������B
�@�����Ƃ����͈̂ꌩ�A�ǐS�I�Ɏv���邯��ǁc�܂����̗����A��ނȂ����̂�����Ƃ��Ă� (=��E��̌���ɑΉ����Ă͂���Ȃ�?)�c�������A�����̕��Ɋm����(�Ŏ�)�����邩��Ȃ̂��낤���B
�@(�ٌ�m�����Ă����悤��) ���̐��Ƃ����̂́A���オ�ǂ�Ȃɐi��ł� (=�f�W�^��������čs���Ă�)�A�l���ł������A�A�i���O�̐��E�͏����Ȃ����A�ς��Ȃ��B
�@���ʂƂ��āA�����̕�������ۂǍ�����`�I�Ɏv�����肵�āc!? (=������͖��Ԉϑ��Ɋۓ������c!?)�@
�@
�@�Ƃ�����A�J���ӗ~����(��)���悤�ȁA���{�̕��G����?�Ȑŋ����x!�@������(�����)�c�����Ă��Ȃ��A�����̂�����c�����̂�����c
���͂�A���f�B�A�̗͂Ȃ����Ă�!!
�@�u�����̐l�͗₽���v�ƌ�����B����͂���Ӗ��A�J�b�R�������t�Ƃ��Ďg����ꍇ�����邵(=���߉�E�ߊ��ł͂Ȃ��Ƃ�������)�c����ȓ������D���A�Ƃ����l��������R����B
�@�������A�������̐��オ���ꂽ���̓���(���ȁE�]�˕���)�c�܂��A��̒n�搫�E���Ƃ��đ�����ɂ́A���̓����͂��܂�ɂ��f�b�J�C!�@���ɂ��ꂩ��̎�҂����ɗ^����e����(�ӔC��)�́A�傫���Ǝv���B
�@�����A�n���ɕ������E��炸�́A�}���ȉ��g���ɁE����B�@
�@�w�q�b�q���x�̎��ɂ�����悤��(=���������Y��E���ǂ��Ȃ��b)�c����ł͐l��(���{�l)�Ƃ��ĕ�炵�čs���Ӗ����E�����čs���Ӗ����A�܂��܂�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�@
�@�v���c�����ɂ���A����Ȗ�肱���A�}�X�E���f�B�A�̐S�����擱�E���~�����̂ɁA���̂Ƃ���A�S���Ƃ����Ă悢�قǖڂɂ����Ȃ����E���ɂ����Ȃ��B�@���̂��낤 ?
�@(�n������i���ɒu�����悤��)�����ǁc�n���ǁc�̂�����ɂ��A��肪����̂����m��Ȃ��B
�@
�@�Ƃ�����A�����n���̎�҂����̐V���������̂����ɂ��A�����̓��E���̉����́A���͂�A�}�X�R�~�̗͂Ȃ����Ă͂��蓾�Ȃ��C�����邯��ǁc�ǂ����낤 !?
�@�����āc����ȓc�ɂɎ��c���ꂽ�A����҂̎�����m���Ă��E�m�炸���c
�@�u�����N�����x�ł́A����҂��������āA�����̎�҂�������������B�v
�@�Ƃ����c���̈�ʏ����ɂ̓s���Ƃ��Ȃ��A�u�N���x���z�̔�r��葛���v�B�@�n���ł���҂����̑������̂���(���E���E���Z���k���̌��������܂߂�)����Ԃ܂��Ƃ������ŁA���������A�N�̂��߂̊i���_�Ȃ̂��낤�c!?
�@���{�́E�}�X�R�~�́c���́A��������܂��u�������N���L�^��葛���v���u��̂܂łɒǂ����܂ꂽ�Еے��̎����v���ǂ̂悤�ɑ����ė����̂��낤 !?�@
�@�u���v�Ɓu���v�̔N�����x�̈Ⴂ���琶����A�u�x���z�i���̖���v�B
�@�̂́A�������ɂ��w�������x�x(=���̑ސE���E���ϔN�����X�c)�Ƃ������̂������āA���́A�͂邩�ޕ��ɂ��т��������������A�l���̖ړI�Ƃ��E�ւ�Ƃ��Ă���l��������R�����B
�@�����āA�����ۂ��u�N���b�v�ɂȂ�Ɓc
�@�w����ς�A�������łȂ��Ⴀ�˂��c�x
�@�Ɓc�I��͂������̌��t�Œ��߂������A�b�͂����œr�₦��B����͐g����(��)���������g������Ă��鎖�ł���A�܂���R�̓��̌������̕��������g�̕�����(�ւ��������)�������錾�t�ł���c�n���ɂ����ẮA��������(���Ȃ�?)���t�����ɂ���B
���Ԋ�Ƃ��キ�Ȃ������A�n�������ł͂Ȃ��̂����m��Ȃ��B�@���ɂ̊����Ɏ����ẮA���̔N�����������̐��ł͂Ȃ��Ƃ����c!�@���������ꂪ�A���ł��Ȃ��ς��Ȃ��A�n���̎��ԂȂ̂��B�Еے����l�A���́w���́x���ς���������Ȃ̂��B
�@
�@�����āA�������}�X�R�~�����c���̐���ɓ��ݍ��ނ悤�Ȏ��͈�Ȃ��A�b������ꂢ�Ȃقǂ�����I��(�����E�����c�̂�)�A�����̍��{�������ɂ��鎖�Ȃǂ͂قƂ�ǂȂ��B����ł����悤�Ȃ��̐Â����́A����ȂƂ����(�}�X�R�~�̕p��)���̍��{���R���B����Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@
�@�v���c�u���d�̓d�͗����l�グ���v����������E������(�͖̂��N������)��������E�{�[�i�X�̎x�����X�v���A�����������ɂƂ��Ă͓������o�E�����Ȃ̂Ɂc
�@���́A��҂ɂ͍����͑S���֗^���Ȃ��̂��낤�H�@���E�����̂��킸�A�܂����ʕ����łȂ��A�����N�̗\�Z�Ă̒��ɑg�ݓ����A�܂����̒i�K���瓢�c���E���c���E���J���ׂ��ł͂Ȃ����낤���i�c�Ȃ��������낤���j�B�@
�@���������A����(���N��)�u��������v�Ƃ����̂͂Ȃ낤?�@���c�@�ւƂ͈�����悷���́u�K�킵�v�ɂ́A�ǂ�ȋN���ƗR�����B����Ă���̂��낤?�@�u��������v�Ƃ����̂́A���c�@�ւ̑啔���ł͂Ƃ��̐̂Ɂu����v�ƂȂ��Ă��錾�t���B
�@�܂��Ⴆ�A�����@�ւł́u���N�̃{�[�i�X�̎x���z�v�̖��ɂ��Ă��A�N���E������Ƃ��Ď�茈�߂�̂��낤?�@�u���v�Ɓu���v�́u�N���i���v�́A���x���̂��̂ɉ����A�����u�{�[�i�X�̎x���z�v���傫����(����)��ł���A�Ƃ�����Ƃ��畷�����L�������邯���?�@��ʋƊE�ł́u���Ј��v���������čs�����A���̃{�[�i�X�̎x���E�������܂܂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A���̂������Ɂc!�@
�@���ɂ��c��ʎЉ�E�e�ƊE�Ɍ��������A����(�e����)�́u�Ζ��̐��̖��v�B�@
�@�Ⴆ�A�N�����x���唼���߂�ό��ƊE�ւ̑Ή��͖��S���c�ꗥ�E�T�x������ł͂Ȃ��A�ɗ́E�Ƒ����o�ł��������ꂼ��̌���ɑΏ������S�z�肪�ق����C�����邯��ǁA�����ւ̖����̑Ή����A���E�E�}�X�R�~�ƊE�͂ǂ��Ď����E�����Ă���̂��낤�c!?
�@�������E�_�єN���ɂ��Ă�(=���E�����N���Ɉڍs�����ƁE��{�̍����N���ƁE����N���V�ݕ����̎O�K����?)�c�x���z�I�ɂ͌������ɂ͋��炭�����y�Ȃ��Ƃ��Ă��A��������������l�A���������̂��߂̐��x�ł���A�̐S�̑g����(�y�g����)�ɂ͊֗^���Ȃ��A(�E��)�Ǝ��̂��̂������B
�@�������N�̓��{�A�������܂ŔN�����ɘf�킳��E�U���c���������̎������͂߂Ȃ��E���S�Ƃ͌����Ȃ��E�i���E�s�����c�����܂܁c�ɂ��S�炸�A����ɒ�(��)��Ȃ������̐��̂Ƃ͈�́A�����낤�B
�@(�����Ⴉ�肵���A�����̒n�������Ǝv<����>�����l�����ɂ��܂��܂Ȍ��t�E�����ł����ėU��ꂽ�L��������c�����֍s���Ȃ���?�@���z�����c�~�łǂ����낤?�@���Ƃ��c<��>�@�̂�т�Ƃ������ゾ�����Ƃ͂����c)
�@���[�����̂�����Ƃ͂����c�����́A�{���ɂǂ��܂ō��̋ٔ��������{�̏�𗝉��E�c�����Ă���̂��낤�c!?�@
�@ �������A�C�t���Ă���l���������̒��ɂ̓S�}���Ƃ��邯��ǁc���ꂼ�ꂪ�E���ꂼ��̗���ŁA�����Ɍ����Ȃ��Ƃ����c����ǂ��납�A���̌������̐l�����̒��ɂ����G�Ȏv���œ��X�𑗂��Ă���l������̂����m��Ȃ��c�������Ƃ����Ă����̒��g�͂��܂��܂ŁA(������Ƃ͂���)�����ɂ͂����́A�܂�������i���̂悤�Ȃ��̂����݂��邾�낤����B
�@(�������͋C�t���Ȃ�����ǁc�u��V�z���ҋ��̖��v�Ɠ����ɁA�u�������Ƃ����C���v�ɑ���c���ɒn���̐l�����̒��ɂ͖����A�u�m�_�H������v?
�̊��o�̂悤�Ȃ��̂��c�����Ă���c�Ƃ����Α�U�����낤���B)
�@�������A�������̐��E�Ɍ���Ȃ��A�����Ȗ��ԉ^�c�łȂ�����(����Ȋ����̊����Ȃ����E�ȂǑ��݂��邩�ǂ����c)�A���̔N�����͑S�Ă̋ƊE��ΏۂƂ����ۑ�Ƃ��Č������ׂ��ł���c���ꂪ�{���̕����Љ�Ƃ������̂ł���c���z(�x���z)�̖�肾���ł͂Ȃ��Ǝv���B�����A������w������҂����̂��߂ɂ���!
�@�܂��A���̂����N���Ɍ���Ȃ��A�����Љ��Õی�(=�����F�ی�)�E���ڐœ��X�A���܂�ɂ����푽�l�Ȑŋ��̐��������I�ɂǂ��W�J���čs���̂��c����ł̓����ɂ���āA�ɘa����čs�����E�ˑR�Ƃ��Ă��̂܂܂Ȃ̂��c
�@�܂��Ⴆ�A���ڐ����Ԑڐ��Ƃ���������Ɉڍs����čs����(=���X�Ɍ��z�������E���Ɩ��̊ȑf�������ꉻ�E���̉����������팸�ւƂȂ��̂�)�c���X�A��������Ȃ��c�������A����������܂ł��A���łɒ��r���[�Ȍ`�œ�������Ă��錻��c����A���c����Ȃ��Ƃ��������B
�@(�ėՂ̃L���X�g�_=�w�ǂ��������̒��Ԃ́A�K����̉�����x)
�@�N�����x�̂Ȃ���������͂��납�c���������ĞB���ȁc����̐l����(=����)���������ꂽ�悤�Ȓ��Ő����Ă����A����ҁc�������r���悤�̂Ȃ��Љ���̒��Ŕ�ь����A���ӔC�Ȃ������u��r�_�v�B�@
�@�u�����̎�҂�������������v�Ƃ����̂́c���{�I���v�����������A�����܂ł�����ێ��ɂ��ꍇ����������_�ł���c���̒��̏�����Ă�������Ƃ����āc�ˑR�A����̍���҂�ӂߗ��ĂĂ��A�˘f�������c��Ȃ��B�Ă̒�A����҂ɂ��ƍ߁E���̂��������鍡�A�����I�ۑ�ȏ�ɁA���_�I�ۑ�ɂ͂��܂�ɂ��傫�Ȃ��̂�����Ƃ����A��̏��ł͂Ȃ����낤���B
�@�u���́A���������ꂾ���̔N�����A�����Љ����������Ƃ����̂� !?�v
�@�ƁA�s�v�c���鍂��҂͑����͂�!�@�S�}���Ƃ���ɈႢ�Ȃ��B�����ƁA���{�I�ۑ�ɖڂ�ʂ��ׂ����B
�@�������N���L�^��葛�������A21���I(���E�́@��Ƒ�)�̍��A������s���S�Ȑ��x�i��(=�����i��)���̂��̂����ׂ��Ȃ̂��B
�@�����āc����ȓ��{�̏�ł���ɂ��S��炸�c�w��Áx�Ƃ����A�Y�I�E���̌����@�ւ��c�u���{�̑f���炵�����x!�v�Ə̂���A���͂̔ᔻ�ɘf�킳��鎖�Ȃ��A�т��Ƃ����Ȃ��A���������F�ی����x(�c��Ȉ�ɏW���I�ړI��)�ł����Ďx�����c
�@�ɂ��S�炸�A�������g�̕������Ȃ��c�s���E�s�����肪�������A�{���̒��S�E�g�b�v�ɒu����A���扻�����E���d����镗���A�����B����ȍ������Ă��鎞��ɁA�u�f���炵��!�v�ȂǂƂ������t����������Ƃ��������̂����������A���̒��̌����������Ă��Ȃ��؋��Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@�̂́c�u�X�N����Q�v(���l�a�Ƃ��c)�ƌĂ�A���̍��}����ƁA���ꂼ��X�̖��Ƃ��āE���R�̐���s���Ƃ��ē��R�̂悤�Ɏ~�߂��A�����I�Ɉ�Â����߂Ă������̂��c
�@���ł́c�u�����K���a�v�ƁA���̌Ăі���ς�(���̖��O���͈̂�w�̐i���ɂ���ė^����ꂽ�A�I�m�Ȍď̂ł���Ǝv�������)�A�u�ꉭ���a�l�v(���A�a�E�O�H�a�E�K���c)�Ƃ��āc�N�����Ȃ��c�l�̎���E�Ǐ�̗L��E�����ɍS��炸�c�L���A�Љ���Ƃ��ē��R�̂悤�����f���`��������E���x������镗���c�d�|���Ă����āE�ł����Ƃ��c�Ƃ������痐�\���낤���B�@
�@�����́c�Ⴆ�����(��f��)�ɂ���Ắc
�@���̎������߂Â��Ɓc�{��(���f)�͂��Ƃ��A�܂��A���f�̏���(=��f�\��҂̎��܂Ƃ߁E�葱���E�\�Z�̊m�ہc)������|����˂Ȃ�Ȃ��c���ɃT�[�r�X��(���܂��܂Ȓc�̎Y�Ƃ�)�Ȃǂł́c(�傫�Ȍ��f�Ԃ����t����̂�����)���q�Ƃ�������Ȃ��悤�c��f�҂̋Ζ����Ԃ�������E�v���C�x�[�g�̎��Ԃ��������c�ƁA���������̈��E��������̂��߂ɁA���܂��܂Ȗ��𐮂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��c(���N�X�X�̊m��\���Ɠ���)�c�o�c�҂̐S��Y�܂��E���f�Ώێ҂̐S��Y�܂��A���N�E���N�̕����I�ɂ��E���_�I�ɂ���ςȍs���E�K�킵�̈�ɂȂ��Ă���B
�@�������A�l�̎�f�҂ɂ��Ă��A���̑�ς��͓������B���ꂪ����́A��ʏ����̖{���ł͂Ȃ����낤���B
�@�������A���͂��̂��ƂŁc�܂�A��x�͂��f�҂͂��Ƃ��A���̌��f�Ɉ����|�������l�����́c�Ȍ�A�܂���u�ڋq�v�̂悤�Ɉ����A��ʊ�Ɗ��o�E�c�����o�ł����ĕ������i�߂��čs���c�I�@
�@�����Ƃ��c�Ⴆ�A��҂����̊ԂɍL����u�댯�Ȗ��p�̗L�E���v�@�u���܂��܂Ȉ������ŁE�K���̗L�E���v�Ƃ��������ʂ̎���̂���ꍇ�̌��f�Ȃǂ͕ʖ��ł���Ƃ��Ă��c�������A����ɂ��Ă��A���z���c���E�����̈�ł��鎖�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��Ǝv���B
�@���ɂ��A�Ⴆ�c
�@�w�����ی�ҁx�́c���̑O��Ƃ�������ƎړI��(�����I)��f�̏�������Ë@�ւƂ̂Ȃ���(=����)�B�@
�@���̌���̎����E�ӓ_�c�^�}�ɂ��Ă��E��}�ɂ��Ă��A�c�����Ă���l�����͂ǂꂭ�炢�̂��̂��낤�B
�@���X�̐V����e���r�ԑg�����Ă��c���N����퐶���Ɋւ��邳�܂��܂ȕ���̐����̐l�������A�܂�������A�u���̑O�E��a�O�̎p���v�c�u�H�����E�^���E�X�g���X�̉����E�o�ϊϔO�v�c�����Ƃ������̎����́c�������厖(=���N�̂��߂̊�{)�ł���Ƃ��āA�������̒��ɗn�����܂��A����ł����Ă��낢��ȁE���܂��܂Ȍ`���A�h�o�C�X���Ă����̂ɑ��c
�@�����F�ی����x�Ɏ��ꂽ�����@�ւɂ́A�������������͂قƂ�nj���ꂸ�A������f�̏���E��a��̒���I�f�@�E��i���^�c�ƁA��{�I�ɂ͋ɂ߂Ď����I�E�����I�Łc���҂Ƃ̊Ԃɂ��A�ǂ�������������ꂽ�悤�ȁB
�@�����āA��f�҂��A��f��̑O�ɒu���ꂽ���ɕ����A���ْ̋����c����͂��������A�������琶�܂����̂Ȃ̂��낤�c?�@�������A���N�̑����ӎ��̓��Ɏ��o����A�l�Ԃ̖{�\�ł͂��낤����ǁB�@
�@�ł��c���N�̑����c�Ɠ����ɁA��l����p���E�A���t�����E�_�i�����ꂽ�悤�ȁA���̐���ɑ��钷���Ԃ̏K���̂悤�Ȃ��́c�������[������ς̂悤�Ȃ��́c����ȉ������A�������̒��ɂ���Ƃ����̂�����ł��鎖�ɂ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���B�@(�ߔN�͂���ɉ����āA�w�K�����f�E�K���鍐�̋��|�x������B)
�@�܂��A��������ʘJ���҂����������œ����Ă������Ȃ��悤�Ȏ������A�킸�������E���\���Ԃœ���ꍇ������c�����Ă��̍s��́A�����E���������Ă���B
�@�̂́c��a�̂��߂ɕa�@�ɋ삯���݁A��t�̎p�����āA�Ƃ肠�����A�z�b�Ƃ������̂ł��邪�c
�@���́c(�������̎q�ǂ��Ȃ�Ƃ�����)��ԁE���N�̎��o�������Ă��E�Ȃ��Ă��a�@�ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A��t�̎p������Ɓc�t�ɋْ����E�s�����c���ɂ́A���|���������Ă��܂��B�@
�@�u��i���^�̖��v�ɂ��Ă��c
�@�@(�������A��T�ɂ͌����Ȃ������)�c�O���͂Ƃ��������c���\�Ȍ�����������A�v���ΐV��Ƃ����̂́A�u�����v�Ƃ������A�������u����v������?�@�����Ă��̌J��Ԃ�������Ȃ��Ȃ������ɋN����̂��A����p�E���z��(=���f�ƁE�̂��k���铙�X)�B
�@�܂��A�ߋ��ɂ��c�ƊE�ł͍L���E���R�̂悤�Ɏg�p����Ă����Ǝv�����i���A�W�S���̌��ʂȂ��W�Ƃ����^�C�g���ŁA��V���̈�ʂ̃g�b�v�L���Ƃ��āA��X�I�Ɍf�ڂ��ꂽ�����������B
�@�����̖��̂��̌�͂ǂ��Ȃ����̂��낤!?�@���ǂ��ꂽ�̂��낤��?�@���R�̔閧�Ƃ��āA�ˑR�Ƃ��Ă��̂܂܂Ȃ̂��낤��?�@�}�X�R�~������ȏ�Njy���悤�Ƃ͂��Ȃ��B���ɂ͂�����̕��������A�N�����ɏ���Ƃ����Ȃ��قǂ̐[���Ȏ����̂悤�Ɏv���邯���?�@
�@�{�����e�B�A(����V)�ƁE�c��������d�̂��̐��E�B�@�v���A�����{�����e�B�A�Ƃ������Ȃ錾�t�ɂ́A���(���ґ�)�͉�����R�o���Ȃ��B
�@�_�i�����ꂽ�����T�O(=��Â͐_�l�Ƃ�������)�̒��Ő����邵���Ȃ��Ƃ����c������A���̃}�C���h�E�R���g���[���Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@�����A�����ό��n�Ō����������i������ǁc
�@�����d�v��������̓����̂ǐ^�Ɂc�e���g��E���ĎD���f���E��R�̊�����ח��ĂāA�ό��q�����������w�`�o���x����A�n���̈�Òc���ɏo���킵����������(��k�БO)�c(�Ȃ�قǁA�����葁�����@���B)�@��ʂ̊�Ɗ��o(=���q�l�́@�_����)�ł͍l�����Ȃ��A���̖��O�E����𗘗p���������̌����ɑ��āA�˘f���ǂ��납�A�{�肳���o���Ă��܂���(���܂�ɂ��Љ�Ɍ�����!)�B�@����ł́A�܊p���m������A�s�������������ό��q�U�v�̂��߂��w�����z�������ɂ��Ȃ�Ȃ��A���̖A�B�}�X�R�~�ɂ��Ă��m��Ȃ��͂��͂Ȃ��̂�!�@����Ƃ��c���������Ȃ��̂��A���Č��ʂӂ�́A�m����B
�@�W�����������œ��{�̈�Â��x�����W�Ƃ����A(��Ñ��̂��߂�)���̃t�@�W�[��(=�B����)�L���b�`�E�t���[�Y�ɂ��A�ǂ����u�����Ƃ��炵���v��������͎̂��������낤��?�@����ȏ�i�́A�����I�ɂ݂ĉ����܂Ŏ����\�Ȃ̂��낤?�@�����̎�҂������A�ʂ����ĉ��̖������Ȃ������p���ōs�����̂Ȃ̂��c?
�@�����ɂ��A���̋���ȎЉ�\���c���P���c���I�@�ւȂ̂��E���I�@�ւȂ̂��Ƃ����A�w�X���x�Ǝ����悤�ȁc
�@����A����ȏ�́A���̌`�Ԃ��s������L���܂œ��{���܂��܂Łc
�@���͂����Ȋw�ɗ��炴��Ȃ�����҂��c��҂��E�����̌o����D���A�Ƃ������c����ɂȂ�Ȃ�قǁA��Ô�E������������Z����E���̒����������c�I�@���������I�ۑ�E��肪�B����Ă���悤�ȁB�ނ���A�i�X�������j������̕�������������ȓƐ��ƓI�v�f�𑽕��Ɋ܂A�����Ƃ��炵�����݂̑�\�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�����A�P���Ɉ�{�����ꂽ�������Ƃ��Ă̗X���Ƃ͈���āA�����Ƃ����Ǝv���̂́c
�@��ÊE�̌��ꂪ�X���̂悤�Ɉꗥ�Ɍb�܂�E���肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ����A���̌����B�@���́A�����������Łc�f���炵���I�Ƃ܂Ō������Ð��x�Ɏ���c�������A���i�����ȂǑ��݂��Ȃ��A���̋ƊE�ł���ɂ��S�炸�A�ˑR�Ƃ��ĕs���E�s�����肪��������̂��Ƃ����c�����̓��X�̐����ɒ��ڋ����Ă���A�Ƃ����c!
�@����c���팸�ĂȂǂƂ͌����Ⴄ�悤�ȁA���̓��B
�@
�@���������������Ƃ��Ĕ[�߂Ă���̂ɁA���葤�ɂ͉c�����o�ʼn^�c����čs���Ƃ����A���̌���E���ԁB
�@��͂�A���P���c���I�@�ւȂ̂��E���I�@�ւȂ̂��Ƃ����c��ォ�獡���܂ŁA���邪�܂܁E�Ȃ����܂܂ɂ��Ă����A���̋ƊE�̖��͑傫���Ǝv���B
�@
�@(�����Ƃ��A��Â̏ꍇ�A�X���Ƃ͈Ⴂ�A���P�����̂��̂������̂ł͂Ȃ��A���܂��܂Ȋ��҂̑w�c�^�c�̐��E�ݔ����ȂǕ��������ɂ����ĉc�������ނ͓̂��R�ł���E���R�ł���E���R�ł���c�v�́A�����ƍ��{�ɂ����Ă̌��������E�c�������ɖ�肪����Ƃ������œ���Ƃ������B�O�̂����B�j
�@���̖��Ƃ͂����c�܂��l���w�E�̐l���������ōl�����̂ł́A���ƂȂ��Ă͂ǂ����悤���Ȃ����[�����̂����錻���Ƃ͂����A������{�������S�ȁE��i�����ƌĂׂ邾�낤���B
�@�����\���Ƃ��A�ߑ�I���Ƃ��c�I�݂Ȍ��t�ɗU�����ꂽ�悤�ȁc�u�����c�v�����ł͂Ȃ��A�f�p�Ȋ��҂������A(�������E�`�������ꂽ)�u�n���̎��ԁv�ɂ��A�����Ɩڂ������Ăق����B�@
�@�u�ǂ������q�������B��x�A�a�@�֍s���Ă݂悤�B�v
�@�ƁA�߂��̓��ȁE�O���c����҂������삯���A���̍������������B���S�������獡���܂Łc���܂��܂ȏo��A�����^�����钆�ŁA�u�a���v�����R�̐���s���̈�Ƒ����A���Ȃ��Ƃ��A�����̑��́E�����̊��o�ŊǗ����Ă����B �{���̖L�����Ƃ͉����낤�B��l�E��l���w�����������E�\�͂����W���ꂽ�Љ�x�ł͂Ȃ����낤���B
�@����肱���́A��Â̌���̐l�������g�̕�����w�E����Ă�����ł���A�Ƃ����̂��ǂ��؋����B
�@�́A���j�͕s���̕a�Ƃ��ꂽ�B�ł������́A�}�X�R�~�̑䓪���Ȃ��A�܂�����̂悤�Ȍ`�ł��u�c���f�v��c�ی��v�̂悤�Ȃ��̂͑��݂����A��Ñ����E���ґ��s���̕a�v�Ȃǂƌ��ɂ��鎖�Ȃ��c�ǂ����E�������A�o�����Öق̓��̗����c�Ƃ������悤�Ȍ`�ŋC���������A�~�߂čs�������Ȃ������c���R�́A�܂������Ȃ����Ɉ��i�䂾�j�˂������Ȃ������B
�@����������͐i�݁A�Ȋw�E�����̔��W�ɂ�����L���Ȑ����E�Љ�����^�����c�C�t���Ă݂�A���j�͂��̊Ԃɂ����R�����̂悤�Ȍ`�Ŏ������̑O����p���������B�u�\�h�ڎ�v�͂������Ƃ��Ă����{�I�ɂ͂�͂�A�������ł���A���̍��ɂ����̂Ȃǂł͂Ȃ������Ǝv���B
�@��Âɍl����c�܂�����Ȏ�����}���Ă݂�Ɓc�Ȃ܂��A���́c�V��j���E�\�c�ЂƂ��炰�E�ꗥ��ӓ|�̈�Ð��x�̓����E����c���Ȃ����������K�������B���Ȃ��Ƃ����̂悤�ȁc���R�̌����E���������A�}�X�E���f�B�A�ɂ�邻�̎���E����̎Љ�ʔO�E�Љ�펯�E���w�Ö@�c���D�悳��c���ʁA��ւ��E��ւ��g�����o���Ȃ�!�@�����������z�������������̂悤�ȎЉ�ɂ͂Ȃ�Ȃ������c�Ƃ������͌����Ȃ����낤���B�@
�@���́c�H��H��c���̂W�O�������_�I�v���ɂ���Ĕ��ǂ���A�ƕ����Ă���B(�����Ƃ�����́A���Ɍ���Ȃ�����ǁB)
�@���_�Ɠ��̂������p(�����K���c��C�c�Ȃǂ��܂�)�ɂ���āA��̐l�i�����݂���c����Ȓ��ł̌���ɂ����邱�́A�u�K���v�Ƃ������݁B
�@����������c���ɂ��K���Ƃ́A������w�X�g���X�̉�(�����܂�)�x�ł����c���̓��������R�ŁE�C�܂܂ŁB�v���A�u�K�����f�v�E�u�K���ی��v�Ƃ����A���̈ٗl�Ƃ��v��������u�K������ʂȑ����Ɏd���ďグ��v�Ƃ��������c�U�� !�@�܂��Ă�������w�������A�X�g���X�͂܂��܂������čs���c���z���B�@
�@����ȉȊw���\�̌���ɂ����āA���������E��������������Ȃ����ł���ɂ��S��炸�A�u���f!�v�u���f!�v�̏���c���ɂ́A�����ɂ����A���̍ő嗝�R�E�|�C���g���B����Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������!?�@
�@��I��(��c����p�����n�D�E�K���I�Ȃ��̂��܂߂��c)����������c�܂��܂������āA���H�E���H�ւƗU�����ނ悤�ȁc�u����A3�`5�l��1�l���K���̎���ł�!�v�Ƃ����Ăт����c���������A����ړI�Ƃ������f�Ȃ̂��낤�Ǝv��!?�@
�@���̘_������d�����c���_�_(�P�Ȃ�S���w�ł͂Ȃ�)��a(���낻)���ɂ��Ă����A�����u�c�P�v�ƌ��������c�������l�Ԃɑ���A���R�E�̉��V�E�x��!�@����Ȏg�������������̑�\�ɂ���̂��A�����w�K���Ƃ������݁x�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�v�����S�Ă����E����E���t�ɂ͖��������c�����v���Ζ{���ɂ����Ȃ�c�����v���Ζ{���ɂ����Ȃ�A�Ƃ����̂��l�Ԃ����A���ꂪ��{�ƂȂ��āA�H�~�s�U�E�t�ɖ\���\�H���h�{�̃A���o�����X�E�^���s������a�c�ɂȂ����čs���Ƃ����B�l�Ԃ͗ǂ����E�������A���t�̗U��(=�}�X�E���f�B�A)�ɂ���Ċ�d�ɂ��ς�鎖�̏o���鑶�݂ł���c�S���̂ɏ]���Ƃ������́A��ɂ��蓾�Ȃ��̂ł���!�@
�@�܂��A�ėՂ̃L���X�g�͋����c��i���̐l�X�́A�w��Ђ��x�̂��߂ɕa�����Ƃ���čs���c�ƁB
�@�X�g���X�c���܂��܂Ȗ̈��p�c���ɁE����Ȑ^�������ɂ���A���̓��{�B�@����҂Ɍ���Ȃ��A���ɍ��̎�������ւ����ՂȖ�i���^�c�����i�K�ɂ���Ƃ����v���Ȃ��A��X�̖E�������c�����Ƃ��炵�����t�ɂ���āA���Ƃ����₷�����p����E���p����錻��́A�[����!!�@
�@�w��肩���x�����w���x�܂Łc�����̏ォ��ڐ����c�����o�ł����Ĉ�ÂɊւ��߂��ė������ʂ�(=�ߊ���)�A���̓��{�̎p�E���ԂƂ͌����Ȃ����낤���B�����d�E���ȊǗ��ւ̌y���c���z�B
���̂̍s���@�@�S�̍s��
�@�܂��c��������Љ��ł���A���R�A�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�w�����x�w��n�x�̖��B���Ƃ��U���ł����Ă��A����Ȃ�̖@�������݂��邾�낤�B���܂��܂ȑ����V���E�h�Ɛ��x�c�@���c���Ȃ̂��E���Ȃ̂��A�����ς蔻��Ȃ�!�@
�@
�@�����̏ꍇ�A�ߔN����������łȂ��A���܂��܂Ȍ����c�́E��ƒc��(=JA�Ȃǁc)������ɉ�����āc�Ⴆ�w�����x�̃n�K�L�ɂ́c�u���ɏ������Ԃ��̋V�͌���u�̈ꕔ���Љ�����c��ւ̊�t���Ȃ��āc�v�Ƃ����������K���L����Ă��邯��ǁc�����Ɋ|�����ŋ��́A����I�Ɍ����@�ւɗ����̂ł͂Ȃ��A�Љ�̒��ŏ����̂��߂ɂ��܂��z�����Ă���̂��낤���B�@JA�A�Љ�����c����ĉ����낤?
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����c���j������l�͌����̐ӔC�҂ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��c�ƁB
�@����͌����đ傰���Șb�ł͂Ȃ��c���܂��܂Ȗ��̂��̍��{�ɕԂ�Ȃ���Ή������Ȃ����낤�A�C�̉����Ȃ�悤�ȍׁX�i���܂��܁j�Ƃ��������ɉ����t����ꂽ�A�����Ƃ��炵�������I�K���E�@�����A���{�ɂ͂��܂�ɂ����߂���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ�����ǁc!?�@
�@�@�u �S�[�͑�n�Ɂ@���͐_�Ɂ@�v���o�͈⑰�̋��� �v�@
�@�@�@�@�@�@ < �u�X�E�F�[�f���̎U���v (HP�E���ւ̑��E�f�ڕ�) ��� >�@
�@�����Ă���Ɂc���܂��܂ȋƊE���w�ӎ��̓]���x�����߂��鎞��B�܂��A�n���S�̂��u�l�ނ́@ ��Ƒ��v��ڎw������B�@
�@�v���A�n����3����2���C !�@�C�m�J���E���f�G�l���M�[�̔��@�Ɠ����ɁA���̖���(=�[��)�A�C�m�������������ŁA���̉����߂鎞�オ����ė���̂��낤���c�ǂ����낤?
�t�͖��݂̂̕��̊����c
�@�����āA����Ȓ��ł��ˑR�Ƃ��ėv��������A�^�}�E�}�X�R�~�ɂ��A�������ň��c����ɂ���ċN����A���z���B
�@�w���Ɓx�͂������A�w������Ɓx�ɂ��Ă��A�܂����������\�Ȏ{�݂�����̂Ȃ�����c�����A�}�X�R�~�ɂ���������E���グ�悤�Ƃ�����Ȃ��l����Ȃǂł́c����ł�����ƕ�������Ȃ��Ȃ�͕̂K���ŁA�̐S�̂������i�̉��i���t�ɒl�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�s���S�ȉ��i�����B�����Ă���́A�d�����i�c������c�ٗp�E�l������ւ����z���ɂȂ���Ƃ����A���X�����̌J��Ԃ��B
�@(�������́A�Ⴆ��365���̐H�i�Ȃǂɑ��ẮA���Ƃ��R���r�j��X�[�p�[�ł����Ă��A���̒��ł�����Ɋi���̏��i�悤�Ƃ��āA���ꂱ�ꕨ�F����K��������c�܂��ď����ƁE�l���X�ł���c)
�@���̓��{�̏�ł́A���̑��Ƃ������܂܂Ȃ�Ȃ��B�O���[�o���P�ʂ�(���E�P�ʂ�)����������Ƃ��Ă��A����͈��̓��{�E�o�ł����E���{����ł���c�s���S�ȉ��i�����ɕς��͂Ȃ��Ǝv���B�@
�@�����ɂ����Ă��c���́A�o�u������゠����?����̌��ۂ��낤���A�W���ƁE�L����Ɗԓ��u�̍����A�����W������ǁc
�@����ɂ��Ă��A�\����(=�����)�͂Ƃ��������c����A���̒��g���E���̖ړI�Ƃ�����̂�����Ȃ��c�����I�Ɍ��ĉ����s�����̂悤�ȁE���̂Ȃ��悤�ȁc�Њd(������)�̂悤�Ȃ��̂������������c�����A(�����͂�������ǁc)��Ɗԓ��u�̌o�c���j�̈Ⴂ����A�t�ɐV�������E�ۑ肪�������肵�āc���ʂƂ��Ă���́A���̌���(=����ғ�)�ɂ��e���������炷�Ƃ����c���ǂ͂�����A�������z�̌J��Ԃ��Ȃ̂ł�?�@�ƌ������悤�ȁB
�@
�@�������A���̒��ɂ͖��̂��鍇�����S�}���Ƃ��邾�낤���͕����邯��ǁB
�@���{�E�}�X�R�~�́A�d�v�Ȗ��E�ۑ肪���������A���̌����E�A�����Ƃ��A������Ƃ��̑�䏊�ɋ��߂�Ƃ������K�������邯��ǁc
�@����ɂ��Ă��c�����Ɏ����Ƃ��ē`����ė���悤�Ȃ����v�͉����Ȃ��A�Ƃ����̂������̂悤�Łc���̏K�����A���̑�䏊�̗���d�����A�P�Ȃ銯���哱�ɂȂ���g�D�[�ł߂́E�`����̂��̂ɉ߂��Ȃ��̂ł�?�@�ƌ������悤�ȁB�@�����̂��߂ɖ{�S���炻�̉����߂Ă���Ƃ́A����v���Ȃ��B
�@�_�l��100%���ꂽ���R�̐��������́c���Ƃ��S�b�̉��E���C�I���ł����Ă��A�����̌������ǂ�Ȃ��̂ł��邩���S(%)�����m�̂����ł�����c
�@���̑啨�̓����������E����瓯�u�œk�}��g��łȂǂƂ����A��������I(����I�j�Ȑ������͌����Ă��Ȃ�(=���ꂼ��̌��d���鎩�R�̎d�g�݁E������������E����Ƃ������ӎ��̂����ɁA���̖{�\�Ŏ��o���Ă���)�B
�@�Ⴆ���A�������R(�R)�̐��́c�������̂悤�ɁA�~�₽���E�Ēg�����ł͂Ȃ��c�~�͂ق�̂�Ƃ����������A���̓q�������Ƃ����₽���B������Ȃ���A���R�̎d�g�݁c�l�G�̍��E���{�̂��߂��V�̔z���ł��鎖�ɋC�t��������c!�@
�@�~�₽���E�ĉ������Ƃ����̂́A���̏�̕����I�E�Ȋw�I�_��(�Z���I�W�])�Ƃ��Ă����l����A�����ɂ��������Ƃ��ŁE������O�̂悤�Ɏv���邯��ǁc�܂��Љ�L����A�������Ȃ��������ς�����ǁB
�@�ł��c���ꂾ���ł́A�����ɂȂ��鉽���������Ȃ���(�����I�W�])�A�����Ȃ��B�@�s��ւ̈�ɏW���c�Ȋw�E���w�̔��W�ɂ���Ă��܂��܂����R�̕��c�l�Ԃ̌��܂ł����A�����ꂽ�܂܁E��������Ȃ��܂܂ɕ���s���A���{���B
�@�_�l�ɂ��Ă݂�A���{���_�ƍ��Ƃ��ꂽ�̂́A�����̂��߂݂̂Ȃ炸�A���E�̂��߂��_�ƍ��Ƃ��ꂽ�̂����m��Ȃ��̂Ɂc!?
�@�u�߁v�u�H�v�u�Z�v�̑S�Ăɂ����āc��ËƊE�������c�܂�ŗ����Ƃ̂悤�ɗ���čs���A���̓��{�Љ�c�n���̎��ԁB�@
�@�̂̂悤�ȁc�d���ĕ����Ƃ��E�I�[�_�[���[�h�c�Ƃ���������̕i�c��������E���S������E�ߋ�����c���̌���(�a�؏Z���j�������A�߂����茸����(�i����֗��ȗA���ނ�D��)�c�l���̏��Ȃ��Ȃ����n���ł́c���̎��v���E�������K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ������Łc���R�̗���E���ۂƂ�������܂ł�����ǁB
�@�w���v(����)�̗���x�͂Ƃ��������A���̑O�ɂ܂��A�w�����̗���x�̖�肾�B
�@(�v���Ώ������́A�X�����c���Ƃ�������v�ɒ��݂Ȃ�����A�����̓��{�̏�܂��A����ł͂܂������ł͂Ȃ��A�Ɣ��f���ꂽ�c������<����}>�ɂ����ẮA���̗X�����v�̈��p���������Ȃ�����ɂ��ꂽ�܂܂ł���c)
�@
�@���߂Ďv������ǁc����ȏ��ɂ����āA����͂��������A�N�̂��߂́E���̂��߂̑��łȂ̂��낤 !?�@
�@���z�Љ����(=����Œ��S�Љ�)�ɂ́A�܂��܂����E��ւ������ς������ǂ����Ă���Ƃ����̂ɁB
�@�u�����v�u�����v�Ńf�W�^��������čs�����Łc�������瓾����݂͂̐���������(�Ȃ�킢)�̎��Ƃ����K���B(�������A�f�W�^�������̂��̂�����̗����ł���A���_�͂����ς����鎖�����m�̏�ŁB�j
�@�ꐡ�̃X�L���^�����A�Ƃ肠�����̌��ʂ��瓾���A���E���̑f�����}�X�R�~��(���_����)���ӎ����邠�܂�c�̐S�̌���(�Љ�)�̎���Ȃǂ��S��z��ɂ��E�]�T���Ȃ��Ƃ����A�s���S�ȓ��{�̐��E�̎����B
�@���̂����A���ꂼ��������グ��̂ł͂Ȃ��c���̃e�[�}�������܂ł��o���̌���E���n�ɗ����Ă��ꂼ��ɁE��̓I�����͂������̂ł��Ȃ��A����̋�_�ɂ��藊��c
�@�Ⴆ�Έ�̐���ۑ�E���s�҂̎v���ɑ��Ă��A���ꂪ�X�|�[�c�ł���u�Q�����鎖�ɈӋ`������v�ƁA�����E�����̑O�ɁE�o���̗���ŗE�C�t���E��܂��̂��c���ł����đ��E�^�����E���Α����\�c�ЂƂ��炰�ōi�荞�݁A���Ƃ��ґ��ł����Ă��A�s���̕����E�����Ƃ��̕����E���Ȃ̕������c����Ă���̂����m��Ȃ��̂Ɂc�c�����u�̌��S�ȓ��c�̂��߂̋�����ǂ��A���E�l�i���ɒǂ����݁A���{�ۑ肩��͊O�ꂽ���ʂȏ��ޗ��E���E���̔ᔻ�_�����ł��o���E�h�������c
�@���ʁA���v��x�炷�̂��A�}�X�E���f�B�A !�@���{�I���v��K�v�Ƃ��A�͍������̃A�b�v�E�_�E���ɐS��D���Ă��鎞�ł͂Ȃ��̂� !�@
�@���Ȃ݂����_�����Ƃ����̂́c���̓��e�ɂ��Ƃ͂����A�Ⴆ���ΘJ�҂̗����ŃA���P�[�g�ɉ�����̂ƁA�o�c�ҁE�w���҂̗����ʼn�����̂Ƃł́A���̉ɑS�R��������̂�����A�Ȃ��Ȃ����_���o���Ȃ��c�K�������Q�l�ɂȂ���̂Ƃ͌���Ȃ��Ǝv���B�܂��A��������ΏۂƂ������_�����Ȃǂ́A���������E�����������Ȃ��B
�펯���t�]������ÊE
�@�������A�����Ɍ���Ȃ��B�@�Ⴆ������ÊE�̑������A��l�̐l�Ԃ̊��̕ω�(=���ށE�ސE�Ȃ�)�c�܂��A�l���ꂼ��̌��͖������A�Ȋw�݂̂ɌX�����A�\�c�ЂƂ��炰�ő��E�w�F�m���x�Ɏd���ďグ�A���҂̖���������t���E�Љ��Ւf���c���ʂƂ��āA�t�ɉƑ����E���҂S���ʂɓn��(=���f�E��Ô�ƁE�Ƒ��̘J�����Ԃ�D��)�˘f�킹��c�Ƃ����̂Ɠ��������Ȃ̂����m��Ȃ��B�~�ς̂��߂���Ë@�����A�t�ɕ��S���ʂɓn��Љ�������Q�������炷�Ƃ����A���z���c!�@�@
�@���R�Ƃ͂����A���̂����F�m���Ƃ����̂ɂ́A�����Ԃ̐ςݏd�˂ɂ�邻�ꂼ��X�̎���甭�ǂ������̂��قƂ�ǂ̂悤�ŁA��ÂȂǂŕЕt����Ƃ������P���Ȗ��łȂ����́A�f�l�ڂɂ����炩�Ȏ��ł���c���̏�ɂ���ɁA��i���^�ƂȂ�c����͂����A���z�ȊO�̉��҂ł��Ȃ��I�@
�@�F�m�ǂƐf�f����A���̑��k���Ȃ�������ˑR�A�{�݂ɑ��荞�܂ꂽ�l�����ɋ��ʂ����A���̍��݂ɖ�������E��c�\��c���A�������ؖ����Ă����@�@
�@������Ñ��Ƃ������A���҂̉Ƒ����g�����悵��?���l�E�F�m���ƌ��ߕt���A�F�m�������ɂ�����Ȃ��A�������q����̎Љ���c�u�����́E�s���̖����v�����������̑f�ʂ����i���g�D���ݒu���Ă��邾���j�c���E���(�c��)�ɉE����Ƃ����A�ꗥ�E��ӓ|�̖����̂��̗���c�Љ�ʔO�c�������ɂ́A�ƒ���s�a�c�o�ς̕���B�@
�@�̂��c�u���̖Y�����Ђǂ��Ȃ��āc�v���炢�̌��t�ŕЕt���Ă����悤�Ȗʂ�����A���w�Ö@�I�Љ���Ɍb�܂�Ȃ��������A�t�ɂ��̎����K�����A���l�ɂ��������}�����E�䖝���̂悤�Ȃ��̂�������āA���Ȃ��Ƃ����̂悤�ȁA���E�a�@���Ƃ��E���@�ȂǂƂ������z�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@�Ⴆ���́A�u�C���t���G���U�v�ɂ��Ă��c���̂悤�ȕ��G����?�Ȍ��ۂł͂Ȃ��c���M�E������݁E�P�c�Ƃ������悤�Ɂc�߁E�H�E�Z�̂��ׂĂɂ����āA�ǂ������������������P���ŁA���̋�C�ɂ����R�����������B �u�C���t���G���U�v�Ƃ����A���̖��O(�a��)�������Ȃ��A���R���ۂɑ��鎩���̕s���ӂŕ��ׂ��Ђ����Ƃ������o�c���E�a�@�ł͂Ȃ��A�H�ו��E���ݕ��ɔz�����Ȃ���A�ɗ́E������(�Ƒ���)�������Ƃ������̂������B
�@���́A�}�C���h�E�R���g���[�����ꂽ�Љ���B�����������̖��E�ۑ��c��Ð��x�̍��{(=���R���ɉ������̗͍��)�����₢�����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ďd�����Ȃ������ !?�@��l�E��l�̌��E�l���͉��̂��߂ɑ��݂���̂��낤�A�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ȁc
�@���̌��ۂ��A�w�F�m���x�Ɍ���Ȃ��B
�@���̎��肾���ł��c�Љ���ɔ��E�ǂ����܂�c��Q�ɂ���N(����)�E�T(����)�E�N�E�T�c�̌J��Ԃ��̂��߁A�o�����������������z�ɚb(����)���l���́c�V��j�����킸�A�����ς����݂���!�@���Ȃ��̍s���ׂ���́A�a�@�����ł͂Ȃ��̂ł�?�@�ƌ��������Ȃ�悤�ȁB�@
�@�����āA����ȏ�Ɂc��������z���ɚb���l��(����)�ɑ��ĉ��̎藧�Ă��u����̂ł��Ȃ��A�V��j�����킸�A�܂�Ōڋq�̂悤�Ɉ����A������f�E��i���^�c������f�E��i���^�c�𐔔N�`�\���N�ƌJ��Ԃ����҂������A��Ì���̎��ԁE���̂��āA���������A�����낤 ??
�@�܂��A���̓��@���҂̌������c��Ñ��̎���Łu�]�@�v��]�V�Ȃ����ꂽ�ɂ��S��炸(=��a�@���珬�a�@��)�c���Ƃ͂����A�c�����o(=���҂̎������E�\��)�ŕ������i�߂���c�ˑR�̑��z���]�@���E�����㓙�X���������ȂLj�ÂɊւ���c��ȏ��o���̔����c�����A���ہE���ۂ̖����̎x�����E��a���̊������S�͈ˑR�Ƃ��đ����Ă���̂������A���ǂ́A�u�����ی�蓖���v�ɗ��炴��Ȃ��Ȃ�A���̎��i�̐\���Ƃ����A�܂�ŗ����Ƃ̂悤�ȁB�@������A���z���̌J��Ԃ�!�@
�@�G�b?�@�܂���!?�@�Ǝv���悤�������ɂ���Ǝv����l����(=�L���l)�܂ł����A���̗��ł��u�����ی�v�ɗ��炴��Ȃ��A��Ì���̎��� !�@�����瑛���ł��d���Ȃ��A���ł͂����̏o����u��ÊE�̏펯�v�̂悤�ɂȂ��Ă��邻��������ǁc��ÊE�Ƃ����̂́A���Ȃ̂��H�@���Ȃ̂��H�@�����ς蔻��Ȃ��B�@�@
�@�c�����Ƒ����v���A�����Ό����|���E�R�c�R�c�ƒ��߂���Y���c�v�������Ȃ��A�킪�g�̂��߂ɁA��u�̓��ɏ����čs���c!�@
�@���R�Ƃ͂����A���̒��ɂ͖����Ɏx�����ׂ��A���z�̐ŋ����܂܂�Ă���B
�@
�@����o�Y�ɂ��Ă��c�������A�ꌾ�ł͕Еt�����Ȃ�����ǁc����͐̂��炠�������ۂŁc���l�̐������ւ̐S�z��͑厖�Ƃ��Ă��A�������芪����Ê��ɁA���̂悤�ȉȊw�E���w�ɗ��������̑Ή��ł͂Ȃ��A�����������R�����������悤�ȋC�����邯��ǁc?�@�@(�����A����o�Y�̎q�������B)�@
�@��Â���l�Ԃ͂܂Ƃ��ŁA�Ȃ��l�Ԃ͕s�K�ł���Ƃ����c���R���E�Љ���ɑ�����ÊE�̏펯����펯���C�t���Ă݂�A�̂ƍ��Ƃł͂Ȃ��t�]�����悤�ȁB(�c�����悤�ȁA�ł͂Ȃ��A���S�ɋt�]���Ă��� !)�@
�@�܂��A�l�ԒN�ł�����A�u���a�v�̂悤�Ȃ��̂�����Ă��āA���ꂼ�ꂻ�̐l�Ȃ�Ɂc�������̐l���c�������Ɏ~�߁E�Ώ����čs�������(�t�������čs��)�c���̈�w�́A���̎��a?(��?�j�������ٓ��ɂ��鎞�_���猩���o�����Ƃ������Ȃ̂��낤��?�@�����������Ƃ�����?�@�L���悤�ȁE���f�̂悤�ȁc����́A���(��)�ɂ܂ł����̂ڂ�l���Ȃ���ǂ����悤���Ȃ����̂Ȃ̂ł�?
�@���l�̓w�͂����������K�v�Ƃ��Ȃ��A�܂�ŁA���{�b�g�̐��E�ɂł����荞�܂ꂽ���̂悤�ȁc��ꂽ��̂āE��蒼���c��ꂽ��̂āE��蒼���c�O��(����)���f���炵�������ŁA����ȏ�̂��͓̂`����ė��Ȃ��B�@���ǂ͂�����c�u�ߓx�̌��f�v�ɂ���Đ��܂��u��I���ւ̖��z���E�j��v�Ƃ����A���z���̌J��Ԃ��B
�@���Ƃ����N�ŎY�܂�Ă��A���E�ǂ�Ȏ��E�ǂ�ȍГ�ɏo������������Ȃ��c���ꂱ�����_�l����^����ꂽ�A��{���y���������l���Ȃ̂ł� !
�@�v���A�������g���g�����q�ł͐i�܂Ȃ�����(�Ȃ�킢)�ł���̂ɑ��A�}�X�R�~���\�c�ЂƂ��炰�œ˂�����Ƃ����̂͂ǂ��������������A���蓾�Ȃ��B�@�����Ƃ͐�(�܂育��)�ł���c����ȁA�P�Ȃ闬�s�ɏ���������悤�ȁc�����E�����̂悤�ȁc�\�ʌv�Z�ꔭ�ŏo����悤�ȂȂ�킢���낤���B
�@���̎���ɂ��J��Ԃ��ė������Ƃ͂����c�����I�ɂ͂Ƃ��������A�܂��܂��A��I�ɂ��������ȁA����ȓ��{�̏���B
�@�S���o���Ă��Ȃ��̂ɁA�Ȋw�͂ǂ�ǂ�i��ōs���c!
�@������A�s�킩�獡���܂ŁA���m�v�z�c�A�����J�i�C�Y��ӓ|�c�̒����Ă����A���������{�l�ɐ��ݕt�����K���̂悤�Ȃ��̂��琶�܂�鉽�����낤���c?�@���{�ɂƂ��Ċ̐S�̂��̎��c�A�����J�́c����ł����悤�Ȃ��̐Â����́A�����Ӗ�����̂��낤�B
�@�������A�������̂���ł͂Ȃ��A�V�g������(�w��p��)(=���l�E�������̗��� )�E�n��V���̃��f�������Ƃ��Ă��A�����J���瓾���A�ǂ����́E��Ȃ��̂������ς�����c�ނ�ɂ��Ă݂�A�����͌����ĈӐ}�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u�키�����v�����Ƃ��E��c�Ɏ��Ƃ����A�����J�c�P�������Ƃ������A�����I�E�P���������A�����J�l�C�� !
�@�����A�����(=�A�����J�l�C�������{�l�C��)�����܂��g�ݍ��킹�E�����̂��̂Ƃ��āc���{�̌��E���R���ɍ��킹�Ďd���ďグ��c�����E�����S��{���c�Ƃ����͗ʂɌ����Ă����c�Ƃ������͏��Ȃ��Ƃ������Ȃ����낤��?�@���ƂȂ��ẮA��������_�E�����ɏI����Ă��܂�����ǁB
�@��Ö���ɂ��Ă��c��������E�̎w���I����ɂ���i������?�j�ɂ��S��炸�A�A�����J�ɂ͖������{�̂悤�ȁu���������F�ی����x�v���ꗥ�ɑ��݂��Ȃ��Ƃ����̂ɂ́A����Ȃ�̗��R�����邩��ł���ɈႢ�Ȃ����c�I�o�}�哝���̊�]���j(=�����F�ی����x�̓����E�I�o�}�P�A)���A�ꌩ�A���z�Ɏv���Ă��c�����A�w���R�d�����č����x�ɂ��Ă݂�A�����ɂ͂���炪�K�������ނ�̋��߂闝�z�Ƃ�����̂ł���Ƃ͌���Ȃ��c���̂��́A���{�̈�Ì���E�����̎U��X�X�E�o���o���Ȏ��ԁE������(=�c���Ȃ̂��E��c���Ȃ̂��c)���v���A���X���B�@
�@(�Q�l�̈���c��@������ �w���݂䂭�卑�@�A�����J �x �W�p�АV�����@�Ȃ�)
�@�u�����F�ی��v�Ƃ����̂́A���Ȃ��Ƃ����̑�O��Ƃ��āA���Ɓc�Ƃ������A�����́c�����I�E��I��{�E��Ձi���o�ϗ́E�]�����j���ꗥ�ɔ�����Ă��Ȃ���ΐ��藧���Ȃ����x���Ǝv������c���̓��{�̏��v���c�܂���҂����̎������E�p�����c���������v���c�܂����E�P�ʂŕ������l���čs���Ȃ���Ύ��c�����c���E�����R�ɍs������E������c�Ƃ������㌗�ɂ����āc�����E�ǂ����ɒ�R��������̂́A���̎��������낤���c!?
�@�܂��A���Ƃ��i�C�㏸�ɔ�����V���z(����)���A�b�v���ꂽ�Ƃ��Ă��c�����ɁE����ɔ�Ⴕ�āA�Љ�ۏ�(=�N���E���)�̌��X�̎x�����z���A�b�v��������A�����E���z���l����Ɓc(�o�c�����܂�)�ȒP�ɂ͊�ׂȂ����̂�����悤���B
�@�ΘJ�������|�I�ɑ������̓��{�Љ�ł́A�����E�����̕ی���(��������)�����炪�Z�o���A�܂����N�̐\���Ɏ��炪���ڏo�����킯�ł͂Ȃ��̂�����A���䗠�܂�A�o�c���قǂ̕��S���E��R���͂Ȃ��A�C�t���Ȃ��ꍇ���قƂ�ǂ��낤����ǁB�s���E���t�ł����A������J���C�t���Ȃ��B����ǂ��납�t�ɁA�u�f���炵��!�v�Ƃ܂ŏ������Ă���̂�����A�S�Ă��}�C���h�E�R���g���[�����ꂽ�����ΘJ�҂̗���ł���A���X���낤�B
�@�������c������Ƃ����āc�܂�A����ȕ��䗠�̋�J�ɋC�t���Ȃ��A����ȋΘJ�҂̗���ł���ɂ��S�炸�A���̎Љ�ۏᐧ�x�Ɍ����Ė������Ă����ł͂Ȃ��c�t�ɁA���������̎��ԂɎ����������U���E�Y�܂���c�Ƃ����v���Ă���A���̌��� !�@��������̖����E���z�� ?�@���ʂƂ��āA���������A�N���������Ă���̂��낤 ?
�w����Łx�𒆐S�Ƃ������z�Љ�
�@���Ȃ��Ƃ������I�ɂ́A���̍���҂��̌����Ă����悤�ȁc���ʂ̑����E�����I�E�����I�Ȃ��̂ւ̏o��͌������A�w��Áx�ɑ��Ă��A�w�{�i�I����ł̓����x�ɂ�������̂����́c����ނ���A��Ñ��̖����̂����ɂ��A���������������E����I�����������c�C�O��i���̂悤�����Ƒ̐��̈�Ð��x(=���łŌ����ȑҋ��E�ݔ���)���~����čs���ɈႢ�Ȃ��B���̏ł́c��J���Ă���e(����)�̂��߁A�q�ǂ�(����)�������ŁE�����̎��Ô���x�����Ă���(=��Õی��{����̊������S�{����̕������������o��)�A�Ɠ����������c(����A�����ł͂Ȃ������ł���E�����̐��̂��߂ł���
!)�@
�@����̔[�߂�ŋ����A�[�ŎҎ��炪�{�ƈȏ�̕����I�E���_�I�G�l���M�[�𒍂�����ŎZ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Љ�̎d�g��(�\�����x)!�@�܂����Ƃ���Ñ��ł����Ă��A�����E����Ă���̂��E���Ȃ��̂��c�Ƃ������A�ǂ���̗���ɂ����Ă��s����ȁE�B���ȁc(�����E���肵�Ă���̂́A�������E���������B)
�@�܂��c�y�䂳���������肵�Ă���A�N�������ɗ���Ȃ��A���ꂼ��̌��E�\�͂ɏy�����A�ϋɓI�Ȓ��~�ւ̈ӗ~�Ȃǂ����܂�ė����肵�āA���̂悤���c������߂������Ƃ��炵�����x�E�d�g���ŏ���ꂽ�A����ׂ̉₩��(=�㐟�݂̕����͌������E�����ɍi����ꂽ�悤��)�ł͂Ȃ��A�����������I���E���L���ȎЉ����}���Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@�K�E���̖��ł͂Ȃ�(=���Ƃ����z�ł��낤��)�A���g�̖���ł���A���ꂳ���������肵�Ă���A�����͎��R�ƍ��t���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�l�ԂƂ��Ĉ�ԑ�ȁA�w���R�x������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�@
�@(�����I����ɂȂ邯���)�@�Ⴆ�c�C�O�ڏZ�ŌːЂ��ړ����A�N���[�t�̕K�v���Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ă��A��N�A�܂��A������ΈڏZ���Ԃ̂����Љ�ۏ��̋߂���@�͂���̂��낤��?�@�t�ɁA�C�O���痈�����āE���N��ɂ܂��A������A���̊Ԏx�������Љ�ۏ��͂ǂ��Ȃ�̂��낤?�@����Ȃ�̓���E���T���x�����݂���̂��낤��?�@����Ƃ��c�����܂ł��u�x�������ԁv�����Ȃ�����Ӗ��͂Ȃ��A���߂��������������͑��݂��Ȃ��̂��낤��?�@�O���[�o���Љ���}���A���̕ӂ�A�ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤�c!?
�@�������A�����炻�̑̐����A���������łɃv���X���ĂȂǂƂ������A�B���ȁE���̂Ȃ��A�����̕��S������邾���̂悤�ȁc�����A�t�Ɍ����@�ւł̖��ʂȍ�ƁE���ʂȐl����E�o���������邾���̂悤�ȁc����ȖڂɌ��������ňāE�����ł͂Ȃ��c
�@�����܂ł��A���s�̐Ő��x�E�Љ�ۏ��E��������A��U�A�[���̒n�_�ɕԂ����炢�̋C����(=�����i�K�ɂ���Ƃ����v���Ȃ����̏���ł��A��U�A�����ɖ߂�)�A���߂Ĉ���_�����Ȃ���c����ɉ������A���x�����A�{���̏���œ�����(=�{���̎Љ�ۏ�Ɛł̈�̉��v)�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂́A���ɂ͓��R�̎��̂悤�Ɏv���c
�@�Ⴆ���^�o�R���̒l�グ�c�p�������c�Ƃ������悤�ȍی��̂Ȃ����}���u�̌J��Ԃ��c�����̑唼�ɗ���s�\�̌��s���x�Ȃǂŏ��z������ł͂Ȃ��悤�ȋC�����邯���?�@
�@���Ȃ݂ɁA�ߔN�A����o�����u�։����v�ɂ��Ă��A���́A����ґ����肪����A�։��w�߂̗��R�A�������E�̔���(=���ޗ��c�����ߒ��c�ꔄ���Ёc�^�o�R�Y��)�́A������y�E���J����Ȃ��̂��낤?�@�������A���X�͎��R�̎Y��(�A��)�B�}�X�R�~�A�Ƃ������A���̑O��(=�����̑O��)�c��͂�A�s���̖�肾�B
�@�@
�@���̂��́A�u���r���[�ȑ��ňāv���V�̍єz������Ȃ��ő�̗��R�́A����ȂƂ���ɂ���̂ł� !?�@�Ȃ܂������͈�|���c�Ƃ����A���R�����̎����B
��s�̂���ׂ��p�Ƃ� ?�@
�@�i���Ȃ݂Ɂj�{���A��s�Ƃ͉����낤�H�@�ƁA���߂čl���Ă݂����Ȃ�悤�ȁc����Љ���}���A������z�肵�����ł́A���́i�n���j��s�̎��ԁB
�@�v���c�Ⴆ���N�����x�ȂǁA����Ȏ���ɂ����āA�Љ�̂Ȃ��E��̌��߂�ꂽ�g�̒��̔��z�ɂ���Đ��܂ꂽ�A�i���I�E�����D���c���I�@�ւɔ����E�U���c���~�ǂ���ł͂Ȃ��c�܂����~�����Ƃ��Ă��A�[�������ɓ������c�Ƃ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��c�����ƁA�L���Љ������S�E�Ώ��Ƃ����A�P�������E����������ꗥ�E���������̂ł������Ȃ��c
�@�N����������ӎ����A���̂悤�ȁc�N�������ɗ������E�ɁX�����c�ł͂Ȃ��A����͋�s�����Z�@�ցE���܂��܂ȎY�Ƃɗ^����e�����A���������S�Łc��s�{�����ړI�E�g���ƌ��������c���~�͂��Ƃ��A�ݏo���Ȃ���ƂƂ̊W���܂߁A�����������ŁE�D�z���Łc!
�@�����ɂ��Ă��A�N���E�N���ł͂Ȃ�(�������A�N���𗘗p�������������邯���)�A��������A���~(�������܂߂�)�E�J���ɂ�����ӗ~�̕�����(�܂�)�����悤�ȁA���܂��܂��\�����܂A���������S�ȎЉ����}���Ă͂��Ȃ��������낤�� !?�@(=�J���������~��������������c)�@
�@�����A1000�]���~�ȂǂƂ����A(���ꂩ����܂��܂������čs���ƌ�����)�z����₷��c��Ȏ؋��Ȃǂ͐��܂�Ȃ�����(���܂�Ȃ�)�ɈႢ�Ȃ��B
�@�_�Ɛl���̌����ȂǁA�y��E��Ղ̕s����ȍ��ƎY��(��ꎟ�Y�ƂȂ�)�̂��߁A�Ⴆ��TPP���������Ă��A�Ȃ��Ȃ��O�ɂ͐i�߂Ȃ��E��̌����Ȃ��E�B���ȁc����ǂ��납�A���̋�s�܂ł��c���~�ł͂Ȃ��A��ƁE�c��(������)�Ȃǂ��玩���I�ɐU�荞�܂��A���v(�����c)�E���������ɗ������悤��(=�U�������𑝂₷�����Ȃ�킢�Ƃ����悤��)�A���̓��{�o�ς̂�����B �@
�@�������N�A������ƊE���{�Ƃ͂������̂��ŁA���܂�ɂ��u�N�����v�ɐU���߂��ė����c�������A(�����ɂ��Ă݂��)�����������E�B��(=�i���t��)�Ȃ܂܂ł���c!?
�@�܂��A��Ð��x���܂߁E�������_���E���v�͂��Ƃ��A�Ⴆ�A�����E�ό��Ȃ������{��������Γ��E���v�Ȃǂ��A�����܂ł���������������ɊҌ������A���E������̂Ƃ������Ƒ̐��i=����Łj�ɏd�_��u���Ƃ��c����ׂ�����ň������̂��߂ɂ��c�����葼�ɉ������@�͂���̂��낤�� !?�@
�@
�@�B���ȁE���ʂ̑������������̒����E���́A��ł��������炷�ׂ����B�����Ă��ꂪ�A�l�����܂߂����܂��܂ȍ팸�E���v�ɂȂ���̂ł���c����(=����?�ȐŎ�)���Ȃ���Ή����������Ȃ��̂�����A�����͎����I�ɉ��P(=���ʂ̍팸)����čs���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����ƁA���c����𒆐S�Ƃ����Љ����W�J����čs���ׂ����B
�@
�@���{���(=�y��E�d�g�݁E�����)������Ă����āA�����Ƃ́E�ƊE�́c�s���������ǂ������Ă��Ă�(=�����)�A���̈��z�͉i���ɏI���Ȃ����낤 �B�@
�@�����(�Ԑڐ�)�̓����ɂ���āc�����̊�]���镨�i���j���E�����̊�]���鎞�ɁE�����̈ӎu�őI��(�w���E��������)�c�[�ł�������E���������A���̏�ő���̍�Ƃ��I����Ă��܂��c����͎����I���[�łɂȂ���E�����I�ɒ����ɂȂ���E�ӎ����鎖�Ȃ��Љ����v������c�����A(���̂悤�Ȍ`�ł�)���N�E���N�̐\��(=���N�E���N�̊����w��)��K�v�Ƃ��Ȃ�(=�o�c�E�J���ӗ~�����ނ����Ȃ�)�B
�@�u�[�Ŋz�팸�v�̂��߁A�E��(�{��)�E�]�ƈ����]���ɂ����u�\���̂��߂̂��܂��܂��x�o�E�Q��E���z���v���������čs�����ɂ͊ԈႢ�Ȃ�����A������l�H�̐��E�͖�����c�C�O����̔���(=���܂��܂Ȑ��x�ɔ����鎖�Ȃ��ƍ߂�����A���R�ɍs������E������c�j�A�܂����R���E���R�G�l���M�[������Ƃ�(=���ʂ̂Ȃ��E���łȃC���t���c)�A�����𒆐S�Ƃ������E���A���܂��܂Ȍ`�ʼn�]���E�W�J����čs���ɈႢ�Ȃ��B
�@�ꌾ�Ō����� �c�����(�Ԑڐ�)�́A���v�E�����̗���A���E���̗���ɊW�Ȃ��A���ꂼ�ꏊ���E�̎��_���甭��������A�V��j���ɊW�Ȃ��E��I�ɂ��E�����I�ɂ������ɁE���L�������o����Ƃ����̂��A�ő�̗��_�ł͂Ȃ����낤���B
�@���ڐłɂ́c���̂���(����)�ɔN�v��[�߂�����Ɠ������o�̂��̂�����E���̖��c��ł���c���܂��܂ȋƊE���E���܂��܂ȍH�����o�钆�ŁE�s�����ȕ������������肵�āc���ʂƂ��āA����͍����ł͂Ȃ��A�啔���������̂��߂̐��x�Ɏn�܂�E�I����Ă���悤�ȁc�ł̍s�����E�ڍׂ��A���̐^���c�{���̂Ƃ���͎����������ɂ́A�S��������Ȃ��B�@
�@����ɂ��Ă��A�Ⴆ���w�Љ�ۏ���v���x�́c�r�㍑�E��i���ɍS��炸�A�܂��ǂ��E�����ł͂Ȃ��A�����ƊC�O�����̎���E�͗�Ȃǂ�������Ĕ�r�������ׂ����Ǝv���̂Ɂc(�t�ɁA���{�̐��x�̗ǂ������߂Č��������Ƃ�������������̂����m��Ȃ��̂�)�c����Ɋւ��Ă͗^�}�E��}���킸�A���̂��A��؎��グ���Ȃ����A�قƂ�Ǖ����������Ȃ�!?�@��������f�B�A�Ƃ��Ă��E�����Ƃ��Ă̌����x��ێ����邽�߂��Ӑ}�I�E�ӎ��I�Ȃ��̂Ȃ̂��낤��?�@21���I�̊��o�E�����Ƃ͓���v���Ȃ����̂������B
�@���ƁE���̈Ⴂ�͂���Ƃ��Ă��A�����Ƃ���ȑO�́E���{�Ƃ��Ă̖��c�����d�E�l��`�̎����ɂ����āc���Ƃ��]���ȓ��{�l�ł���Ƃ��Ă��c�����̎�҂������A�ʂ����Ă���������p���ōs�����̂Ȃ̂�?�@���A���E���ŋN���Ă��鏔�����A�������{�ۑ��͂����ɂ���悤�ȋC�����邯��ǁc?�@
�@�Ƃ������A���̂܂܂ł́A�w���E�́@��Ƒ��x�ɂ͒������B�@
���{�E��蒼���_�@?�@
![]()
![]() �@
�@![]()
![]() �@
�@![]()
![]()
�@�����A�����I�ɁA���{�E��蒼���_���l���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�����c�܂��A�����E�������팸�Ă̓����́A(�ǂ����Ă�)�i�܂Ȃ��Ƃ�����(=���}���u�̌J��Ԃ������o���Ȃ��Ƃ�����)�c
�@�v���Ɂc�܂��A���{�E47�s���{�����ꂼ��́u�x�k�v�u�p�k�v��Ԃɂ���y�n�E�����ՂȂǂ��w�k�n�̕����x(�A�ѓ����܂߂�)�ɂ́A�g���E�g�D�E�c�̂ł͂Ȃ��c�܂����D�E�������E���ƂɊۓ����ł͂Ȃ��c���������Ƃ��Ă��̋K�͂̑召�ɍS��炸�A���ƁE�n�����������j�����킸�A���ڒS��(�w������)�c
�@�����āA�y������������Əo�����E�����Ȃ�A���ƁE�n���������ɂ́A���S����͎�������Ă��炢�A�o�b�N�Ŏx���c�t�ďH�~�A���R�ЊQ�ɂ��E�l�Ђɂ��A����ł͂Ȃ��E���ł͂Ȃ��A���o���ȂǏ������ɑҋ@���c�����܂ł��A����������Ƃ���B�@�������A�������̋N�p������ɉ�����ˊo�����l�������P�����E�z������B�@(��c���L�т̊Ǘ��E���L�тւ̎w��)�@(�����E�����E�͐�c)
�@�������A���R�������ł͂Ȃ��A���ƁE�H�Ɠ��X�̌���c�����A�w��̌���(���t���E���k�����)���X�c
�@��V��(�܁E�Љ�ۏ�)�A�����܂ł������E���������𒆐S�E��Ƃ������ł́A�����E�x���z�Ƃ���B�@
�@�����āA���ۂ̌���́c�Ⴆ�A�w�_�Ƃ��c�ސl�����x�Ƃ��āA��������g�����E�y�g���������ł͂Ȃ��A���x������������{�݂̂Ȃ炸�C�O�����܂߂��E�V��j������Ȃ��E�l�E�c�́E��ƁE�O���[�v�Ȃǂ𐧌����鎖�Ȃ����L�����A�c�_���Ƃ��Ĉ����p���ł��炤�c���̏�ł̑g�D�E�c�́E�g���������̓����E�ݒu�Ȃǂ͂��ꂼ��Ɏ��R�Ƃ���(=�@���E�s���̉���ł͂Ȃ��A���̎Y�ƂƓ����悤���A��@�E���@�Ƃ��Ď������)�B�@
�@�@���E�s��(�����哱)�Ƃ����c�Ⴆ�����������c�ǂ����E�������i���t�����ꂽ���܂��܂ȁE�����Ƃ��炵���K���E�@���Ɏ��ꂽ�c(=���t���E�⏕���E������?)�c�ɂ��S�炸�A����E�_�Ɨ��������̓��{�̔_�ƌ���̎��ԂȂ̂�����B����ێ������A��ɖ����ɂȂ����p���I�Ȃ��̂łȂ���ΈӖ����Ȃ��̂ł���A����͂������A���k��n�̌p���Җ�����܂߂����̂Ƃ��đΏ�����c(���ꂱ������Ԃ̉ۑ�B)
�@�{���̌���ɗ������A��������f������������ς��E�����ς��萶���čs���Ăق����B
�@ ���_�A�}�X�E���f�B�A���擪�ɗ����ċ�������c�Ƃ����̂͂ǂ����낤?�@
�@�e�s���{�����̓y�n�E���̓y�n�̖��^���|�����Ă���̂ł���A�_�Ɖ��v�ɉ��傷��悤�Ȑl�����́A�����Ĕ��[�ł͂Ȃ��Ǝv������B�����Ă����Ȃ�ƁA���ɂɂ����܂��܂ȎY�����_�ƂƋ��ɕ������Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@���{�̂��߂͂������A���E�̐H�Ǝ����c�܂��ʎY�����ł͂Ȃ��A���R�_�@�Ɛl�H�_�@�̈Ⴂ���琶����A�h�{�f�E���o�̖�蓙�c�_�Ƃ�������\�I���w�c�����o�x�ōs����ׂ����݂ł���A���R�������R�E��E�C�c�����E�A���E�z�����A�ꋓ�ɉ����Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@�������{�́A�H�Ɠ�ɚb(����)���w���E�̐H�Ǝ���x�𗝉����Ă��Ȃ��B���ꂱ�����A���E�L���̔_�ƍ��ɒu����E�͔̗͂����ɒu���ꂽ���{�̎g���E�V���i����e�����j�Ȃ̂ł���c�l�����x�̍������ł��鎖�̗��R�ł���c
�@�����Ă���́A�����I���E�K�R�I�ɁA�������n�����ƁE�H���ɂ��Ȃ����čs���c!
�@�w��ꎟ�Y�Ɓx�Ƃ����A��l�̍��������E�ʒu�t�����c����ȓ��{�̌������}���Ă݂�Ɓc������ꕔ�ɂ����ʗp���Ȃ��A��ʓI�E�f�ГI�}�C���h�E�R���g���[���������c�܊p�̓V�̔z�����w�ɂȂ����c�Ǝv���Ă��d���̂Ȃ��悤�ȁB�@
�@�L�������A�u��t�����v���u�|���v���A���̍��{�̖��E�ۑ�́A���E���̗��_�E�����ł͂Ȃ��A���ɁE����(=�������̂�����E�n���s��)�ɂ������̂��Ǝv���B
�@�����E�w��I�ɑ�����c�u�V�g�v(=�����I�Ö��Ō����A�_�̎q�E�l�Ԃ����A���l�B����Ō����A������)���A����ɐ��̒����єz���Ă���c�Ƃ����̂��A���̓��{�́E���E�̎���낤�B
�@�Љ�ۏ�̖��B������������E�����Ǝ��c�ł͂Ȃ��A�������蕥�����A�ɗ́A�u������̉��v�̈ꗥ�E�����̂��̂łȂ���B
�@�����͂������A�_�Ɩ��Ɍ���Ȃ��A���������̂��߂̂����镪��ɒʂ���A���{�I�g���ł���A(�������E�n����)�����Ƃ̎w���̉��A��������������������ɗ����E�擱����A�Ƃ������̂łȂ���B
�@�����ƂƏd�������悤�Ȏd�����e�ł́A�u���݂̈Ӗ��͂Ȃ��v�@�Ƃ��������B
�@�����n���s���̏ꍇ�c
�@(���N�̗\�Z�v��E�m�ۂ̂��߂�)�R���N���[�g�E�R���N���[�g�̔��z�����ł͂Ȃ��A���Ƃ����n�ł����Ă��A���R�ЊQ�ɋ������łȒn�Ոێ��E�m���̂��߂��u�A���v�u�G���E�G�E�͐�̊Ǘ��v���u���V��ւ̐��̏�����̐ݒu�v�ȂǁA�������l�����c���̂��̏��q�������@���ɂ��ē��{���܂��z�����E���p����̂��Ƃ����A���g�E�o�����X�̖��(=���N�|<����>�����m�b�E�̌��E����d��)�ɑ���A���ߍׂ��Ȕz��(=����҂ւ̖������S)���ق����B
�@���������A���D�E�������E���ƂɊۓ����E���C���ł͂Ȃ��A�����������������ڒS���E�擱����B
�@���̏�ł̓��D�E�������c�́A�u����̎���v�ɂ���Ă͓��R�A���蓾��B
�@
�@�������鎖�ɂ���āc����͕K�R�I�ɁA�������̕����I�E�ӎ��I���v�ɂȂ����čs���Ƃ����c?
�@�s�X�n�̖��N�E���N�̓��H�����ɂ��A�c�M�n�M���炯�̕����B�l���q��l�������Ȃ��c�ɂ̃h�^�ɁA�����E�����c�s���c�������c�����s�ɑ���c���\�N�̃x�e�����E�h���C�o�[�ł������A�A�����邽�тɌ˘f���E���������ށA�Ƃ����c�ɓ�!
�@�o�C�p�X�ɂ���Ė{���̒����݂������čs�����ۂ́A���{�A�Ղ�₽�Ȃ��B
�@�����哱�́u���ݎY�Ɓv�Ȃǂɂ��u���H�E��n�����v �u�����́v �Ƃ����̂́c�n��o�ς̏z�E���v�̊Ҍ��ɂ́A�Ȃ��Ȃ��Ȃ���Ȃ��c���c�@�ւƌ��c�@�ւ̌o�c�\��(=����)�̈Ⴂ�Ȃ̂��c�����@�ւ̊Ԃ��s������E�����肵�āA�s���E�����̐��������(���邨)���������o���Ă��Ȃ��B�ߔN���������R�ЊQ�c���ꂱ�����A���z�̌J��Ԃ��̑㏞�E��\��Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@�ܑ����H�E�S�،��z�E���u���ꂽ�R���̑����ɂ���A�J���̋z���͂̒ቺ�c�D�y�̌����Ȃ��ܓ��ɂ́A���t�͕K�v�Ȃ��Ȃ����B���t��H���Ƃ������������̂��Ȃ��Ȃ������a�c�R���N���[�g�ɕ���ꂽ�A���̓D�y���c�i�X���{���E�������Ȃ����čs�������낤�B�D�y�E���������ł͂Ȃ��c���ɂƂ��Ă��E���ɂƂ��Ă��c���̂Ă�ꂽ�R�тɐ�(��)�ށA���܂��܂����b���ɂƂ��Ă��B
�@
�@���Ȃ݂Ɂc��ؗ��Ȃǂ��H���E�f���B�̂Ȃ���̎��R�͔|�E�琬�E�L��ɂ��S��炸�c�ߔN�A���R�̔����E���������ꂽ�Ƃ������E�������Ƃ������c�����͂��̐��Y�E�����ߒ��Ƃ��������A�����Ƃ��̍��{�ƂȂ�A�y��(�y��)�E�����E��C�c�̕ω��ɂ����̂Ȃ̂��낤���A�ǂ����낤?
�@�s������������A���������̊Ԃ����ݏ��Ƃ��Ă��������B�u��v�Ɓu�R���N���[�g�v�ł́A���ݐS�n�E�h�{�f���S���Ⴄ�Ƃ��������A�R�E�́E�C�̌���E���R�ЊQ�c��ʂ��āA���܂��܂��������������Ă���Ă���B�����𒇕ۂƂ���A�I�V�x�ƃ��V�x�̌�z�ɂ���Đ������Ă����A���E���R�̐X�c���X���������B
�@���x����k���ł��A�����������̐S�̎��A�n���s���E�����ǂ̐l�����̌���ւ��Ώ��E����?�͂ǂꂭ�炢�̂��̂������̂��낤!?�@���Ȃ��Ƃ��A�}�X�R�~������ۂł́A���ɂ͂ƂĂ��傫���^�����c�����B�@
�@�t�Ɂc�������������i���k�Ђ̗L���ɍS��炸�A�����̌���������`���E���O�E�����I�Ή��j�̐ςݏd�˂��琶����A���S���ʂɓn��Г�ǂ�Ȃɑ傫�Ȃ��̂ł��鎖��(����������)�c!�@
�@
�@�������������ɂ��Ă��c���������̎n�܂�́A���R�̌����E����(=�l�Ԃ̓��̓��l�A���ׂĂ��Ȃ������d�g��)���������ʂ́A���R�j������̏��Y�ł���c���̌�ŁE���̂��̂��̂��ǂ�Ȃ���ςȋc�_�E���_�ł����ĒNjy���Ă݂Ă��A���͂⎞�ԁE�o��̖��ʂł���A���̉����ɂ��Ȃ���Ȃ��B�@
�@�{���悩�E�����悩�c�V�Ђ��N���Ȃ����R���E�Z����(=�����)�A�V�Ђɔ������E����ɑς�����Z����(=�����)�c
�@���ꂮ����E�����܂ł��A�����ɂ��E�����ɂ��֗^���Ȃ��c�����������E���~����ɗ������A��g���g�̊����`�c�܂������̂��߂̂��܂��܂Ȍ������E�g�D�̐ݒu�E�z�u�ł͂Ȃ��B
�@�e�s���{���̂��ꂼ���y�������������肵�Ă���A�C�O�Ƃ̂ǂ���w���x�ɂ����X�ƎQ���o���A��ÂɁE�q�ϓI�ɑΏ��o����i�o�����c�j�̂ł͂Ȃ����낤���B�����I�E�l�I�͂Ƃ��������A�������{�̔_�ƁE���R����������̂ɂ́A�����葼�ɉ������@�͂���̂��낤��?�@�łȂ�������������{�l�́A�w��������Ɏn�܂�c�l�����E���R�E�̂��܂��܂Ȍ��ǁE���z�x�ɉi���ɁA�����ł���܂ŋC�t�����͂Ȃ��悤�ȋC�����邯��ǁc�ǂ����낤�c!?�@
�@
�@�����A�����̂��������ł͂Ȃ��A���ɂɂ����E�̂����ɂ� (=����E�f���Ȃǂ�ʂ���) ���������E�E�����c���ׂĂ͍���������哱�E�א��҂̂��̌��Ɋ|�����čs�������낤�B
�@�_�ƍ��E���ƍ��E�ό����ɂ���Ȃ���c�u���E�L��?�̐H�ƗA�����v(�H�Ƃɗ��܂�Ȃ�!)�Ƃ����A�������������ň��̎�����E�o���鎖�������A�挈���Ȃ̂ł́c!?�@
�@�Ⴆ�Γ��{�ɂ́A�߁E�H�E�Z�c�ɂ����Đ̂���A�umade in china�v�̐��i���ƂĂ������B�ɂ��S�炸�A�s��(���Ɗ�)�ɂ����Ă͉����ƏՓ˂��鎖�������͉̂��̂��낤?�@����E���ԂƐ��������܂����ݍ����Ă��Ȃ����ɂ́A�ԈႢ�Ȃ����낤�B
������������ ���R�̈З͂ւ̊S�x
�@�v�����A���{�̍��q�n�т̒��S�E�����{�ɂ�������k���Ƃ����̂́c
�@�������������܂ŕ���ŗ����A���̒n��(���{)�Łc���炪���o�������̂ɑ���A���Ǝ����Ƃ��������ł����E���ł���c���̎��炪���o�������̂�ʂ��ẮA�����܂ł��厩�R����̌��ʕł���c�����������R�̖@���Ƃ����@���̑n���(=�_)�̎v�����������E�������������ɑ���A��肠�������x���ł���c(=�����c�m�A�̍^���R������̋��P�E��)�@(=�`�F���m�u�C�����̓��l�c�Ƃ��̐̂���a������Ă����x��)
�@�ϗ��E�N�w�E�@�����Ƃ��c���Ԃ̏펯���Ƃ��A�̑O�Ɂc�������͂�����x���_�ɖ߂��A�^����ꂽ���{�̌��E���R�̃G�l���M�[������ȏ�A��̎�������ɂȂ�Ȃ��悤�A�����������S�����ł���������������E��肭�g�ݍ��킹�E��g���Ȃ����c�ނ���A�����(��k����)���̎��ɋC�t�����邽�߂ɗ^����ꂽ�A�b�݁E�`�����X�Ƃ��āA�t�Ɋ������čs���A��蒼���Ȃ���! �Ƃ����A�_�l��������b�Z�[�W�ł���A���{�̍K�����{���̖����̂��߂ɁA�����w�\�K�x�w�\���P���x�Ƃ��ė^����ꂽ�A�ďo���̂��߂������Ƃ����c���́A�����{�ɂ�������k���ł͂Ȃ��������낤��!?�@�����ƁA�����ł���ɈႢ�Ȃ�!
�u�V�v�� �u�V�v�̑Η��͂�������!!
�@���������ł���c�ƕ������L��������B�������A�S�ĂƂ͌���Ȃ�����ǁA�K�����������Ƃ͌���Ȃ��Ƃ������Ȃ̂��낤�B�@�ނ���A���̍Г��ߖځE�_�@�Ƃ����w���K�x���E�w���ȁx���A�i���������s���̌���������������悤�Ɂj���ʂ͂������A�����c�Ɛ�c��ʏ����ɂ͖��O�����m��Ȃ��悤�Ȑ���c�͋ɗ͏��i�͂ԁj���A�\�Ȍ���u���v�Ƃ̊ւ�荇���ɂ����Ċi���E�s�����������A�E�C���錈�ӁE���f�ł����ėՂނׂ��ł���c�����͂������A�r��������E�����鎖�����ɂ̖ړI�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A
�@�u���E����̉��Љ��ڎw���I�v
�@�Ƃ������ł����c
�@
�@�������A���̂��߂���p�͕K�v���B
�@����(������t����)�w�X���I���x�ł������ꂽ�悤�ɁA���ꂱ�����A�S������{�����唼�̖{���Ȃ̂�����A������o�b�N�Ɂi���S�̎x���Ɂj�A�א��҂ɂ́A���������M�ƁE�E�C����s���ł����Đ擱���čs���Ăق����A�Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�@�܂��A���̎���ɂ��J��Ԃ��ė����A�u�V�v�Ɓu���v�̑Η��B����͓��R�A�N����ׂ����Ƃ��ė����o���邯��ǁc
�@�u�V�v���u�V�v�̑Η��Ƃ����̂�����A���ɂ͔���Ȃ��B�萁��������́c��������ɂ���Ȃ���c�������Η��Ƃ́I
�@�Ⴆ�A�u���s�\�z�v�ɂ��Ă��c�u�n�����͂̑��D��v�c�Əq�ׂ����f�B�A���������B����͐������\�����낤��?�@��x�A��������Ƃ������̏�ł��̗��R��A�����Ă݂���!?
�@�{�����������c��Ȃ������ɂ����āc��Η��v�ł͂Ȃ��A�����ƈႤ���@������̂ł́H�@���܂�ɂ��Z���I�Ƃ������c����̖{������������Ɣc��������ł̑Η��Ȃ̂��낤��?�@���Ȃ��������{���ɖڎw���Ă�����͉̂��Ȃ̂�!?�@�Ǝv���Ɓc�^���Ƃ������c�Ȃ��߂����Ȃ�B�T�d�ɁE���J�Ɂc�͗����o���邯��ǁc�܂��g�����m�̓��c�E���_�E��(��)�ߎ��Ȃǂ́A�O�i�̂��߂ɂ͂ނ���K�v�ȁA���R�̐���s���Ƃ��ė����o���邯��ǁc���ʓ_�͑S���Ȃ��̂��낤��!?�@
�@(�X�����v���n�߂Ƃ���)����܂łɂ����x���`�����X�Ɍb�܂�Ȃ���A�ǂ������r���[�Ȃ܂܁E������܂܁c�Ƃ������R�̈���A�����ɂ���悤�ȁB�@�@
�@�u���������v�v���L���b�`�t���[�Y�ɗ����オ�������}�B�����������̖ڂɂ́c��ǓI�ɑ�����A�u���������v�v���u(���)�s�\�z�v�Ƃ����͖̂��炩�ɂȂ����Ă���̂ł���A�ڎw�������͓����ɂƂ��������Ȃ��̂�!?�@(=�O�҂͒��ۓI�E�n�[�h�A��҂͋�̓I�E�\�t�g�c�̈Ⴂ?)�@
�@�u�V�v�̗���ɂ���Ȃ���A�u�����v��ۂƂ����̂́c�u���v�̈ӎu�v�͂ǂꂭ�炢�̂��̂��낤!?
�@�u�V�v�Ƃ����̂͂��ׂĂ̋ƊE�ɂ����Ăł���A�����Ƃ����łȂ��A���f�B�A�ɓo�ꂷ��]�_�ƁE����ҁc���Ƃ����j��(=�����j�E�o�ώj)�ł��낤��(=���j�͉��̂��߂Ɋw�Ԃ̂��Ƃ����A���̖ړI���炵�Ă�)�c�Ƃ������S�Ă̋ƊE�ɋ��߂���ۑ�ł���c�����A�����������V�������z�����߂鎞�㌗�ɂ���l���������A�ʂ����Ĉ���Ă��邾�낤��?�@���Ȃ����g�̖�肾�A�ƌ��������B
�@���ɂ��c(������)�u�A��v���Ƃ��c�u�Ïʂɏ��グ��v�c���Ƃ��B�w���v�h�x�Ƃ����ǁA�ǂ�������A�|�C���g���͂߂Ȃ��A���ǂ������g�D�̑������ŁA�w��ԐV�������v�h�x�Ɍ������Ă������t���낤��?�@�����I�ɂ݂Ă��A�u���s�\�z�v�Ƃ����̂́A(���̖��̂͂Ƃ�������)��ゾ���̖��ł͂Ȃ��͂��Ȃ̂� !?�@
�@�ߔN�́u�s�\�z���v�͂ǂ��ւ��A(�ڐ��)�V�������E�ۑ肪�����オ��ƁA�����������s���Ɏ��^�������W������Ƃ����A�}�X�R�~�̎p���E�������ɂ������^��̂悤�Ȃ��̂������Ԃ̂́A���������낤��?�@����Ƃ��c�s�������g�̗͗ʂ�����������̂��c?�@(��)�@�@
�@����Ƃ��c�s�������g���A�V�Ɏ�����Ă������̂��낤��? (���̓�ւ�@���ɂ��ď��z����̂��A�Ƃ����c����)
�@�������A�����������ɂ��Ă��c�w�ېV�x�Ƃ������ځE���̗���c���{�̗��j�������悤�ɁA���̐ߖځE�ߖڂɓo�ꂵ���悤�Ɂc���������Ă����s�����ꂸ�˂��i��ł��炢�����A�Ƃ����v���������̂��m��������ǁB
�@�����A�s�\�z���Ɍ��炸�A�Ⴆ�c�V���ɑ���A���ł����E���́u���Ή^���v�B (���c����^���Ȃ�������)�@
�@�܂�A���{����ᔻ���Ȃ����A���Ƃ������V�����ł����Ă��Ă��A����ɑ��Ă������������E���c��ԕs�v�c�Ȃ̂́A���Δh�ɑ����ΈāE��������߂Ȃ��܂܂ɁA�ꏏ�ɂȂ��Ă����������f�B�A�̂�����B��������f�B�A�̑唼�Ɍ����鎖�ł���(�S�ĂƂ͌���Ȃ������)�A���{�Ɠ��̂��̂Ȃ̂ł� ?�@����ł͓��{�̔��W�͉i���ɖ]�߂Ȃ��A�������čs�������Ȃ����낤�B
�@
�@�Ƃ�����A���̂悤�ɁA�}�X�R�~�̕\�����@�E����������ɂ���肪����Ƃ��Ă��c����ȏ�ɁA�}�X�R�~�ɍ��E����Ȃ��A�����I�E��I���ʂł́c�܂����{�̎�v�����E�ڐ�̓s�s���������d�������A���̓���炵�̐����Ɉ��ݍ��܂�Ȃ��c�e�n���E�����̂ȂǎЉ�S�̂����ʂ��u�q�ϐ��v���u��Ƃ�v�̂悤�Ȃ��̂��A�w��y�̐����ƁE���v�h�x�ɂ͗~�����C�����邯��� !?
�@�����́A�����̂ڂ�ی����Ȃ�����ǁc
�@��͂�A�u�`������v�E�u�Љ����ڑO�ɂ����A��w�݂̍���v���Ɍq�����Ă������ł͂Ȃ����낤���B�@
�@�u�m���̔c���v���u���H�v�͈Ⴄ�̂ł���c�u���m�̐��E�v�ɑ��āA���݂������������d�������ׂ��Ȃ̂ł́H �Ǝv���Ă��܂��B�@
�@�����������ɂ��Ă��c
�@���̐��Ƃ����͈̂ꌾ�ł����c�Ⴆ�ǂ�ȗY��ȉ��y�i���I�j���c�g�߂ȉ��y(���I�j���c�y�ȍ��̖@���͓����ł���A���̖@��������Ίy�Ȃ͊������Ȃ����A�l�X�ɂ�������Ȃ��B����ƑS�����������Łc
�@���̊y�Ȃ��L�߁E����グ��ɂ́A��鑤�E�������̋��͂Ȃ����Ă͐��藧���Ȃ��c(=���͂ɍ��E����Ȃ��E�����ɉ������Ȃ��A�����̐��_�E���f���B)
�@���̂Ȃ�c�����i=�����E�`���l���E�����E�ۗ��E�摗��E�Ӗ��c�g�D�̈ێ��j�̐ςݏd�˂̌��ʂɂ���Đ��܂��A��R�̎�����S���̂́c�u�L�j�ȗ��̎c���ȕ��A�̗��j=��蒼���̗��j�v�������悤�Ɂc���ǂ́A������w��������ɂ���A���̎q�������Ȃ̂�����!�@�����v���Ă��������E�����Â����c�w�ɂȂ��ĕԂ��ė���Ƃ���!�@���ɂ���Ȓ���́c�����ɂ͑S���g�Ɋo���̂Ȃ��E1000�]���~�Ƃ����������������A�c��ȍ��̎؋�(=�C�O�ɂ͊֗^���Ȃ�?�@�����ɂ��E���������؋��c�����s�c���B)��ʂ��Ă��\���Ă���̂ł����c�����Ă���́A����ȑ̐�����������A����ɁE����ɑ�������Ƃ��� !�@(���̓��{�����炱���A�Ȃ�Ƃ������������Ă���̂����m��Ȃ��E�z�����t���Ȃ��A���c��Ȑ��� !)
���@�Ƃ� ?
�@�v���c�w���@�x�Ƃ͉����낤�H�@���炭�A�����������̑唼�ɗ���s�\�E�������w���{�����@�x�B
�@�����A���@�����Ƃ����Ή��́A�W�����W��������荹�������̂��낤�H
�@���Ƃ�����ł����Ă��c���̍��{�E��{�́c�A�����R�̊ē̉�(=�A�����J�̎哱)�ɍ쐬����E�~���ꂽ�Ƃ����A�u���{�����@�v�B�@�������Ƃ��A�쌛���Ƃ��c���̓��e�E�K�v���Ƃ��������A����ȑO�́c�`�ԂƂ������E�̐����̂��̂Ƃ������c�܂��A�u���{�����j�I���������E�������̂܂܁c�v�Ƃ������A���̌��@���̂��̂̂�����c��͂�A�����y���i�������ʒu�E����j�������蒼�������A�ꕔ�́E���Ƃ̂ł͂Ȃ��A�V��j���S�Ă̓��{�������[��������A�B��̕��@�Ȃ̂ł́H�@������ǂ��ɒu���̂��Ƃ����A��{�E�o���_�̖�����Ǝv���B�@�m���̖��ł͂Ȃ��B
�@(��i���ɂ���Ȃ���)���@�_�c������x�ɁA�A�����J�c�A�����R�c�}�b�J�[�T�[�����A�Ƃ������t���A70�N�߂��o���������o�ꂷ��Ƃ��������̂���������(���E2015�N����)�B�����A�������݂���w����ČR��n�x�c���_�E�����ȑO�̖�肾�B
�@�Ⴆ�A���̎���ɖ����E�吳�̕����ŊX������Ă�����ǂ����낤?�@���w��N���ɂȂ������q�����w���̓��A�e�ɐ����𒅂��Ă�������悤�ȁB
�@�܂��쌛�h�Ɍ��킹��Ɓc�݂������āE���������āc��{�͓�������Ȃ����A�C�ɂ��鎖�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ɂȂ�?�@
�@�����������h�A������҂����ɂ́c���̊O�ς�����(=���łɋc�_�̓�����)���۔������N����(=���ɓ��낤�Ƃ���)�A����݂����Ƃ����Ȃ��A�Ƃ����̂��{���Ȃ̂ł́c?�@(�v�V�n�̊w�Z���炩��w�l���������邯��ǁc)
�ꍑ�єz�E������`����̏I��
�@�����c�����A�A�����J(�A�����R)���A���{�����@���z�Ɠ����ɁA����̐푈�������������H���Ă���Ă�����A����ȍ��ׂƂ����������炯�̕s�����Ȑ��̒��ɂ͂Ȃ�Ȃ��������A�������u���{�����@�v����{�E����v�Ɋ�M���x�E�S�x�ɂ́A�����ƍ��x�ŁE���łȂ��̂��������ɈႢ�Ȃ��B���R�A���́u�����n�v�͑��݂��Ȃ����c�u���Ēn�ʋ���v���u���Ĉ��ۏ��v���c�����A����Ȑ�̌����Ȃ����@�_�����������݂��Ȃ������B
�@����̕K�R�Ƃ��āA�w�}�X�R�~�푈�x�͓o�ꂷ�邯��ǁc���̌�̃x�g�i���푈�c�p�ݐ푈�c�C���N�푈���c�ă\�̗����c���̖��ȁA�A�t�K�������c���݂��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@���Ƃ��A�����̐��E�̎���(���x��)�ł́A�����(=�A�����J�̐푈������)�����Ș_���������Ƃ��Ă�(�\�A�R�̑��݂Ȃ�)�c�������A�A�����E�A�����J�Ƃ����卑�����悵�ē������������Ă�����(�ڎw���Ă�����)�c���Ȃ��Ƃ����E�̎���́A�����͑S����������̂ɂȂ��Ă������ɂ͊ԈႢ�Ȃ����A�ŏ��̔�Q�ɗ��܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��i�����A�\�A�̐��E�i�U�Ȃǂ́A�����Ɏ���܂ň�����݂��Ȃ��j�B
�@�����A�I�킩��}(����)��70�N! (���E2015�N����)�@���́A����ȓ���O�̎����A���̂Q�P���I�̍����Ɏ���܂ŕ������炩���E������ɂ���ė����̂��낤??�@���{�����̐ӔC���낤��?�@
���e(���@�_��)�ɓ���ȑO�̖��Ȃ̂ł́c!?�@
�@�w�r�̐��E���̂悤���u����_���v���A���߂��瑶�݂��Ȃ������B�@
�@���Ȃ݂ɁA�C���N�i�U�ɓ��{�����S(�֗^)�����̂́A�����̐i�U���̂��̖̂ړI�E�A�����J�s���̎^���c�����A���̍��{�����{�����@�ɂ�����{�̗��������̂悤�Ɉʒu�t�����Ă������߂ł���A�����ƃC���N�푈�͒��ڂɂ͌��ѕt���Ȃ��c���̑����������������Ƃ������ł���A���̏ꍇ�̌��ʘ_�₻��ȏ�̑F���ɂ͋q�ϐ�������Ȃ��Ǝv���B�����̑S�e�𑨂��Ȃ��A���������f�B�A�̑Ή����o���炵�Ă��A���{�S�̂Ƃ��Ă����������������̗��_���͗ʂ��Ȃ������B�C���N�푈��Njy����Ή���������ł͂Ȃ��A�����Ƃ���ȑO�̍��[�����̂�����Ǝv���B
�@����͈ꌩ�A���{���Ƃ��Ă̎��R�̑��d���(����)���Ă���悤�ɕ������邯��ǁc
�@����A�O�ɏo���(=�O����ł�)�A���{���{�̑O�͑f�ʂ�́c�\�c�ЂƂ��炰�̃A�����J�哱(��n���Ȃ�)�c�w�A�����J�����̓��{���{�x�Ƃ��Ĉ���ꂽ�����R�̒��ł̎��R�ł���c�����E70�N�߂�(���E2015�N����)���A�����J�ǐ��̓��{���Ƃ����A���{�̐����哱(����)����̉������c
�@�܂��A�����ɂ����Ắc��̐��̂Ȃ��E�C�O�E����ɂ͒ʗp���Ȃ��c����̋�_�E�����Ƃ��炵�������x�z(=��R�̑叫)�ɂ��A���̂悤�Ȓ��r���[�Ȗ����`���Ƃ�グ�Ă��܂����B�������_����������ƈ�Ăė��Ȃ������B��{���A�����J�哱�ł́E�����哱�ł�(=�A�����J�哱�Ɗ����哱�̔���)�c��Ă悤���Ȃ������B�@(�����̑��݂ɂ��S��炸�A������n�����݂��E���@�_���┽��f�����s�������̂��A�ǂ��؋� !)
�@����ɂ́c���̃A�����J�������c(�Ԉ��w���Ɋ֘A�����A�����s���̎w�E�ɂ�����悤�Ɂc)
�@�ŋ߂�����̕ČR���ɂ�邳�܂��܂Ȏ����E���́c�ߋ����琔���Ă������Ȍ����ƌ����Ă���c(�}�X�R�~���S�����グ��킯�ł͂Ȃ��̂�����)
�@�Đ��{�Ƃ��������c�S�E����(��n)�ɍ݂炸�c�ƌ��������A����̔ނ玩�g�̐S����Ԃ��A���͂���E�ɒB���Ă���̂ł�?�@�Ǝv�킹��悤�ȁB����Ȍ���Ɂc�ٍ��̒n�Łc�命���̌������炻�̑��݂�ے肳��钆�ŁA�u�����v���̂��̂��̗ƂƂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����A����̑��݊��E���l���ɑ��関���ւ����]�E�r�����̂悤�Ȃ��́c�ނ�ɂ����āE�ނ�Ȃ�́c�܂��ނ�ɂ�������Ȃ��A���̒��ɑ����a�O���̂悤�ȁE�i�����̂悤�Ȃ��̂��Q�����Ă���l����������ɈႢ�Ȃ��B
�@���̎��ɂ��Ă��c���V�Ԃ��Ƃ��E�Ӗ�Â��Ƃ��c���@�_�����l�A��n(��s��)�ړ]�����ȑO�̖�肾�B�@�@
�@���{�E�}�X�R�~�́c�܂����_�ɂ��Ă��A���́A�����������̐S�ȂƂ���ɖڂ������悤�Ƃ͂��Ȃ��̂��낤 !?�@����y���E�Љ�̌��@?�@�B��(�����)�@?�@����Ƃ��A�w�E�C�̖��x�Ȃ̂��낤���B�@
�����E������苰���c�C���[�W�̗�
�@����Ƃ��c
�@���Ďv�z�_�҂������Ƃ����c�ɂ��S�炸�A�쌛�_(����)�����ԁA�쌛�h�̖����c!?
�@�u�푈�����v�̈ꌾ�ɖ������c�A�����J�ɂ�����������ɂ��S��炸�c���{��������ΏۂƂ����A���̋��`����ʓI�쌛�_�ɂ��S��炸�c����ւ̎����B���{�R�������ƂƂ���A���s�I�����U���c!�@
�@����ɂ��A���́w����x���A�����J�𐨂��Â���(=�������������E�����Ɏ��t��)�c���ʁA�����Â����w�ƂȂ�A�ČR�P�ނ�x�点���c!?�@
�@�A�����J�Ƃ̋���E���Ȃǂ�ے肵�Ȃ�����A��{���쌛�_�Ƃ��������c�t���A���E���a��x�点���c!?
�@�m���ɁA���{�����@�ɂ���ē��{�͐��A�����̈�x���Q�킵�Ă��Ȃ������B�@(�V�c�����A�K���ŋ��������ė���ꂽ�B)
�@�ɂ��S�炸�A�ˑR�Ƃ��āw�푈�x�Ƃ������t�ɋ�������E���������c��s����Ƃ������c�����ȗ����ۂ������Ă����c�����Ă���́A���X�Ƃ��č��ł������Ă���B�@���̈��̖����Ƃ��v���錻�ۂ́A���̋N����̂��c??�@�����ɂ��A(���E��ΏۂƂ��Ȃ��E�ʗp���Ȃ�)����̖��n���E�Â����M����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@(�����Ɍ����āc)�@�����I�ɁA�����A�A�����J�ɍ��ƓI�Г�~��|�����ė����Ƃ���(���R�A�o�ϖ����܂߂�)�c����Ȏ��A�ʂ����ē��{�́A�������E�A�����J�̂��߂ɂǂꂾ���̗͗ʂ��o���邾�낤
!?�@�u����v�́c�A�����J�A�Ƃ�����萢�E�̂��߂ɁA�ǂ�ȓ���������̂��낤�A����������^���Ă���邾�낤 !?
�@�Ƃ�����A�����ɂ��Č����c
�@���܂ł��Q�W�S���ɕ��ꍞ�݁c�ނ�ƈꏏ�ɂȂ��āA�A�����J�ɂ͉��̉e�����y�ڂ��Ȃ��A�Z���I�Ȕ�Q�҈ӎ��ł����Ď咣���E���Ԃ����ł͂Ȃ��A�����A�A�����J���̂̂��߂ɂ��A�����E��������ɗ����āE�������������Łc�������A���������̔[���E���Ȗ����ɏI���Ȃ�(���ꂱ�����厖!)�A���E���ɗ������A
�@�u �w�R���E�j�������Ȃ����E�x �̒��Ɓ@�v
�@�̐擪�ɗ����āc�Ⴆ���w���q���x�Ƃ����A�l�X�E���Ƃɂ���Ắc�Ƃ��������A�������炳��������������悤��(���r���[��)�C���[�W�ł͂Ȃ��c�܊p�̔ނ���v���ʂɂ��Ȃ��c�O���[�o���Y���ɗ������A���E�ɒʗp����E�G�Ί����������Ȃ�(���ꂱ�����厖!)�E�t�ɔނ�(����)�����Ăэ��ނ悤�ȁc�����̈��S�����ł͂Ȃ��A���E�I�K���ł�(�퓬�ړI�ł͂Ȃ��E���Ƃ��������ł��낤�Ɛ퓬�v���ɂ͉����Ȃ�)�l�ЁE�V�Ђւ̏��v�ɂ����E�Ή��o�����E��e�͂��������c�܂��A�J�������܂c
�@�u�Q�P���I�ɂӂ��킵���@�L�`�̖��́v
�@�Ɏ��ւ����c(��ƂɗႦ��Ɓc���A���u�{�Ёv�Ƃ��āE�e���͂��ꂼ��u�x�Ёv�u�x�X�v�Ƃ��Ēu���c�݂����Ȗ���?)
�@�A�����J���玩�������E�ނ���擱�I�ȁc����ȁA���E�ꗥ�̉���I�Ȗ���(���̂����łȂ��E���`�E�P���̓��e�����܂߂�)�ɐ�ւ���Ƃ����c�����ŏ��߂āA���{���Ƃ��āw�����x������ė����쌛�_�Ƃ��Ă̈Ӌ`������̂ł���c�����Ă���́A�u���E�̂��߁v�����܂A�����_�ւƂȂ��ōs���c!�@
�@�Ƃ��������A�쌛�E�����ł͂Ȃ��c
�@�ꍑ�єz�E������`����I���̎����}�������A����ɂӂ��킵���A���������̑z���͈̔�(�̈��)�̌쌛�A�����ł͂Ȃ��A���E�I���n�ɗ������c���E�̂��߂�����E���{�����@�Ƃ��āA���E�����`�F�b�N���Ȃ���E���̗��������悤�ȁA�u�Ώۂɑ���\�ʓI�E�\���I���v�Ƃł������Ηǂ����낤���B(=���������E���E�̂��߂́A�V�݁E���{�����@)
�@�Ⴆ�A�w�C�\�b�v����x���c���e�̎�|�͐̂������ς��Ȃ�����ǁA���̂�}�G(������)�Ȃǂ͂��̎���E����̖|��Ƃ����ɂ���āA����̃X�P�[���ɉ������E���E��Ώ��Ƃ����A���ۊ��o�ł����ĕω����čs���c�Ɠ������� ?
�@���q�E�h�q�c�R���c������ ���Ƃ��E�R�͂��Ƃ��c�U�����͂������A���Ƃ��h�q���ł����Ă�(=�h�q���Ă݂Ă�)�A�ǂ���̗���ɗ����čl���Ă݂Ă��c�����̌��t�����݂������c�卑(��i��)�����悵���A�����̌��t���̂�\���䂩������Ȃ�����c�w�푈�x�Ƃ����C���[�W���A���̒n��(=���E)�������@(�ӂ����傭)���鎖�͕s�\���B
�@���ĊԂɁA���Ƃ������A�o�ϓI�E�����I?��肪���̗��ɉB����Ă���Ƃ��Ă�?�c�푈��������v�킹��悤���w��n�x�c�Ȃǂ́A�_�O���B
�@�u�����v�E�u�����v�́A���̏�̏o�����Ƃ��čŏ����x���̏�ɗ��߂鎖���o���邯��ǁc�w�C���[�W�x�́A���E�ꏊ�E�l�c��I�Ȃ��A���\�킸�A�����ɍL�����čs���c !
�@�e���ǂ�Ȍ��t������ł����Đ������Ă��A�ƒ���C���[�W���ς��Ȃ�����A�q�ǂ��͌����ĐM���Ȃ��B
�@�Ⴆ�c�w�V�c�É��x���A�����̐܂ɍ����Ɍ���������t���v�������ׂĂ݂Ă��c�����������́A�É��̂��������t�ɁA�u�ォ��ڐ��̈Ј����v�Ȃǂ͑S�������Ȃ����A����ǂ��납�A�����̕������É������߂Ċ��W�܂��Ă���c!�@������A�Ȃ�ƕ\��������悢���c�ӎ����鎖�Ȃ��A���E���E������(=�ォ��ڐ�)�����O����čs�������B�@
�@���E�̒��ł��ł��d�v�Ƃ����A��e���ƁE���{���V�������@�ɂ́c�킪�q�̕�������Ɍ�����Ă���A�e�̐S�����v�킹��悤�ȁc�������E�܂����E�s�������������c(���E�s���c�펯�c�����c�@��<�M�Ƃ͂�����ƈႤ>�c�́A�l�ɂ���Ă��E���ɂ���Ă��Ⴄ����A��ɂ܂Ƃ߁E���ߕt����͓̂��)�c����ȉ������A���{�����@�ɂ����~�����C�����邯��ǁA�Ƃ肠�����ǂ����@�͂Ȃ����̂��낤�� !?�@
�@�V�̊肢�ł���E�l�ދ��ɂ̖��́c���{���������w�����������A�����ł����E�P�ʂɍL���čs���A�Ƃ������ł͂Ȃ����낤���B
�@���a�V�c���u�������~���錾�v�Ƃ��������v�����A�ĂсA���E�ɏ�����?�@
�@
�@����푈���}�X�R�~�푈�̈Ⴂ�́A�����ɂ�������悤�ȋC�����邯��ǁc !?�@
�����Ȃ������@����Ȃ�
�@�܂��A�����͂Ƃ��������A���̂悤�ȁc�j�ۗL�����u�ォ��ڐ��v�ŁA�����E�r�㍑�Ɍ������Ċj��������������Ƃ����A����ȕs����(��������)�E�B���Ȋj�́A��U�x�~�E�p�~����قǂ̌��ӂŗՂނׂ��� !�@
�@�����������(=�q�ǂ��̎���)�A���Ƃ��_�l�ł���o���o���Ȃ��B�@
�@���E�̂�����M�E�@���̑��ݖړI���A���ɁE�����ɂ���̂��Ǝv���B(=���Ƃ̎���)
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����B
�@�w�ߋ��̂悤�ɁA��̍����擪�ɗ����Đl�ނ����������Ă���������͂��łɏI���܂����B������`�̎�����I���܂����B�x
�@�w��������A������l���T���ɕ�炷���@�ł͂Ȃ��A�������̎���̂�����Љ�I�ȏ������������邱�Ƃ̂ł���m�b�������Ȃ���Ȃ�܂���B�x�@
�@�w�l�̎g���������ŏI����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�_�̑S�̖ړI�ƈ�v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x
�@
�@�c�ƁB
�@
�@21���I���}���A���͎�`�ł͂Ȃ��A�^�̖����`�E���E���a��������A�I�o�}�哝�����o���́A���̎����ؖ������傫�Ȉ��ł͂Ȃ����낤���B (=���A�ۗ����j�E���j�I�������ɂ����āA�����ׂ����āE���ꂽ�l�B)
�@�w�̔ɉh�x���w���̔ɉh�x���A���̍��{�ړI�͓����B�ɂ��S�炸�c
�@�u���̂��̔ɉh�́A����(����)�̂��߂ɗ^����ꂽ���́B�v
�@�Ǝ~�߂�Ƃ��납���������܂�A���łɂ��̎��_����s�K�͎n�܂��Ă���Ƃ�������m��Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ������Ȃ̂��낤�B(���j�I�������ւ̑Ή��̎��s�E���m�c)
�w�������~���錾�E�y���x�̑㏞�ɋꂵ�ށA���{�l
![]()
�@�s�퍑�E���{�ɂ́A���a�V�c�ɂ�邠�́A���{�~���錾�����݂���B
�@�Ñ�E�ߑ�j��A���E�ɗނ����Ȃ��A�����c�䎩���S���Ƃ��Ĕ�����ꂽ�A�������~���錾�B (�����E�C�T�N���Ղ���̋��P)
�@�����A����������]�����E���������̂́A�ނ���A�A�����J�������c! (=�}�b�J�[�T�[�����ɂ��)
�@�����Ă���Ɂc�s�퍑�E���{�����̂��߁A�}��10�N�̍Ό��������A���a�V�c�̐擱�̂��ƂɎn�܂����A�������܂����߂̓��{�E�����K�c(���ꂳ�����A�������E�ɗނ����Ȃ�!)
�@�����V�c�̍v���E���J���c���ɁE�V�Ɏ~�߂�ꂽ���̂悤�ȁc���̌�����{�o�ς̔��W���o�ϑ卑�E���{�̒a�������E�O���c!�@�@
�@
�@�V�c�̓��{�����Ɋ��������A�c���ɂ͂т��鍪�[�����K�c�K���E�@���c����!?�@�@
�@(�X�|�[�c�I�����A�����Ă��E�����Ă������l�i�E�i�i�ɕς��͂Ȃ��A���d�����c�Ɠ����悤�ɁB)�@
�@���̗����U��Ԃ��c���{���݂̂Ȃ炸���E�̖͔��Ƃ��Ă��A�������͂��������d���E�F�����ׂ��������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���͖̂łтĂ��A���a�V�c����(���܂���)���E���P�́c�����ď����鎖�Ȃ��c�����Ă���́A���̌�(=����)���c���O���Ɉ����p����E��������E�Ɏ����Ȃ����c��������ƁA���������{�����̐S�ɐ����Ă���B
�@�u�ߋ��̓��{�v���|(����)�Ɂc�����������{�U���B�@�ڐ�̋�����E������̂悤�Ȏ�������J��Ԃ��E�d�v������A�W�A�̎��Ԃ��݂߂Ȃ���A���X�̂悤�Ɏ��͂��̎����v���Ԃ��Ă݂��B
�@���́A���������A�w�]�R�Ԉ��w���x�ɂ��Ă��B�@
�@�����ۑ�̒��̈�̗���Ƃ��ďo�Ă����A���̘b��ł���ɂ��S��炸�A�܂�ł��ꂾ�������ׂĂ̒��S�ۑ�ł����邩�̂悤�ɁA�����Ƃ��炵�������グ�c�i�}�X�R�~��擪���j�k�}��g��ŁE�������(����)��c�t�ɐ��̒����h�������c�N�ɂԂ���Ƃ����̂ł��Ȃ��c����ɂ́A�l�U��(=�����s���U��)�ɑ���Ƃ��� !�@��Â�����������������ϓI�E����I�������_ !!�@(�����ā@�X�����Ȃ�)
�@(�{���ƌ��O�̋�ʂȂ���点�Ē����Ȃ��)�c���{�l�ɂ͐푈����鎑�i�͂Ȃ��̂��c!?�@���̒��ɏ]�R�Ԉ��w���قǔߎS�ȏo�����͂Ȃ��A����͂��́A�L���E����̌��q���e������������̂��̂������̂��c!?
�@�����ɂ���ẮA�S���ʂ����j�I�����E�،������݂��邩���m��Ȃ��A���̖����c���������A��������(����)�ʼn������߁A�ǂ��������悤�Ƃ��Ă�����̂��낤�c??
�@�i�Q�l�c�u����c���Y�c���������]�R�Ԉ��w�̐��́v�@���_�E�ꌎ�����A�ق��j
�@���ׂĂ��c�����E�ǂ�������ӂ���c(�C�O���猩��j�g�b�v�i���[�_�[�j�̑��݂��Ȃ��C���[�W��^����A���̐��̓��{�c���n�ȁE�B���Ȗ����`�B
�@���������A�w�]�R�Ԉ��w���x���E�w�����n���x���E�w�f�v���x���c�܂��A�c���̍P��s���ɂ͑g�ݍ��܂�Ȃ��w�����Q�q���x���c���̃��[�c�E�N��������c�܂����O�_�ł����c����́A���̓��{���ɂ���̂ł���c�u�g����o���K(����)�v�Ƃ������ɂȂ�A�܂��Đg�����m(����)�ŝ�(��)�߂Ă��Ă��A�����牽�̉����ɂ��E�i�W�ɂ��Ȃ���Ȃ��B
�@�����͂��ׂāA���͂Ƃ������́A�������~���錾�E���{�����K�Ƃ������݂��d���E�������y�������c�����m�푈�̔ߎS���������ւ̋��P�Ƃ��đ�����̂ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�l��_�ɗ����ꂽ�c�ƌ����Ă��d���̂Ȃ��悤�ȁc�t�ɁA�C�O���_�����S����悤���c�ڐ�̌l�I����_�ɑ���A��ʓI�E��ϓI���{���_�̊Â��E�Q�W�S������̏��Y�c�܂����́A�w���{�̐�㋳��̂�����x�ɂ��A������x�A���ߒ����ׂ����̂�����̂����m��Ȃ��B
�@�u���{�̍��̍K���́A�푈�ɕ��������A�ŗ^����ꂽ���́v�Ƃ����A��������Ԑl�����́A���̒P������ !�@����͌����Đ������Ƃ͌����Ȃ��A����́A���̂��̐��E�̔s�퍑�̎��ԁE����������������������ł���c�@
�@�s��ɂ���Đ��܂��A�g�b�v�E���[�_�[�̒Ǖ��E�S���c�ɌY�c�c�o�ψ����c���ƁE�n���c�r�₦�鎖�̂Ȃ��A���������c���܂��܂Ȍ��ǁc�����́A���{�̐��̕����������Ĕs�킾���œ���ꂽ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����A�傫�ȏ��ł͂Ȃ����낤���B(�e�̐S�@�q�m�炸)�@
�@
�@�w���s�x���w���ȁx�͈Ⴄ�̂ł���A�C�O���_�ɗ^����e�����S����������̂ƂȂ�c�����A�����݂̂Ȃ炸�A���́A�C�O���_�̐����̂��߂ɂ��c���ꂮ����A�����ւ̋�ʁE���ʂƒ��ӂ��̗v�Ȃ̂ł�!?
�@�s�퍑�E���{�́c��������������ꂽ���ɗ������ꂽ�A���a�V�c�B
�@
�@���a�V�c�̕��܂ꂽ��(=��蒼���̂��߂̓y�䑢��)�ʂɂ��Ȃ��E�y�����Ȃ��E�ߋ��ɕ߂���Ȃ��A�͔͂Ƃ��E�B�R�Ƃ����A�����̂��߂̔��z�̓]���������A�������K�v�Ȏ��ł͂Ȃ����낤���B�@(�����ā@���j
�@�����m�푈�������ƌĂ������(�䂦��)�c�����卑�E�A�����J���A�s�퍑�ł���ɂ��S��炸���{�ɑ��č����Ɏ���܂ŁA��ڂ�u�����c�u���Ă��ꂽ�c�Ƃ����̂ɂ��A���ɁE�����ɂ������̂��Ǝv���B
�@�_�����Ӑ}�I�ɗ^����ꂽ�����ɁA�䂪�q�E�l��(=�ۗ����ƁE���{)���A�ǂ��Ώ�����̂��Ƃ����B
�@�����Ă����Ȃ�c���R�A���{����芪���A�A�W�A�����i�אl�j�̏d�v���i���ݕ}���̐��_�j�ɂ��C�t���͂�����(�͂���������)�c����Ɂc����������ւ��e�����y�ڂ��c���̌�̐��X�����ʂȐ푈�������������Ȃǂ͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@(�Q�l�c�I �����E���w�@��w�����̊�u���|�u�ƂȂ�тƁv�F�ߍ����W�z���|�@�����V���f�� ���j
�@�܂��c�w���ۘA���x(=���ۘA���Ɏn�܂�) �Ƃ͉����낤�H�@���̂��߂ɐ��܂ꂽ�̂��낤 ?�@
�@���̒����c���E�����c�卑�E�������킸�c�܂��A���Ƃ����A�ɉ������Ȃ����ł���Ƃ��Ă��c���ꂾ���A���܂��܂Ȗ��E�ۑ������E�ǂ����܂�E�h�ꓮ�����Łc�i�ƒ�ɗႦ��A������e�̗����ɂ���j���A�̖����Ƃ͉����낤�H�@���O�́c�ł͂Ȃ��c����́E���́c���ׂĂ̌��ʕɑ��Ă̖��߁E�w���������Ƃ������������A���̂Ȃ�킢�Ȃ̂��낤���H�@���̎��Ԃ́c���݂̌����Ƃ����c�P�Ȃ�`���ゾ���̂��̂Ȃ̂��낤��?�@�������݂̕K�v���͉����ɂ���̂��낤 ?�@��������̊����c�H�@����A���ꂱ�����A�_�̎q�E�l��(�e����)�������A�����̏W���̂Ƃ͌����Ȃ����낤���B�@
�n�[�h(����)�@���@�\�t�g(����)
�@�l�ނ͍����A�}�X�R�~�푈(��O�����E���)�̐^�������ɂ��鎖�����o���Ă��Ȃ��c�C�t���Ă��Ȃ��c�A�����J�ɂ��Ă��E���V�A�ɂ��Ă��E�����ɂ��Ă��c�܂��āA��i���Ɏ����Ắc!
�@�Ⴆ���́A���̒����̍U����(�k���N���܂߂�)�A�}�X�E���f�B�A�̑��݂Ȃ����Ă͂��蓾�Ȃ������ł���c���═��푈�Ƃ����̂́A����ɕt���������̂ł���ɉ߂��Ȃ��̂ł���c�S�ẮA���̌����ɂ����̂Ȃ̂��B
�@�e����N�[�f�^�[�Ȃ�Ƃ��������A����푈�̎���͊��ɏI����Ă���B�V�̋����ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̎�ςŏ���ɓ����Ă���B
�@
�@�Ē��������Ƃ��c�Ċؓ������Ƃ��c�Ⴆ�Γ��{�̐V���́A(�����ɔz��?�����E���s�I��)���o���E�^�C�g���̈�E����Ɋ��҂����߁E����𗘗p�����e����]�ɂ��A���Ɩڐ��ł����{�U���c����!�@
�@���t�̈�E����M�i�������j���Ă���c����ȓ��{�̏��A���ԈˑR�Ƃ������o�ł��܂ł������Ƒ����Ă��Ắc��I�݂̂Ȃ炸�����I(�o�ϓI)�ɂ��A�Y���Y���E�Y���Y���Ɛ��ނ̓���H�邵���Ȃ����낤�B�@�@
���j�̐ߖځE�ߖڂɓo�ꂷ�� ���Ԑl�̗�
�@��������A���ꂩ��́c
�@�w���E��ƁE�����E���y�E�X�|�[�c�E�{�����e�B�A���X�c�l��E���Ƃ���Ȃ��E���܂��܂ȗ���ł���������̑����C�O�ɕ�(������)���A��J�E����̊����E�������Ȃ���A�F�D�̓����J�����Ƃ���l����!�@�e����]�𒆐S�Ƃ������Ɩڐ��ł͂Ȃ��A�������̌���ɗ������A���������ڐ��ɂ����ڂ������E���d���E��]������c���܂��܂��}�X�R�~�U���ɘf�킳��鎖�Ȃ��E�x�炳��鎖�Ȃ��A�����̓��Ɍ�������簐i(�܂�����)���� !�@�ނ��덡�����A�����ő�̃`�����X�̎��Ƒ�����ׂ��ł���c!
�@�������Ԑl�̗��B�@�v���c���X�̂����wNHK�̒��������x�w���j�h���}�x�ɂ�����悤�Ɂc����͐̂��炠�������ۂƂ������A��i�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�Ⴆ�A�嗤�̐�n����̈����g���̎��c�G�R��邻�̐�X�Łc�G�E�����̋�ʂȂ��A�ނ���(����)���E��(������)���E�������̋��n���~���Ă��ꂽ�̂́A���n�̒����l�B ���N�l�c�\�A�l������̂����m��Ȃ��c�������A���{�l�����܂��܂ȏꏊ�ňٖM�l���~�����̂����m��Ȃ��B�@(���̕���A�����������B)
�@�l�����Ȃ��c���̓y�n�E���̓y�n�����Ԑl�������̂ł����c�����u�q(��)���v�����������炱���A���{�l�͋~���E�A���̓r�ɒ��������o�����B���������ɂ����āE���n�̐l�X�ɋ~��ꂽ�c!�@�܂��܂��A�������̒m��Ȃ����j�I�����E�h���}�������ς��B����Ă���ɈႢ�Ȃ�!�@�^�C���ɂ��c��㌻�n�ɕ�(������)���A���{�̔_�����w�����čs�����A���{�l�̑��ՁE�������c����Ă���B
�@����Ō����c
�@�@�r�O�����̂悤�ȁA�|��ƁE�G�b�Z�C�X�g���a������!�@(�Q�l�c�w�����ցA�ӂ������x�V���Њ����)
�@�e���T�E�e�������̂悤�ȁc���̕��䗠�ł͂��܂��܂ȋ�J���d�˂Ȃ�����c�A�W�A�̉̕P�ƌĂ��A�f���炵���V���K�[�����݂����B
�@���́c�V��j������Ȃ��A���������{�������������E��(���邨)�����c�����l�̑����͑傫���B
�@�������A�����j���ɂ����Ă��A�ׂɐ����悤�Ƃ���D�ꂽ�����Ƃ͑��݂���B
�@�w���z����x���f�����؍��E���咆�哝�� (�J�g���b�N���k) �́A�j�㏉�����؋����ɂ���C�x���g�A�w���[���h�J�b�v�J�Áx�̂��߁A�^�}�̉����傫�ȗv�E�����ԏサ�A������̎�����E������͂ЂƂ܂��u���āc���{�ɂ��т��їv�l�𑗂荞�݂Ȃ���A���{�����J���̂��߂��؍��ł̐��j�㏉�߂��́A(�ւ����Ă���)�w���{��ł̑�R���T�[�g�x(=�wCHAGE & ASKA�x�ɂ��A�`�����e�B�[�E�R���T�[�g)���J�Â��ꂽ�B����́A���{�l�A�[�e�B�X�g�Ƃ��ď��߂Ă��ő�C�x���g�������B�@(�����؍��ɂ����āA��������{�̍��̐ď��̂��߂ɂ� !?)�@
�@
�@���̎��A�哝�̕v�l�́c�w�O�\���x�������a�R���T�[�g���J���A�؍��E�k���N�̍����ɓ����Ɍ�������!�x�c�E���E�k����ɂȂ�Ƃ����A�傫�Ȗ���`���Ă���ꂽ�Ƃ���!�@�����̍��ۏ�E���܂��܂ȕ����I�E��I���E����ɂ��A����͊���Ȃ���������ǁB���́A�w���{�����J���x�̂����A���{�̃A�[�e�B�X�g���w�����Ȃ���E�擪�ɗ����Ėz�������̂��A(������)�w�؍����{�x�������B
�@��킭�A���e���Ƃ̑�\�E�p�哝���ɂ��c��������E�哝�����������Ȃ��������B���̕������A�k�E��E���{�A�܂����ӏ����E���f�B�A���X�������������Łc���Ė���������̂Ȃ��A�V���������̂��߂̑̐��ł����āA���g�݂Ȃ���A�ނ���A������_�@�Ƃ��āA���ЁA���߂��Ăق������́B
�@�܂��ACHAGE & ASKA�ɂ����k�����ʼn̂�ꂽ�����W�N�����ė��W�@�܂�Ŏ��O�̋Ȃł����邩�̂悤�ɉ̂����Ȃ�C&A�����āc�����������̂��낤�A���̎����ϋq�̊������Y����Ȃ��B
�@�ނ�͂��́A���i�R���y���ɂ��A�W�A�̑�\�Ƃ��ĘA���o��B���ɂ��A�k���E�p���E����A�W�A�c!�@�@
�@���瓮�����Ƃ͂����A�����͈͂ŁE���̏�����U�����߂́u�S���w�v�������闝�_�ƁE�]�_�ƁB�����܂Ō�����̂Ȃ�A���́A�����Ǝ��̑O�ɍs���o���Ȃ���?�@�Ƃ��������_�E��������ь������Łc
�@�X�|�[�c�E�����ƁA�A���g�j�I�������̑��݂͑傫���B�ŎZ�̂Ȃ��A���_�E���������A���E�k���a�O���B����͗����̌����������A���ł��������čs���Ă���A������E�ЂƂ��Ŋ撣���Ă������B�@
�@�����āA�\�t�g�o���N��\�E���@���`���̑��݁B
�@������Љ��ɂ����āc���������E���������c�Ƃ����A��������E�s��̍őO������ޗ���ɂ���Ȃ���c(=���N���������J�̗��j���A����̑̌��ɂ�����������A���e���ƁE�؍��Ƃ��Ă����������߂����A���̑�\�I����ɂ���Ȃ���)�c�������ɂ̖ړI�Ƃ���Ƃ���́c
�@�E�����z�����A���_�E���������c�����{��k�������P�E���������Ƃ��āA �w�E�����x���w���R�G�l���M�[�̓����x�������A�w�K���̊�{�E�o���_�x�ł���Ƃ��āA�E���E�k�̂��߁A���E�̂��߂ɁA���܂��܂ȍ�������z���Ȃ���A���L���ϓ_�ɗ������A���E�v���B�@��A�s���ȑ������B
�@�������́A�܂��܂�������Ă���B
�@����������c���łɕ����͌��́E�̋�ʂȂ��A��E���I�蕪���Ȃ���A�ǂ�ǂ�A�i�߂��čs���Ă���̂����m��Ȃ��B�@
�@
�@�����̎�(=�����ڐ��E���ԗ�)�����ɂ������āA�܂����߂ɂ�������ƔF�����ׂ��������̂ł͂Ȃ����낤���B���̎���u���ė��j������Ă��A�܂��������L���ɓ����Ă��A����͕����I�E�\�ʓI�����ɗ��܂�A���Ƃ������Ƃ��i��ł�(=�ɉh���Ă�)�c�V�̓����ɍ���Ȃ����́c�������̂Ȃ����́c(�l�ԂƂ��Ċ̐S��)��I�����A�܂�����y���́c�����I�ɖ��v���A�P�v���a�̂��߂ɂ́A�����̌`��ʂ��ĕK�������߂����ɈႢ�Ȃ��c�܂��Ă��ꂼ��̍��ɁA�ۗ�����(=���e���ƁE��e���ƁE�V�g��<=���l�E������>����)�Ƃ��Ă̔F�����Ȃ���c�ǂ�ȂɊ撣���Ă��E�撣���Ă��A����͎����I�Ɂc�^�C�E��C�������čs���B�@
�@���L���E�_��������Ԑ�(=�q�ϐ�)�ƁA��������Ƃ��������m���A����������! (=���{���E���E�����߂�)�A�����������i�s�������厖�ł���A�}����鎞�ł͂Ȃ����낤���i�Ȃ��������낤��)�B
�@�擪�ɗ����}�X�E���f�B�A�ɂ́A������P�Ȃ����s�����Ƃ��Ă����������A�㐶�ɂȂ��ōs���w�͂����ė~�����B
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����B
�@�u�������l�Ԃ����̐�����ړI�́A���X�̕�炵�̒����琶�����w��сx�A�����𐬂��I������(������)�ɐ����� �w��т�̊�����x ���ł���A����͐l�X������A����������Ƃ����A�w��d�̖ړI�x�̏�ɐ��藧������łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v
�@�c�ƁB
�@�f�G�ɉԂ��������Ȃ�A�����Œ��߂Ă��邾���ł͂܂�Ȃ��B�����̐l�ɊςĂ��炢�A�������E�^���Ăق����̂��B�@
�@�����c�Ƃ͖�����́c�����I�E�o�ϓI�ł̋����ǐ��E�ی�̉��A�ł͂Ȃ��c���ɂɂ͎��炪����o�����A�����E����������I����łȂ��Ắc�܂������ɓ��B���Ȃ���A�`���ǂ�Ȃɐ������悤�ƁA�����͂����͐��ނ��E����(�Ƃ���)���čs�������Ȃ��Ƃ����c�����E���킸�c�卑�E�������킸�A���߂������R�̖@�������̂悤��(=��d�̖ړI)�g�ݗ��Ă��Ă���A�Ƃ������Ȃ̂��낤�B
�@���̏�ł́A�f�Ղł���E�C�O�𗬂ł���c���ݕ}���̐��_�ł���c���̂��߂ɗ^����ꂽ�E�V�ϒn��(=�I���E���@)�ł���c������x�A���_�ɖ߂�Ȃ����Ƃ����c�V�̌x��(=�e�S)�Ȃ̂������B
�@���͂�A���̓��(=�卑�ǐ�)�́A���{�������̖��ł͂Ȃ��Ǝv����B
�@�k�Ђɂ���Ĕj�ꂽ�A���܂��܂Ȋ��E������������u�����܂܂Ɂc�܂��A�k�Ђɂ͊W�Ȃ��A�S���I�ɍL�������A���q����E�l�����E��Ƒ��c����������Ƃ��Đ�����A�d�C�E�K�X�E�����g�p�ʂ̌����c����ɕ֏悵���u�������M��̒l�グ�v�c�����͏���ňĂɂ͊W�Ȃ��A�t���[�p�X�ŁE�������o�Ŏ��{����čs���c���́u�Œ莑�Y�Ő��x�v�Ɠ����c�Z��ł��Ă��E���Ȃ��Ă��A�Ƃ����c!
�@����ȍ��̒n�������̂̐[���ȏ����ז���̂܂܂Ɂc���̎{�݂̍ĉғ��E�����H����D�悷��A���{�o�ς������E�D�i�C�ɂȂ������o����Ƃ����̂́A�Ȃ�Ƃ��c!�@���R�̋��فE�،h�̔O���щz�����A�E�T�M�̎O�i���т̂悤�ȁA�����C���t���̖���B
�@���R�j��E���]��Q�E�픚�̍ė��ɋ����Ȃ����X�Ƃ������X���߂����čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂́A�ǂ��݂Ă����R����Ȃ��B
�@�u�����v�u�����v�����|�����́A������u���]��Q�v�ł���c�O�҂͂Ȃ܂����߂��t���A���̎�i���l���邯��ǁA��҂́c�i�ގ����E�ނ������o���Ȃ��A�s����^���E�����鐶���̑����~�߁E�˘f�킹�c���ɂ́A�}�C�i�X�̒n�_�ɂ܂ł��ǂ�����
!�@
�@��ǓI�ɑ�����A��͂�c���ƓI�E���E�I�K�͂̍ЊQ�͉��̋N����̂�(�N�����̂�)�A�Ƃ����͍��E����������c���{������܂ŕ���ŗ������E�s���̂������U��Ԃ�c�����ŏ��߂āA(��̓I��)�ꂩ���蒼���A������������_�ɗ����Ԃ��c�Ƃ����̂��A�������{���E���E���u����Ă��闧��ł���E�g���ł���c���R�ł͂Ȃ��E�K�R�Ƃ��ė^����ꂽ�����ł���(=���j�I�������E�V�̈Ӑ}�c���j�͌J��Ԃ���鏊��<�䂦��>)�c���R�ЊQ���������ߓI�o�ω̌J��Ԃ����A�ʂ������A�����̎q�������Ɍ��S�Ɉ����p����čs�����̂Ȃ̂��c�����Ǝv�����̂��A�t�ɖ��ʂȉ�蓹(���ʌ���)�����Ă͂��Ȃ����낤���A�Ƃ����c!?�@
���̂���̂Ƃ��� �푈 �͗L�� �� ���_����̂Ƃ��� ���� �͖���
�@�����Ă����ڎw���ׂ����́A�����ł͂Ȃ��E�����ł���c!
�@��̂��́A��ꎟ���E���E����E�c�Ȃ�ʁA���x�����A�_�̖{���̖ړI�E�肢�ł���A��O�����E���E���E����(=���E�̂��߂̐��E�I�c�_�E���_)�Ƃ��đh(��݂���)���c���̂��߂��n���ł���(=���̔��@)�E���Y�ł���c�l�H�̐��E�Ƃ����̂�(=�}�X�R�~�̑䓪�E�o�ρE�O���c��Â��Ƃ��c�N�����Ƃ��c)�A�܂��A�����̊�Ղ������ꂽ��ł́E���̌��ʂƂ��ė^��������̂ł���c���ʂ̉ƒ�ɒu�������čl���Ă݂Ă�����悤�Ɂc���̍��{���E���Ԃ���������̂��A���̓��{�́E���E�e���̎���E���Ԃł͂Ȃ����낤���B
�@
�@����ł́A�u���{�b�g�J���v�@�u�F���J���v�c����ł́A�u�������v�E���v�@�u�������v�E���������v�c��ѐ��̂Ȃ��A�����ɂ��Ă݂�A�����������A���ׂĂ��˘f��������c�E�������̌J��Ԃ��B
�@�Ƃ������A�������́c�����I�ɂ��E��I�ɂ��A�[���̒n�_�͋����A�}�C�i�X�̒n�_�����蒼���ׂ��ۑ�������ς��ɕ���(=���R�j���E��������u�E�ʼn������g������)�c(�n���S�̂�)�S�[���ł͂Ȃ��A�o���_�Ɉ����߂��ꂽ�悤�ȏ�ɗ�������Ă���c(���ׂẮA�a������Ă������Ƃ͂����B)
�@�������A�ɗ͗�Âɍl����c���{�ɂƂ��Ă��w�����{��k���x�Ƃ����̂́A����(=���A�ۗ����j=��蒼���̗��j��)�o���_�E���P�Ƃ��ė^����ꂽ�A�Ӌ`����E�V���ȑ����Ƃ��đ�����ׂ����̂Ȃ̂����m��Ȃ��c!?
�@������ƌ����B�@
�@�ꌾ�ł����A�O�҂́c���Ƃ̓���(=���R�̌b�݁E�Y��)�E�l�Ԑ�(=�ǂ݁E�����E�Z�ՁB���N�̊�b����E�ƒ닳��E�Љ��B���R�̕ی�Ǘ��E�琬�B)���O��E�m������Ă���c���オ�ǂ�Ȃɕς�낤�ƁA��̗^����ꂽ�����ɑ��āA��������Ƃ�����{�I������A�����ΐ��藧������c
�@��҂́c���Ƃ����{���E�������A�����閈�����̈�E��ɁA�Վ����c��c�Վ��ψ���𗧂��グ�A��蒼���̂��߁E�҉�̂��߁A��ۂƂȂ��Ėz�������Ƃ��Ă��c���̌��ł́A�Ɖu�E��R�͂��Ȃ����߂Ɂc�����͊�����Ă��E���x�J��Ԃ��Ă��A����Ȃ��E����Ȃ��A�̘A���c�e��S�~�̊g��c�~�}��ÁE�x���̑��݁c��̌����Ȃ��E�ی��̂Ȃ��A���}���u�̌J��Ԃ��E���z���B�@
�@�܂��ߔN�������ƌ�����A���f�w�E�t�c���g���c�f�r�E�p�j�������b���B����(=IT���)�ւ̉ߓx�̈ˑ����琶�܂��A���n�E����Ώ��̎�̉�(=�i�r�ɗ��邠�܂�A����̏������������)�B�������𖾂���Ηǂ��Ƃ���A��I�����̌y���B�s���E�X�g���X�ɂ�鎖���E���̂̑����c�F�m�ǁc���B���␔�l��1�l�����ɐN����鎞��ł��邩��E�@���ɂ��Ă��̌��ۂ�H���~�߂�̂��Ƃ����A���ꂼ����������E��ËƊE������(�M��)�̒��S�Ƃ����悤�ȁA�����Ƃ��炵���Љ�ہB
�@�l�Ԃ��E���R���A�n���̌����͓����B�����́A(�쒷�̗����ɂ����l����)�������E���̏��ԁE��{�����̔c�����y���������ʂ̏��Y�ł���E�㏞�ł���c���R����u�������ʂł���B
�@�̂̓V�C�\��ɂ́c���̂悤�ȁA�u�C�ۑ�n�܂��Ĉȗ��́c�v�@�u�ߋ����\�N�A����������̂Ȃ��c�v�Ƃ����A�����E�����̗���ł͂Ȃ��c
�@�u���v����o���A�G�߂̕ς��ڂ��ӎ����c�~�J���I���A�u�[�����v�ɉJ���ς��ƁA�Ă̓������ӎ����c�����ƁA����L���������B���R�Ƌ��ɐ����Ă����B
�@���~�ɂȂ�ƁA�����܌����u���t���a�v���A���ł́u�n�k���a�v�̂悤�ȃC���[�W������Ă��܂��B
�@�ЊQ�̑O�����@�����A(�_��100%���ꂽ)���R�̐������̂����̏ꂩ�炢�Ȃ��Ȃ�Ƃ����A���P�B
�@�t�Ɂc�̎��ɂ���A�u�ُ�ɑ����������ʎ��́@�͂��O���ł���v �Ƃ����A���P�B�@
�B�R�Ƃ��� ���@ �� �ړI ������ɂȂ����
�@�܊p�́A�w�V���ɂ����{�����_�x���c����ɕ֏悵���E�ߓx���u�������~(=�n�������̖����E�k��)�ɂ����{�����_�v�ɂ���āA���������R�̌b�����j�����Ă��܂����B�@
�@�������A���R�͒P���Ɉ�ł͂Ȃ����낤�B
�@�����ɂ��āA���]�������������Ă����c
�@�w�p�������A�ꐶ��������Ă����c!�x
�@�c�ƁB
�@
�@�����̐������́c�u�����_�v���̂��̂ɑ���A���S�����B���@�E���������ɂ��c���{�Ɠ��̐��`�����琶�܂���A�l�U���B ���f�B�A�́E�C�f�I���[�O�́c��|(=�����_)���O�ꂽ�A����I���ߌ����B�@���ǂ͂���炪�c���v�̉��E�݁A�擱���������Ԃ���(=�|�C���g���h������)�c���[�_�[�̑��݂��Ȃ��E�ړI�̂Ȃ��A�B���ȓ��{�����_��グ�Ă��܂����B�@�@
�@�v�������̌���(=�l�U���E�ߌ���)���A���̓��{�Љ�ɉ��������炵�A�ǂ��𗧂��ė����̂��낤?�@
�@�t�ɁA�����ɂ�����邠�܂�A���̎��X�̐���A���ƓI�E���E�I���E�ۑ���ǂꂾ�����u���A���ߍ���ŗ��������B�����Ă��̍������ۂ͓r�₦�鎖�Ȃ����X�Ƃ��āA�����Ɏ���܂ő����Ă���B�@
�@�u�_��ɁE�^���Ɏ~�߁c�l�X�Ɓc�v
�@�Ƃ����A���̏����̌��t�̗��ɉB���ꂽ�c�B���ȁA(�����`����)�ېg�Ƃ������A�ۑS�Ƃ������B
�@�g���(=��)�c��������l�߁A���ꂾ���𗊂�Ƃ��āA����ɓo��l�߂��l�B�������\�c�ЂƂ��炰�ł����āA��r�E�ᔻ�ȂǏo����Ȃ�(�Ȃ�����)�B�@
�@�l�Ԃ́A�w��d�̖ړI�x�������đn������Ă���Ƃ���(=�����̂��߁E���̂���)�B���������������^�����Ȃ���(=�l�I�~�])�A���I�~�]�������Ȃ����E�����������Ȃ��悤�n������Ă���A�Ƃ��������B
�@�̋��E�V���́A���������R�������������������c!?
�@���̎���ɂ��c������l�Ԃ̍��{������m��Ȃ������Ƃ���}�X���f�B�A���E�������������_���c���̓��{��グ�ė����B�܂��A�ė����B
�@�����n����c�v�������Ȃ��A�ˑR�������{��k���B�@���������A���̂��̓��{�c!
�@�Ƃ͂����A�����߂���A�����́c����̐l�����͂������A���Ƃ����n��̐l�������E�c�̂��c�����̂��߁c��Вn�̂��߂Ɂc���͂��Ăт����Ȃ���K���ŋ���ł���Ă��c���E�S�̂̉ۑ�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ����グ���Ȃ��A�n��I�E�����I���Ƃ��đ������A�܊p�̂����̊|�������`���I�E�V��I�Ή��ɗ��܂��A�Ȃ��Ȃ��O�ɂ͐i�܂Ȃ��B�n���ƁE�����Ƃ̊��o�̑���c�n���̐��͂Ȃ��Ȃ��{���ɂ́A�����E�����ɂ͓͂��Ȃ��B
�@(��c���̎��X�̖��E�ۑ�ɉ������u�e�Ȓ��̑Ή��v�ł͂Ȃ��A�\�c�ЂƂ��炰�́u���[�����ɂ��A�ꗥ�E��ӓ|�̎����I�Ή��v�B�e�Ȓ����d�݁E���l�ς������Ȃ���Ηǂ����A�Ƃ����v���B)
�@�����{��k�����A������4�N���o��(���E2015�N����)�B �������Ɏ����ẮA�I�킩��70�N (���E2015�N����) !�@�����A������`�E���Ǝ�`����̏I��(���イ����)���}�������A��n��������́A���ė��������ł͂Ȃ��A���E�̖�����B
�@���X�Ȃ����c�u�����n�v�Ɓu���@�����v�c�u���B���� �K�B�����v�̂悤�Ȃ��̖������A���E�͂ǂ������Ă���̂��낤�B�@
�@�u���s�\�z�v�c���������A�u���́A����ȉ��v�Ă����܂ꂽ�̂��c�v �Ƃ����A���{����Ȃǂ͍l���Ȃ��B
�@�ߋ��̑��{���E�s���̂�����B�����A�s�\�z���Ɍ���Ȃ��A���{���S�̖̂���E�ۑ�c���̑�\�̗���ɂ���̂��u���s�\�z�v�c����̗���E�K�R�ł����B
�@�ɗ́E���_(=���n��)�ɖ߂��čl����c�Ⴆ�A�u�������v�v���u�������v�v�͂��̍��{�ɂ����Ė��炩�ɂȂ����Ă���̂ł���A(���ɂɂ�)���Ƃ̖����̂��߂�z�肵���A��̂��������E���f���Ƃ��ė����グ��ꂽ�A�s�\�z���B
�@���̓�ւ����z����̂ɂ́A(���ꂪ�傫����Α傫���ق�) �ǂ����Ă��A�\���E�����c���ɂ͎�ϓI�����͕t�����̂��B
�@�l�Ԑ����Ƃ��E�������Ƃ��̌l�U���B��搮���ɂ���ēy�n�̐l������E������Ƃ����A�����Ƃ��̒��ۓI�E�Z���`�����^���Ȗ��ւ���������Ȃǂ́A�ǂ��݂Ă����v���B�@
�@�����Ԃ́A���������Ɋ��炳�ꂽ���_�c�Đ��B�Â� ! �Ƃ��������l���Ȃ��B�@
�@ ��̐��A��̐��Ƃ�������ǁc����������ɂ����̐������߁c���̋�̐���������Ă��c����ɑ��Ă��������ے肵�A����ێ��ɂ�����锽�Δh�B���̋�̐��������o�������~�߂Ă��܂��Ă���̂͂��������A�ǂ����ȂA�Ɩ���Ă��d���̂Ȃ��悤�ȁA���̓��{�̌Â�����̈����K�B
�@�\�ʓI�E��ʏ펯�͂ЂƂ܂��u���āc���������c������(�擱��)�̂��̍���ɂ�����̂������o���E�t�H���[����c��������f�B�A���A���߂Ĉ���炢�͂������~�������́B
�@���ʂ���Ɏ��_��u���A����Ɍ����钧���(=�_�ɑI�ꂽ�l)�̎v���͖�������c���̒��̍����́A����ȂƂ��납�琶�܂��ɈႢ�Ȃ��B�@�@�@
�@�@����c�����{�c�Ɠ�����������܂Ȃ��悤�A�`�����X���Ȃ��悤�A����̓��e���̂��̂��݂߁A�������I�̓�������킵�čs���ė~�����A�Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�����E�����̋�ʂȂ��@
�@�S�������S�����B
�@�O�҂́c���ʂȑ̌����Ȃ��Ƃ���r�I�ȒP�ɐg�ɕt�����A���Ƃ���l�ł��c�܂���p�ŁE�\�͂�������A�q�ǂ��ɂł��o����B�C�^�Y���c�Q�[���c�������\�E�~�~���\�c�푈�B�@
�@�������A��҂́c���̖ړI���炵�Ă�(=����́E�S�̂̍K�����v��)�A�P�g�ł́A�܂��s�\�ŁB����E���n���������E�̊����A��l�ł������̓��u���W�߁E�S����ɂ�������������Ȃ���A�����ȒP�ɂ͐��藧���Ȃ��B
�@�����Ȃ�c���߂đ����̃��[�_�[(=�m������)�������A�ꌧ�ł��������W�܂�A�����̏o�����ł����Ă��A�����������̏o�����Ƃ��đ����A���͂��čs���ӗ~�E�w�͂̂悤�Ȃ��̂��~�����C�����邯��ǁc?
�@�܂��A���f�B�A���擪�ɗ����āc�u�����n�c��Вn�c�s�\�z�c�̖�����ǂ������邩�v �ƁA���E���_�E�T�_�����ł͂Ȃ��A�����̌���m���ɂ���̓I�Ɏ��₵�E���͗v���̓�������(=����)������Ƃ��c�Ƃ����̂͂ǂ����낤!?
�@�����Ă����Ȃ�A���ʂƂ��Ă���͕K�R�I�ɁA�����ɑ���A(�U���ł͂Ȃ�)���́E�����E�i�W�ɂȂ���Ƃ����B
�@��̉ƒ�Ɠ������c�Ǝ�(����)�̕��S�����Ȃ���E���Ȃ��قǁA����(���ƓI�E���E�I���E�ۑ�)�́A������������B
�@�����A���̂悤�ȏ�ł́c�܂�A���E�����ɂ��蓊������Ƃ������̑̐��ł́c�����͓w�͂���������͕K�������Ƃ����A����Ȕ��z�E���o���Ȃ��Ȃ��(=�g�ɕt���ė��Ȃ����)�c
�@�����̎�҂������A�ڂ̑O�̙��ߓI(���ȂĂ�)�E���l�I�\���ɂ���ڂ������c�����E�o���͂��Ƃ��A�ƒ�E�Ƒ��Ƃ������̂ւ���(������)���Ƃ������A��I�Ȃ��̂ւ��������ӗ~�𔖂ꂳ���E�����Ȃ��Ȃ�̂́A�K�����낤�B(=�X�|�[�c�͑�w���ɂȂ��Ă�����ł��A�Ȃ��Ȃ��g�ɕt���Ȃ�) (=�`�������̌y���E���w���̏d��) (=�ƒ�E�Ƒ��ւ̉��l�ς̌y���c����)
�@
�@���a�V�c�������ꂽ�悤�Ɂc���E���������E�a�O������钆���c�C�O�ɂǂ��f�낤�ƁE�v���悤��(�ى���Ȃ�)�c�Ђ����獑��(=�킪�Ƒ�)�̂��߁E��蒼���̂��߁E����̍������������߂ɁA���������ɗ���(=�D�̒��ɓ���Ȃ���)�c���{�E�����K�ɐs�����ꂽ�B
�@��������Ƃ������@���ړI�������A���{����I�E�����I�Ɉ�v�c�����鎖�ɂ�����c�V�̋�������������������E�����͂����܂��A���������́E����(����)�o�ϗ��ɂȂ���A���{�����~�����B
�@���m��w�����m��w�̈Ⴂ�ɗႦ��Ȃ�c�̂������I�Ή����S�g�I�E���{�I�Ή��̑���c�̂悤��?
�@����Ō����c(�����E�{�y�̋�ʂȂ�)�i���̂Ȃ��E���{�S���Ƃ��Ă��y�䑢��̐��_�������A�C�O�ɐU���Ȃ��A��Ԃ̕����ƂȂ�(�Ȃ���)�̂ł͂Ȃ����낤���B�@
���z�̓]���c�푈�����a�� �u����d�v ?
�@���E���̊Ⴊ������钆�́c���̓��{�̐���s���E�����B
�@
�@(�C�̂������c) �����(�����C���[�W��)�J���t���[�W�����E�t�H���[���邩�̂悤���A�V�c�E�c�@���É��́c
�@�p���I�ւ́c�k�̃p���I�ւ�(=�u�k�����v)�A��v�҈ԗ�K���c�}�E�D���Ǔ��B
�@�쑾���m�������̎�]����������A�c���ł̒����B
�@(���q���܁E�H�{�����̂���������Ȃ���)�@�c��(���{��)�Ƃ͉����ƗF�D�W�ɂ���A�쑾���m�̓����E�g���K�ւ��c���q���v���ɂ��A�����̑Պ����E�֘A�s���ւ����o���B�@�@
�@�P��s���������Ȃ���́A�����������E���O����Ȃ��A���{���̏ے��̗���(=�C���[�W�c)�Ƃ��ẮA���܂��܂����C�����B
�@�@���́c���V�c��ʂ��Ď���ė����c�܂��A�w�V�c����Ƃ̂���x(=���إ���Ȃ�)������������悤�Ɂc
�@�w�c�����抪�����R�x�ɂ́A���P�Ƃ�����̂��A�����ς��Ɉ��Ă���悤�Ɏv����B
�@�@���������{�����́A���R�E����̂��܂��܂ȍЊQ�ɁA�����܂Ő�����Ȃ��قǂɑ������ė�������ǁc�v���A(���X�Ȃ���)�u���R�̋��Ёv�ɂ́A�ǂ�ȍ��x�Ȑ���E�{��ł����Ă��Ă��e�Ղɂ͑ł����ĂȂ��A�c��Ȃ��̂�����B
�@�@(���{�����@�̎��͂悭�͔���Ȃ������)�v�����c�w�c���̎��R��x���A�P�Ȃ鋳�P�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���̑��݁E������������Ɛg�߂ɒu���A�������̒��ɂ�������Ǝ�����E�������čs���Ă����Ȃ�A�͂�����������Ă����̂����m��Ȃ��c������ЊQ�卑�E���{���}���Ă͂��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@�܂��A(30�N�]��ɋy��)�c���q�����́c(���{���ɗ��܂�Ȃ�)�w���E�̐��^�E�����x������A�����v���ƁE���g���ɂ́A���X�Ȃ�ʂ��̂��������A����͍��ł��A���X�Ƃ��đ������čs���Ă���̂ł���B
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����B�w�n���̎O���̓�́A�C�ł���x�ƁB���^�E���������ẮA���{�̖����E���E�̖����͂Ȃ����낤�B
�@�J��Ԃ��悤������ǁc�@�@
�@�w ���Ƃɂ́@���̂������� �x �Ƃ����B�@
�@���a�V�c���w�������~���錾�x�B�@
�@������A����ɗႦ��Ȃ�B�@
�@�j���u���v �� �u�����Ȃ��v���B�����́A���̃��[�_�[ (�g�b�v) �́A�����ꌾ�̌��ӁE���f�ɂ���āA���̒��̗���E����A�K�����ƕς�鎖������Ƃ����c��������E���P�Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@�l���͌��X���A�w�F�@���傤�����x�Ƃ��đn������Ă���̂�����A���ꂪ(=�j����))�^�S���甭����ꂽ���̂ł���A����͎����I�ɑ���̐S�ɗn������ōs���Ƃ����c(�G���ƌĂ�悤�Ɓc)�B
�@�������Ăт́c�S�Ă̋ƊE�ɂ����āA���̗���E���l�ς�����鎞��c���{���������_�c!?�@
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����B
�@�w�����̈�E��ɂ́A���ꂼ��Ӗ������߂��E�^�����Ă����x
�@�ƁB
�@�u���A�ۗ����j�����s�̐ςݏd�ˁv�ɂ��A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂ͐��E�̎���͕t���ė��Ȃ�����ǁc����������́A�u5�v�E�u6�v�Ƃ����A�u���ׁv�E�u�������v�ł͂Ȃ��c�u7�v�E�u8�v�Ƃ����A�u�j���v���u�ďo���v(�ăX�^�[�g)�̎���c!
�@
�@�܂�A���70�N���}�������ł���A�u�푈�Ƃ������z�v�́A���ł��ߋ��̂��̂ƂȂ�E��蕥��ꂽ����ł���A�u���L�v�̔��W�ւƌ��������㌗�Ƒ�����ׂ��ł���c!
�@�����I�ɂ́c�u�����n�v�́A�v���������z�̓]���ɂ��A���Ƃ���Ό���v���悤�Ƃ��c�u��n�̈ڐ݁v�ł͂Ȃ��E���̊�n�͔p���E���_�ɖ߂��āE���߂āc
�@�w�ό����Ɓx�Ȃǂ��w�n���Y�Ɓx�A�܂����R�G�l���M�[(���f�G�l���M�[�Ȃ�)�̓����c�C���t���ɐ�ւ��� �c���ׂĂ��u�r���v�ł͂Ȃ��c�n���̐l�����c(��킭��)�ČR�������������A�������E�A�����J�̋����̂��ƁA���ƓI�K�͂̓W�J�Ƃ��āc
�@������̂āc�u�v�����\�Z�v�Ƃ���(���đo���ɂƂ��Ă�)�S���ƂȂ��E�������̂Ȃ��c�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A������Ƃ����A(����̎��R����������)���ƎY����ڎw���Ē��킷��(�����߂�)�Ƃ����̂͂ǂ����낤 !?�@�W���{�̃n���C�W��ڎw���� !?�@(�����Ƃ��A��ĂƂ����C��܂ł͕ς����Ȃ�����ǁc����)�@
�@�ό������ł͂Ȃ��A�Ⴆ�A�T�~�b�g�I?�Ȑ����W�̏�ɗ��p���c�u��n�v�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u���c�E���_����c�̏�v�Ƃ��čv������ !?
�@�����Ă���́A�S���ɍL�����n�̕Ԋ�(�P��)�ɂȂ���A������f���E����{�ƂȂ��āA�s���s���́A���E�I�W�J�ɂ܂ł��v������ !�@���̂��߂ɂ��A�v���������z�̓]���������s���ł���A�}��������㌗�ւ̓˓��c!?�@
�@
�@����푈 �� ���O�푈(=�}�X�R�~�푈)���^�̓�����(�A�����J�����ɗ��܂�Ȃ�)�̒a���c!
�@�ǂ��K���𑱂��邩(=�y��E��{�̊m��)�A�����K���𑱂��邩��(=���}���u�̌J��Ԃ�)�A���̐l�́E�������Ƃ̖������ʒu�t����A���O��E�������_�ƂȂ��čs�������낤�B
�@�ߔN�́A���{�ւ��w���������x�A�܂��w������ꌴ�����́x�����P(=���ʋ��t)�Ƃ���A(�h�C�c�E�����P�������n�߂Ƃ���)�e����]�ɂ���u�E�������i�^���v���A���E�I�K���ōL�������悤�Ȋ�������B
�@����Ȓ��Łc���́E�̐S�̂��̓��{�́A�ǂ��i�����Ƃ��Ă���̂��낤 ?�@�u���{�̏펯�́@���E�̔�펯�v�c�u���E�̏펯�́@�V���̔�펯�v�Ƃ���悤�ȁA����Ȏ��オ�K���̂́A���������Ȃ���̘b�Ȃ̂����m��Ȃ��B���߂Ȃ��ł������B
�@����̐����̎��A�w�����n�̓P�p�x�Ƃ����A�����E����E���̏I���c����������E�擱����A�E�C����E�q�[���[�i�q���C��)���a������̂́A���̓��̎����낤�B�@
�@�������A�X�Ɏv�����́c
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����B�ꍑ�єz��`�E������`�̎���͏I���܂����A�ƁB
�@�������x�z���Ă��邩��Ƃ����āA�����������ƂƌĂԂɂ́A���v���B �ނ���A���̌��͂ł����đ����ɊÂ��Ă���̂́A�єz���ƂȂ̂����m��Ȃ��B
�@����Ȏ���ɓo�ꂵ�c���̎��𑁂����@�m���A�ő����ł����Ď����̂��߂ɖ�N�ɂȂ��Ă����̂́A�A�����J�哝�́E�g�����v�����Ȃ̂����m��Ȃ��B �@
�@
�@�ǂ�Ȃɕn�����ƒ�Ɉ���Ă��A�e�d����q���͂���B����Ɠ����悤�Ɂc�����I���̉��������ł́A���̎���E���̒��ɂ͒ʗp���Ȃ��B
�@���̎�҂����ɂ́A(�ėՂ̃L���X�g�̍v���ɂ��)�@�����w���߁x(�w��p��)�͑��݂��Ȃ��Ƃ����B
�@�����������}�������ł���c�����āA(�����Ƃ��炵��)�w�V�g�̗U�f�x�ɏ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�l�Ԏn�c�̎��s���J��Ԃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ꍑ�E�ꍑ���w�����̐��_�x�B�@���̏�ł� �w�����E���h�̐��_�x �������厖�Ƃ����A����Ȏ��㌗���}���Ă���c�Ƃ������Ȃ̂��낤���B�@�����ƁA�����ł���ɈႢ�Ȃ��B
�@����͍X�ɐi�݁c
�@�u�l�ނ́@��Ƒ��v���A�n���́E�V�������{�����E�����Ƃ��鎞��̒��Łc����́A�w��Ƒ��x�Ƃ́A���E�P�ʁE�n���P�ʂł����đΉ����鎞��ł���c
�@�ŐV�̃j���[�X(2022.����)�ɂ����āc
�@�N���������Ĕ���A���̃��V�A�哝�́E�v�[�`������̗��s�E�؍s���A�@���ɂ��Đ������E�[�������邩���A���Ӎ��Ƃ́E�S���E�̖����ł���A���̈Ӗ��ł́c���́A�q�g���[�������㓯�l�c�v�[�`������́A����ɂ�����A����ȓO�ꂵ������ɒu���ꂽ�A�ނ���A�]�����Ȃ̂�������Ȃ��B
�@
�@�l�Ԃ̐ӔC���S�́A��������5%�B����͂��Ƃ��A�q�g���[�ł����Ă��c�v�[�`������ł����Ă��c�k���N�E����������ł����Ă��A�����B���ׂĂ͐_�̈Ӑ}�ł���Ƒ�����ׂ��ł���A���̗^����ꂽ�g��(=�����E����)���A�ǂ��~�߁E�ǂ��Ώ����邩���A�l�Ԃ̐ӔC���S���B
�@����Ȏ�����}���c���V�A�哝�̂��c�܂��A�k���N���c�������E�[��������قǂ́A�����I�E��I�\�͂�������A �q�[���[ �E �q���C�� �������̂��ǂ����ł���A�S�Ă̖��E�ۑ�����̌��_�́A�����ɂ���ɈႢ�Ȃ��B�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(2011�N�@�`�@2022�N)�@
![]()
�@
�@���NjL���@�@����ς�A���Ǝd���� !?
�@NTT�E�d�b��(=�^�E���y�[�W&�n���[�y�[�W)�̒��́A�w�������y�[�W�x���n�߂Ƃ������I�@�ւ�T�����Ă݂āA���Â��v���B�@(�Ƃ����Ă��A�ق�̓����t�߂̘b������ǁc�j
�@���͂������A��������́u�s�v�������Ƃ��Ă��c�@
�@
�@���͂�A���̌��Ǝ��̋�ʂ������͂߂Ȃ��悤�ȁc���̃^�E���y�[�W�Ɍf�ڂ��ꂽ�A���X�̊������c�c�� !
�@
�@���߂āA���̑��ݗ��R�E�ړI��m�肽���Ǝv���Ă��A���炭�N�ɕ����Ă��A�T�v�͂Ƃ������A���̌���Ƀ}�b�`���E��������Ƃ������R��ړI������Ă����l�Ȃǂ��Ȃ����낤�A����ɂ�����A���̖c��Ȓn�������c�̂̑��݁c����c!
�@�����A����}�����ɂ��A���߂Ă��w���Ǝd�����x���{�s���ꂽ���c����}�̐i�o�́A���R�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A���̂��߂̐�����ゾ�����ƁA�����Ŏv�������̂������B���̒��ł́A���ł����̋C�����͕ς��Ȃ��ł���B�����Ƃɂ��Ă��A���̌��_�ł�(=�}�h�ɍS��炸�j�����v���ł���ɈႢ�Ȃ��B
�@���̌�A�����}���������A���A�����Ɏ��邯��ǁA���̐���E�e�[�}���\�ɏo�鎖�͂Ȃ��A���ł͉e���`���Ȃ��A���S�ɏ��������Ă��܂�����������B�@
�@���߂āA(��)����}�ɖ₢�����B�����c
�@�u�������������Ɂi�ǂ�����̔��z�ŁH�j�A���Ǝd�����ɗՂ̂ł����B�v
�@�u�����v���āA���Ǝd�����𒆎~�������̂ł����B�v
�@�����āA(���^�}) �����}�ɂ������Ă݂����c
�@�u���Ǝd�����Ɋւ��ẮA��ɂॐ�ɂ��S�������ė\��ɂȂ��A���̋C�͂Ȃ��̂ł��傤���B�v
�@�Ƃ��������B
�@�����Ɍ����āc�����w���Ǝd�����Ƃ�������x�́A�����}�A(��)����}�A���̑��̓}�A�ǂ���ɂƂ��āA�Ƃ肠�����A�L���E�s�����͔���Ȃ�����ǁc�@
�@�d�b���ɘb��߂��āB
�@
�@���̋@�ւł���Ƃ���́A�u�����ȁv�E�u�@���ȁv�E�u�����ȁv�E�u�����J���ȁv�E�u�_�ѐ��Y�ȁv�E�u�o�ώY�Əȁv�E�u���y��ʏȁv�E�u���ȁv�E�u�h�q�ȁv�c
�@�Ɓc���̑��݂͈ꉞ�A�����o����B(���ɂ́c�̂Ȃ���́c�܂��d�������悤�ȁc�����Ȃ��ł͂Ȃ������)
�@�v���ɁA���E�s�E��E�����@�ւ̂��ꂼ��A���̋�̓I�E���g�ł��邯��ǁc!?
�@���͂�A���݁A���݂̋敪�A�܂����Z�A�Չɂ̋�ʥ���ʁc�͂ЂƂ܂��u���āB
�@�c�c�U����A�c�c�Z���^�[�A�c�c�������A�c�c�����ǁA�c�c�@���ǁA�c�c�@���ǁA�c�c�o�����A�c�c�ē����A�c�c�{���A�c�c�{�ǁA�c�c�x�ǁA�c�c�x���A�c�c�x���A�c�c���ЁA�c�c����A�c�c���c��A�c�c�O���[�v�A�c�c�X�^�b�t�A�c�c��فA�c�c�w���A�c�c�ۗ{���A�c�c�ݏ���A�c�c���C��A�c�c���C���A�c�c�������@���X�c�����ς��A�����ς��B�@
�@���߂Ă��邾���ŁA�C�̉����Ȃ�悤�Ȏ�ނƐ��ł��� !�@
�@�����āA���͂�������Łc
�@���̈�̑g�D�̒��ɁA��R�́u�����v�����݂���B�c�c���A�c�c�ہA�c�c�W�@���X�B
�@�܂����́u�����v�c�u�ہv�E�u�W�v�̈���Ƃ��Ă��A����`�\����́u�d�b��v���n�߁E���܂��܂ȁu�ݔ��v���u����c
�@�����A����ɍ��킹��(������)�A���̈�Ԃ̓��E�ۑ�ł���Ƃ���́A�u�����v�E�u�E���v�E�u�����v�����݂���B�@
�@�����A�ǒ��A�����A�����A�����A�ے��A�ے��㗝�A�����A�W���A�w�����A�����A�Ď��A�Q���@���X�B
�@�w���Ǝd�����x�ɂ����āA����͂����A�c��Ȑ��̂��̂Łc�����Ƃ̕s������E�ɂ�鎫�C����E�ȂǂƂ͖Ⴄ�A�����Ⴄ�悤�ȁc! �@
�@(���\�Ȍ������������Ă��炦��) �������́u�Ǐ�v�ɗႦ��Ɓc
�@�u���͂�A��̎{���悤���Ȃ� !�v
�@�Ƃ��������ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤���B�����v���̂́A���v���낤���B
�@�������A�L���L�����̐��E�B�����ɂ͌f�ڂ���Ȃ��A�����������ɂ͊֗^���Ȃ�?�@���J�̕K�v���̂Ȃ� ?�@�B�ꂽ�g�D�E�c�̂Ȃǂ��A�܂��܂������ς����݂��邩���m��Ȃ��B(���̂悤�ɋ^���Ă��܂�
!)
�@
�@���ɂ��c���܂��܂Ȏ{�݂̐V���E�����c�����E�������𒆐S�E��p?�Ƃ��Đݒu���ꂽ�A�X��(���X)�E�Z��X�c�����ƁA��ʎЉ�E�ƊE�Ƃ̊i���B
�@
�@�����́A(������)����}���u�d�����̑Ώہv�Ƃ������̂ƁA����E���n�̂��̂ł��邩�ǂ����͔���Ȃ�����ǁB
�@�������A���ꂾ�����Ƃ��Ă��c
�@���}���A���~�c�ۗ�? �ɒǂ����܂ꂽ�̂���������ʁA������A�c��Ȃ��̂�����悤�Ɏv����B
�@(�����ɁA�����ɑ���F���̊Â��������������ۂ߂Ȃ��悤�ȁc)
�@(���g�̕K�v���͂Ƃ�����)�y�n���ɂ���ẮA�Ⴆ�Ώ�����E���c�̊w�Z�̐��k�����������A���ԈˑR�Ƃ����������o�̋�������̂����m��Ȃ��B
�@�v�́A���ۂɁA�����̂��߂ɂ�������Ƃ��̌���ɂ����ċ@�\���Ă��邩����肾���c�������A(�������f�l�ɂł���)���̖��̂����������ő������^�������Ȃ�悤�ȁA�g�D��g�D�A�`���E�`���c�̗���ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�@
�@������O�ɂ��āc���{���Ƃ��čl�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����E�ۑ肪�R�ς��Ă���悤�ȁB�@
�@�X�����v�c�s�\�z�c���̗���ƂƂ��Ɂc���炭�A�w�Ō�̉��x?�ƂȂ�ł��낤�A�����w���������v�x�@�w���Ǝd�����x�B
�@
�@���͂�A���H�ɓ����Ă��܂����u���Ǝd�����v���A�Ƃ肠�������_�ɗ����Ԃ�A���́u�^�E���y�[�W�f�ځv�̊������̈�¥��Ȃǂ��܂��A���n�߂Ƃ��E�Q�l�ɂ��E�_�����Ȃ���c
�@�܂�A�u�s�������̌���ŋ@�\���Ă��邩�ǂ����v�Ƃ������̑O��(����猻��̏͂ЂƂ܂��u����)�c�܂��_���̑��x�́A���ꂼ��E���܂��܂��Ƃ��Ă��c
�@�^���}���킸�A���E�����킸��̂ƂȂ��āA���߂��ăX�^�[�g����Ē��������c����A�܂��A�ăX�^�[�g�̂��߂̏����i�K�ɓ��鎖����n�߂ė~�����c�Ɗ�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�@�łȂ���A1000�]���~�Ƃ����A���N�E���N�����čs���A���̖c��ȍ��̎؋�(�����s�c��)�͉i���ɏ����鎖�͂Ȃ��A�����E�����ƁA�X�ɁE�X�ɖc�����čs�������Ȃ����낤�B
�@���̉��v�Ȃ����āA�����Ȃ��c�ƁA���ɂ͎v���邯��� ?
�@�������A�����炻�̑��݂�S�ʔے肷���ł͂Ȃ����A�����������ɂ͂���Ȕ\�͂��E�l�����Ȃ��B
�@�������A�����ԂɍL����ɍL���襑����ɑ����čs�����ł��낤�����̑��݂́A����̗���E�O���[�o�����E�Ȋw���\(�R���s���[�^�[)�̌���ɂ����āA�B���ꂽ���܂��܂Ȗ�襉ۑ肪���X�Ɩ\�I����鎞��̐^�������Łc���ԈˑR�Ƃ����A���̎v���E�͍����Ȃ����̐�����ێ����čs�����Ƃ���p���ɂ́A���͂�A�ǂ̊p�x����l���Ă��^���o���Ȃ����̂�����Ƃ����̂��A�V��j���E���܂��܂ȋƊE�̐l�����E�S���鏎���̑���̎v���ł͂Ȃ����ƁA���ɂ͎v����B
�@�����Ƃɂ��Ă��A����Ȗc����u�����̑g�D�ԁv��O�ɂ��āA���������͗ʂ��Ȃ������Ȃ̂��B(�����s�\�z�������A�o���o���Ɉ�����Ă��܂����c!)
�@�}�X�R�~�푈�̎���ɂ����āA�C�O�ɗ^����C���[�W�̖��ɂ��A�ɗ͔z�����ׂ����B
�@���_�ɖ߂��čl���Ă݂Ă��c
�@�������邽�сE�N���邽�сA�����ɐ����Ƃɔᔻ���W������Ƃ����̂́i�����Ƃ܂ł��ꏏ�ɂȂ��āj�A�ǂ��݂Ă����������B(�����̖ڂɓ͂��Ȃ��A�ɁX�v���C�x�[�g�ȁE�ɒ[�ȗ��͕ʂƂ��Ă��B)
�@���̂悤�Ȓ��r���[�ł͂Ȃ��A�����̑�\�ł���ׂ������Ƃ̊��E�������������ƉA�Ŏx���A���f�B�A�ɂ���ĕ\�ʉ������O�ɁA�����H���~�߂�̂������Ƃ��Ă̖����Ȃ̂ł́H�@�K�E���̖��́A�����Ǘ��̔@���i������)�̌��ʂƂ��Ĕ���������̂ł���A�����Ƃ�������������̂́A�ǂ��݂Ă����������B
�@������(������)�ɂ��Ă��c�����������h���E���C��`�̊��ӎ��̓��Ɏp���E�펯�����ꂽ�悤�Ȋ��o���琶�܂�錾���E�s�ˎ��ł͂Ȃ����낤���B�@
�@���͂⌻��ł́A�ǂ�ȗ��h�Ȋ�Ƃ̑�\�ł����Ă��c
�@�����̌����ŏ���ɋ��ɂ��J���鎖�͏o���Ȃ��E��������������鎖�͏o���Ȃ��E�Г��ݔ�������ɓ��������͏o���Ȃ��c�����E�Ǘ��E�o�������X�̋��ƐӔC��ʂ������ẮA�Ƃ����̂��펯�ł���A�����������B�@
�@���̏ł́c���̌�Łc�����E�����E�����̑O�͑f�ʂ�ŁA�}�X�R�~�����̗���ɐ�������A�i������ɂ��ꂽ�j�����ƂɑΏ�(�R��)����Ƃ����c����ȓ��{�̖������o�E���f�B�A���o���B
�@�������A�����Ƃ����ł͂Ȃ��A������ƊE�̊�{�E����ɂ���̂��A�u�������v�B
�@���ƁE�n���������̗���ł����āA��������ƍ����̑�\�ł���A�ނ�(�����ƁE��ƉƓ��X)��l�E��l�d���E�t�H���[���E�Ǘ�����c���̓��{�Љ�ł́A����炪�t�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B
�@�Ƃ���ōŋ߂́A�u����ҁv�̎c�Ɩ��B�u���{�݁v�̕s���E�s�����B
�@�ނ�Ƃ͊�{�I�ɂ͓�������ɂ���Ȃ���A�����͉��́A�N����̂��c!?�@�����Ƃ��Ă��w�{���̌����x���ǂ������Ă��Ȃ��A�Ƃ������̏��ł͂Ȃ����낤���B����ɂ���������B����̌������B�@
�@���Ȃ݂ɋߔN�A�Ⴆ�u�Z����v(�Ɩ����܂�)�Ȃǂł��܂��܂ȃg���u�����A���{�E���������ŋN���Ă���悤�����c
�@����́A���ɂ��E�w�����ɂ��A���ꂼ��Ɂw�@��E���c�����݂����x�Ƃ��������A�o�������o���Ă��Ȃ����߂ɋN����g���u���ł���Ǝv������ǁc�����ɂ��Ă��A�����A�w�Ȓ��x�͂ǂ̂悤�ɔF�����E�w�����Ă���̂��낤 ?�@�ǂꂾ���S���E������Ă���Ă���̂��낤 ?�@
�@�u�Z����v�Ɍ���Ȃ��B�����̓��퐶���ɂ����āA�ǂꂾ���ӔC���������Č�����Ă���Ă���̂��낤 !?
�@�ߔN��������A���R�ЊQ�A�l�g�����B�@
�@�܂��A����Ȋ���_�����c�����Ƃ��炵��������(=�ނ�ɓ�����悤��)�A�����Ǝ҂̑���B
�@����Ȓ��Łc���R�E�E�l�ԊE�c�t�ďH�~�c�����N���悤�ƁE�v���悤�ƁA�т��Ƃ����Ȃ��A�\�ʂ����܂��܂Ȑ��x�ŏ����������̂悤�ȁA�����S�ɑg�D�����ꂽ�A�����E�����Љ��B�@
�@����Ƃ��c
�@�����������̐��ɒa�����E�l�Ƃ��Đ����čs����ŁA�ŏ��Ɂc�����̊�{���Ɂc�܂����̐ߖځE�ߖڂɂ����b�ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�������B
�@���́u�������̂�����v�ɁA�u���̎�҂����̎��㊴�o�v(=�匠�ݖ��E���̑��d)�ɉ���Ȃ����̂�����Ƃ�����c
�@�����̒����w���ʂȊ������x�́A����Ƌ��ɁA�����̌`�Ŏ��R����(����)���Ă������̂Ȃ̂��낤���B���R�ɔC���Ă����Ηǂ��̂��낤���B�@
�@����Ȏ�҂����̑O�ɂ͂т���A����(=���Y�E�����c�����S�c)��W����悤�Ȃ��܂��܂Ȗ��ʂȋ�J(=�ڐ�̕��~�E���K�~�ɕ߂��ꂽ�c)�́A�����ɋC�t�����邽�߁E���z���邽�߂��u���ʗ͂�{���v���߂ɁA�Ӑ}�I�ɗ^����ꂽ�����Ȃ̂��낤���B
�@���A�ۑ�̈�ł����w����ŁE�đ��Ŗ��x�Ȃ��́c
�@�������u�����i���v�̒����琶�܂���u�{���̖��ʁv���������A�ނ��������{���̒�ʒu�ɖ߂��A�u�s�����Љ�v�u�X�g���X�v����ł������Ȃ��A���߂���]������Ƃ����c�o��(���Ɩ�)���S�����[���������ɁA���߂ē��������ׂ����̂Ȃ̂ł́B�@
�@
�@�����Ă��̂��߂ɂ́A���R�A�e�s���{���E�������������Ȃ����Ă͂��蓾�Ȃ��B
�@���ꂼ��̌��n�����̐l�������A��{���ɗ����Ԃ�(=����̗���̔c���E���ʂ̍팸)�A�����Ƃ̐擱�̉��A�������{����Ɏ��g�܂Ȃ���A�����̎������i���ɕs�\�E�]�߂Ȃ����̂ƂȂ��čs�����낤���ɂ͊ԈႢ�Ȃ��B(�u�M���V���v�̋��P)
�@���͂��̂悤�ɑ����Ă��邯��ǁc�ǂ����낤 !?�@�@�@�@(�Q�O�P�U�N)
�@���NjL���@�u���{�̓����v�ł͂Ȃ��A�u���E�̓����v�Ƃ����@
�@���Ⓦ���A�ƌ����c2020�N�E�����I�����s�b�N !�@����Ȓ��ɂ����āc
�@(�z���l��������)���ɂ́A����ȏ�ɐ[���Ȗ��E�ۑ�Ƃ��ĕ����Ԃ̂��c
�@(�����ł͂Ȃ������) ��͂�A��������v�uIS�W�v(�ƁA���̎���)�B�����͈ȑO�ɂ͂Ȃ������A����N�A�ˑR���サ�ė����c�V�����O���ۑ肾�B
�@�������n���ɐ�����l�ԂɂƂ��Ă��A���l���Ƃ͎v���Ȃ��B
�@�u���E�̍L���v�Ƃ��Ă̐S�\�����l�A������{�̐��������A�u���{�̓����v�ł͂Ȃ��A�u���E�̓����v�Ƃ��Ă̍\���Ȃ����Ă͑Ή��o���Ȃ��قǂɋٔ��������E�̎���B����Ȓ��ɗ������ꂽ�A���{�̎�s�E�������B
�@�m���Ƃ��Ă̐l�i�E�͗ʂ͂������A����ɉ����A�w�n���c��x�Ɓw����x�̈Ⴂ�́c����̐�(=���p���������)�����߂���Ƃ����Ƃ���?
�@
�@���f�B�A�̔��W�ɂ���āA���E���u����������v�ɏk�߂��čs������ɂ�����(=����ɂ��āA���E�̎��������)�A���̒��ɂ͓��R�A�u�댯���̖��v���͂��ł���B
�@���̌��n�E����ɗ������A�ٔ��������E�̓��E�ۑ�ɑς�����S�\���Ǝg�����Ȃ����Ă͏��z�����Ȃ��Ƃ����Ă������ĉߌ��ł͂Ȃ��悤�ȁA���̂������B
�@�����w�s�m���I�x���A���悢��X�^�[�g�����B
�@�s�m���͂������A����ȏ�Ɂc
�@����ȋٔ��������̒n����ɑς�����E��\�̗�����x����A(���ƥ�n�����������܂�)�w�X�^�b�t�E�s���̐��x���������E�������鎖����킸�ɂ͂����Ȃ��B���ׂĂ��J�M�́A�����ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�܂��A�������������炷��c��킭�A���Ƃ����I�����l�����ł����Ă��A���̎v���E�ˊo�������ɏ��������ł͂Ȃ��̂�����A���������A�����̌`�ł������������E���͂��čs���Ƃ����A(���f�B�A���܂߂�) ���̐�ւ����S�ӋC���~�����C������B
�@�b�͏������邯��ǁc
�@�捠�́u�s�m���̕s�����v�Ǝ��������ēo�ꂳ��E��������A�u���E�ōł��n�����哝�́v�Ə̂��ꂽ�A�E���O�A�C���哝�́E�z�Z�E���q�J�����B
�@�ǂ̂悤�Ȃ��������ŁA�܂��v�炢�ŗ������ꂽ�̂��A�ڍׂ͂��܂���Ȃ������B(��ʂ�)���f�B�A�ł͂قƂ�ǒ��ڂ���Ȃ��������A���������Ȃ����̓s���ł́A���̗]�T���Ȃ��������낤����ǁB
�@(�ǂ��E�����̔��f�͂��܂��܂��낤�����)
�@�����u�ΏƓI�v�ȏɒu���ꂽ�u����l�v���A������A�����ɓo�ꂳ�ꂽ�����w�i�ɂ́A�ǂ���Ӗ����������P�A���������B����Ă����̂��c������l�����l��������_�͈ĊO�A���������̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���{�̖������c����A���{�̂��߂����ł͂Ȃ��c���܂��܂������T�O����E����Ȃ���A�i���̂Ȃ��E���������A�����A(�����ȏ@���������琶�܂��)�e���E�ƍߎ��܂Ȃ��E�{���̖L���������߂��w���E�O���x�w���ڊO���x��ڎw�����߂ɂ��c��������ʂ��E����ɔ��������̂悤�ȁE�������u����{�v�Ƃ��Ă̗���ɒu���ꂽ�悤�ȁA������V����w�������A���哝�̗̂����ł͂Ȃ��������ƁA���͓���ł��邯��ǁc!?�@(����)
�@����͔����ɕω����A�V�����w���������߂��鎞�㌗�Ɍ������ĕ���ł���̂����m��Ȃ��B����Ȓ��ɗ������ꂽ�A��s�E�����Ȃ̂����m��Ȃ��B�@�@�@(2016�N)�@�@
�@�@���NjL���@�҂��ł��ꂽ�A�I�o�}�哝�� �� �w�L���K��x
�@2016�N5��27���B�҂��ɑ҂������̓����A���ɂ���ė����B
�@���������A�w���E�̍L���x�Ƃ��Ă̗��K��������A�I�o�}�哝�����L���K���B
�@
�@���̗���ɂ���āA�l�X�̕]���͂��܂��܂��낤����ǁc���_�E�����͔����ɂ��āc
�@�܂��A���������w�����x��^������A���̏���w�Ղށx�Ƃ��������́A���̏���������Ȃ���A�l�Ԃ̋�(�킴)�����ł͕s�\�Ȏ����낤�B
�@�w�j����o�łƂ����ڕW���ʂ�����ŁA�L���ȏ�ɂ��̋c�_�ɓK�����ꏊ�͂Ȃ��B�܂��A�哝�̂͗��j�Ɍh�ӂ����ƂɑS�͂�s�����Ă���B�L����K�₷��A����E���̂��ׂĂ̔�Q�҂ɑ��鋭���h�ӂ��������Ƃ��o����x
�@�ƁA���[�X�O�č���g�͋����Ƃ����B
�@(�I�킩�獡���܂�)���܂��܂ȗ���ŁA���܂��܂Ȑl�������K�ꂽ�ł��낤�A���̍L��������ǁc
�@�ƂĂ����R�Łc���E�̍L���͂��Ƃ��A�w���{�̍L���x�ւ̑Ή��Ƃ��Ă��A�\���ɂ��̎g�����ʂ����ĉ���������������B
�@���E�́E�č��̗���Ƃ����A���̋��ԂŁc
�@���i�̉��o������̂ł��Ȃ��A�������E���R�̐U�镑���ɂ���Č��E�����ꂽ�A�I�o�}�哝���B�����W�听�Ƃ��Ă̎g�����\���Ɏ����ĉ��������ƁA���͎v���B�@����̎v�����u�ܒ߁v�ɑ������B
�@����ɂ��Ă��c��c���̕������̑���������Ȃɑ傫�����̂ł���A���l������̂ɂȂ낤�Ƃ́c!�@
�@
�@�؈�@��������M���Ƃ���A������c���̕������̂��̎v�����A��������Ɛ��E���Ɏ����ꂽ�悤�ȁc����������̈�u�E��u������ !�@���炭�A�قƂ�ǂ̕������ɂƂ��Ă��A�\�z�ȏ�̏���ł������ɈႢ�Ȃ��B
�@
�@����ɂ́A�{���ɑ傫�����̂�����Ǝv���B����́A�i���ɍ��܂�čs�����̂ƂȂ��̂ł���c��c���̕������ɂƂ��Ă��c�����܂ł����炦�ė����̂́A�܂������A�������̓��E���̏o��̂��߂������A�ƌ����Ă������ĉߌ��ł͂Ȃ����̂��A���ꂼ��̕������̑S�g�Ɉ��o�Ă����悤�ɁA���ɂ͊�����ꂽ�B(�V���@�������̂��B)
�@�������́A�W�听�ł���Ɠ����ɁA���ׂĂ̎n�܂��ł͂��낤����ǁc
�@�l�Ƃ̏o�����E�o�����ɂ����āA���̒������R������Ȃ��Ƃ����B
�@
�@�������́A�w����������p�x(=�M�u�E�A���h�E�e�C�N�j�͂������̎��A���̂悤�ɁA�w�����Ȃ������p�x�ɂ���Ă��Ȃ����Ă����̂��Ƃ��������A�I�o�}�哝�́E��c���̕�������ʂ��āA���߂ċ�����ꂽ�v���ł���B�@���̒��A�w�����Ȃ������p�x�̕��������̂����m��Ȃ��B
�@�Ƃ�����A�f���炵���E���̓���^���ĉ��������A�_�l���A�@�I�o�}�哝���ɁA��������c���̕������ɁA�S����A���ӂ̈ӂ���������Ǝv���B
�@���ׂĂɂ����āA�w�����x�w���v�x�̋��߂��鎞��B
�@���̎���ɂ��w�����E���v�āx�Ƃ����̂́A���̌���E�����ɂ����āA��肪���邩�畂�サ�Ă�����̂ł���c����̈ڂ�ς��̒��ŁA�������琶�܂����̂ł���A���R�̗v���ł���E�{�\�ł���c
�@����(�����̎���)�̂����₩�ȍK���ɊÂc����̋�_�ł����āA�ے襔��c�ے�E��������J��Ԃ��E�����Ă��邾���ł͏���������̂ł͂Ȃ��ƁA���ɂ͎v����B������肪�Ȃ�������A���߂����u�����E���v�v�Ƃ������t���́A�����Ȃ����낤���A�܂��������Ŏ�茈�߂�Ƃ����悤�ȁA����ȒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̖��ł͂Ȃ��Ǝv���B(�S�����Ώۂ̑������ł���Ƃ��������B)
�@�w���@�E�����x���������B
�@����A����������A�w���E�̑����x�Ƃ��đ�������ׂ��ł���c
�@�W���E����푈���Ȃ����čs���� �W
�@�Ƃ����A��������Ƃ������O�E���ӂ̉��Ɏ{�s�������̂ł���A���������ɒu������ł̢�쌛�v�u�����v�̗��_���i�߂���ׂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̐��̒��A���ׂĂ����E�P���ōl�@���Ȃ���c�������f���E�����łǂ�Ȃɐ푈���������Ă��A�܂����̒��̌o�ρE�������ǂ�Ȃɔ��W���čs���Ă��A�푈���Ȃ��Ȃ�Ȃ�����c�܂�A���E�����푈�̂��߂̕�����̂ĂȂ�����A���͂₻��́A�������̂Ȃ��A�ꍑ�E�������ɂ����ʗp���Ȃ��A�t�@�W�[��(�B����)�A�Ӗ��̂Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��B
�@�w��ɂ�����Ɖ�������Ă��A�̒��ɒɂ݂�����c�Ɠ����������B����A�����ł͂Ȃ��A���߂��炻�̂悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă���B
�@����A���̋���́A���E�̂��߂ɂǂ�Ȗ������ʂ����Ă���鎖���낤 !?
�@�w�����n�E���V��(��s��)�ڐݖ��x�ɂ��Ă��c
�@���{�ɂ���A�����܂��w�ڐ݁x�ł����Ă��A(�����̑��݁E�ڐݗ��R�̏ڍׂȂǒm�낤�Ƃ��Ȃ�)�C�O�̐l�������炷��A(����A�����ł����A�^�S�ËS������l�Ԃ��S�}���Ƒ��݂��钆��)�A������u�V���Ȋ�n�̌��݁v�ł���A���݂��̂��̂��푈���ӎ������u�V�����헪�E�h�q�v�Ƃ��Ă����f��Ȃ����낤�B
�@���ɂ́A(����)���{�l�̗��O�E���z�ɂ́A�ǂ����Ă��u�����ā@�X�������v�Ƃ����c�ڐ�̗��_�E�����A����̋�_���A���܂�ɂ����߂���悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ������?�@�@
�@��͂肱��́A�u���E���v�ɂ���u�S���̑̌��v�Ƃ����A�g���E�}�Ɓc�����Ƃ������ŁA�����ɂ���Ă��܂�ɂ������ԁA�卑�E�A�����J�Ɏ���߂���(=�]���߂���)�����Ƃ����c����ɂ��A����Ȋ��ɊÂ����ʂ��琶�܂�錻�ۂł͂Ȃ����낤���B
�@
�@�쌛�ł͂Ȃ��A�����ł͂Ȃ��A�A�����J���玩�������E���E���������ނ悤�ȁA�܂��A�u�C�O�����̌��@�v�Ɣ�r������E�Q�l�ɂ�����̏_����������A�V�����C���[�W�����z�̉�����ꂽ(�\�����ꂽ)�A����ȁA���E�Ƌ��L�����悤�� �w���{�����@�̒a���x����킸�ɂ͂����Ȃ��B�@�@�@�@�@�@(2016�N)�@�@
���NjL���@�@�y�k���~�T�C�������z��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���N���{���ɋ��߂Ă�������@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
�@���{�ɂƂ��ẮA�k�́u�~�T�C�����˖��v�B
�@�@
�@�u���ꂵ�����@���Ȃ��̂��낤�� !?�v
�@�Ƃ����c!?
�@
�@���x�ƂȂ��J��Ԃ����A���̖��Ƃ͂����c
�@����(���{)�̋�J�����ł͂Ȃ��A��͂�A����̎コ�ɂ��S��z��ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă��܂��B
�@���ɂ͂��̍����A��m�E�����ɒ��������Ƃł���Ƃ́A�ǂ����Ă��v���Ȃ��B
�@
�@�܂����̓����A�ߔN�A�ɗ͗�ÂɎ~�߂悤�Ƃ����m���l�E���_���A�{�c�{�c�A�����n�߂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����C�͂��邯��ǁB
�@�������c
�@������w�ƒ�x�ɗႦ��c(�������u�e�̗���v�Ƃ����ꍇ)�B
�@����̑e�T������ł͂Ȃ��A�S���w�ɂ��藬�����̂ł͂Ȃ��A���ꂪ���U�ł��낤�ƁE�^�ӂł��낤�Ɓc�������Ȃ��E�܂�����A���̖ړI�E��J�����Ɏv����͍��������Ƃ����̂��A�e�S�Ƃ������̂ł͂Ȃ��̂��c�����ړI�Ƃ����s�ׂȂ̂����A�^�S�ł����Ė₢�������p���B�@���Ƃ�����(�q��)�̑Ή����ǂ�Ȃ�����ȁE���\�Ȃ��̂ł������Ƃ��Ă��A����ł������Ƃ��Ă��A�����I�ׂȂ��̂��A�e�̗����Ȃ̂ł� ?�@
�@�o���ɂƂ��āA���́u�v���C�h�̖��v�͑傫���B�ꎞ�I�E��ϓI�����͂Ƃ������A ����Ȃ����Ă�(=���ڑΘb�c����Ƃ��Ă̐ӔC�E�]���̐S)�A�{���̘a���̓��͗L�蓾�Ȃ��B
�@(���瓮�����Ƃ͂����c)�@
�@��k�ɏڂ����A�������ɂ��Ɓc�v�@�u���̖��ɑ��A�������̑Ή��́c�v
�@�ƁA���ڑΉ��ł͂Ȃ��A���Ƃɂ���E�����ɂ�������߁A�g��C����c
�@���́u���l�A�����C���v�ɂ��Ă��A�V��I�E�`���I�Łc�e���킪�q�̔Y���ɉ�����p���Ȃ��A�\�ʓI���قł킪�g(�e�̗���)��ۂ��Ă��邾����(�J���t���[�W��)�B���ꂾ���Â������Ă���Ƒ���(�q��)�͎~�߂�ɈႢ�Ȃ�(=���݂ւ̌y��)�B���ꂱ�����A���̍s�ׂ��~�߂����Ȃ��A�ő�̗��R�ł��鎖�ɋC�t���Ȃ��B����(=���E�āE�c)�̔����@���ɂ���āA����Ȗ�X�Ƃ����E���ׂƂ�����Ԃ������Ă���̂��Ƃ��������A�����ƔF�����ׂ����B
�@����Ƃ��c
�@�k�̍s���ɂ������������Ă���A���E���������A�u���̃^�l�v�ɂ����̂��I�`�A�Ƃł��v���Ă���̂��낤���B��̐����(=�k�Ƃ����̂͂����������A�Ƃ������ߕt��)�ɁA�}�C���h��R���g���[�����ꂽ�悤�ȁB����͑傫�ȊԈႢ���B
�@�A�����J�ɂ��Ă��E���{�ɂ��Ă��c��x���A���ڑΘb���������̂Ȃ�����Ɍ��������A����فv�u���́v�ȂǂƂ������t���g���邾�낤���B����Ȍ���������̂��낤���B���ꂼ��̓������܂܂Ȃ�Ȃ����ŁA�u�����ւ̈��́v�ȂǁA�ʗp���邾�낤���B
�@��ɂ���ɂ��u�E�l�͈��v�ł���A�Ə����A���Q�҂̎E�l�Ɏ������o�܂Ȃǂ͖�������A�Ɠ������c�ǂ������������̓��@������m��Ȃ���A�⑰�͉i���ɋ~���Ȃ�(�[���o���Ȃ�)�A�Ɠ����������B
�@
�@(���X�Ȃ���)���ƂƂ������̂́A�����Ƃ̂��Ƃ肾���Ő��藧���Ă�����̂ł͂Ȃ��Ƃ��������A�ǂꂾ�������Ă���̂��낤�B
�@���t�̏�́A(���̐�����)���̏�̏������E������(=�^���E����)�Ŏ��܂������_���Ȃ�Ƃ������A�u���فv�u���́v�Ƃ����̂́A�u�����̐����v�ɒ��ڊւ���Ă����肾�B
�@�����ƍ��������̒��ɓ������s���A�O�𐭍�̕��j�E������(=�_�)�ւ̐�ւ����K�v�Ȏ��ł͂Ȃ����낤���B
�@����Ƃ���͂�A�u�E�C�̖��v�Ȃ̂��낤���B
�@�Ƃ͂����c���ڌ��������z���Ƃ��Ă��c����ɒ��������͂Ȃ�����ǁc
�@���͂�A�����܂ŗ����ȏ�A���ׂĂ���ƔC����ӓ|�ł͂Ȃ��A�}���l���E���[�h�ɗ�����鎖�Ȃ��c
�@���̂��́A�n�[�h(����)���E�\�t�g(����)�̎�����}�������Łc
�@(�}�X�R�~���ӎ������E���Ɠ��m��)�\�ʓI�Η��̌J��Ԃ��ł͂Ȃ��A�ߗ����͂������A���E�e���̂��ꂼ�������̐l�����������̂��Ɓc���܂��܂ȋƊE���w�������_�x(=�Ƒ��S��)�ɂ����ڂ�������ׂ��ł���(=�Ăт���)�A�m�b�����߂�ׂ��ł���B
�@ ���咆���哝�́E���v�l�ɂ��A�k�ւ��w���z����x�c�A���g�j�I�������́A�܂��A�������f�v�Ƒ��̕�����(�@�r�O�����j�c�����̑��݂�M���E����{�Ƃ��āA�X�ɁE�X�ɍL���čs���c!
�@�����A�������Ȃ���A���̂悤�ɍs�����Ȃ���c���Ɏc���ꂽ���{�̂��܂��܂Ȗ��E�ۑ�Ɠ��l�c
�@�u�����ƁA�}�X�E���f�B�A�́A���̂��߂ɑ��݂���̂��낤 ??�v
�@�Ɩ���Ă��d���̂Ȃ��A��g�E��g�A�ԐځE�Ԑڂ̌J��Ԃ��ƂȂ�A���ׂĂ͌��̖؈���ƂȂ��Ă��܂����낤�B(���荑�����ł͂Ȃ��A�o���������̃`�����X�������B)�@
�@�@
�@���܂��܂�����̐l���������߁E�T���o���E���̐l�����𒇉�Ƃ��ē�����������w�e�ߊ��x�w�������x���A��������Ɣނ�(�k�̐l����)�ɒ��c���̂悤���u�Ǘ��v�ł͂Ȃ��c
�@�u�������A���������܂��܂����S�ł͂Ȃ�(=�����̐����E��������X�܂ł��ׂĔc�����E�������Ă����ł͂Ȃ��j�B�����E���h�̓���ڎw���āA��̓I�ɓ��c�E���_�������Ȃ���A�ꏏ�ɕ���ōs���܂��傤��B�v
�@�Ƃ����A�݂����������d�������Ȃ���́A�Ăъ|���A�U���|���B
�@���فE�����Ƃ����A���g�̂Ȃ��A�ォ��ڐ��E�����C���ł͂Ȃ��A�u�Ƒ����o�v�ł̑Ή����A���������߂��鎞�Ȃ̂ł� !?�@(�܂��āA��e���ƂƌĂ��A���̓��{�ł���� ! )
�@���͂�A���ꂱ�����ł��}�����c���������ł͂Ȃ��c��k�̓���(=�e�a�E�e��)�͂�������c���E�ɂƂ��Ă��A�d�v�ȁE�i�ق̉ۑ�ł���ƁA���ɂ͎v����B�@( �����c���ׂĂ̂킴�ɂ́@�������� )
�@�����͂������A���E�I��E�K�͂ɂ���w���c�̏�x�w�����̒m�b�x(=������o�ς̔��W)�ݏo�����߂̌������A��ł������݂��E�Q���𑣂��Ƃ����A�M�����E�C(=�u���E�I��c�̏�v�ɗU���藧��)�B
�@�Ⴆ�A�I�o�}�哝���̒��ɂ��A�u�č��ƃL���[�o�Ƃ̍����v(���̌���u�A���[���`���v���܂߂�)�̂悤�ȁB
�@���Ȃ݂ɁA���A�b��ƂȂ��Ă���A(�č����E�^�ۗ��_��)�I�o�}�哝���ɂ��A�w�L���K��x�B
�@���̎��ɂ��Ă��c�����̂��ׂĂ����E�P���ōl�@���ׂ��A����21���I���}���c
�@�哝���ɂ́c���q���e�ɂ����j��ő�̋]���ƂȂ����A�L��(����)�B���̍L��(����)���c�u���{���̍L��(����)�v�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�w���E�̍L��(����)�x�Ƃ��đ����A�u�j�̔p��v�Ƌ��ɁE�����̂��߂��w���E���a�x��ڎw�����w�L���K��x���������Ē��������B�����ł���A���Ȃ��Ƃ��A�����K���ɑ��āA�č����ɂ��ω��������A�X�Ȃ��^���҂̊g���ɂȂ���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����̒��Łc�����̐l�Ԃ����ő�����ǂ�Ȃɍׂ����E�[�����͂��Ă݂Ă������͐i�܂Ȃ��̂ł���A���������E�P��(�Ƒ��S��)�ōs���Ȃ���A��ɑO�ɂ͐i�߂Ȃ��̂ł���c����Ȏ��㌗�ɂ���悤�ɁA���ɂ͎v����B
�@�}�X�R�~�����́E���̏�������낤���߂́c�S�����̌J��Ԃ�����ł́A�k�ɂƂ��Ă��A�����ɂƂ��Ă��A���̗��v�ɂ��Ȃ���Ȃ��B
�@�S�����̗e�Ղ��c���B�@�S�����̓���̂́c�������E�\���B
�@���̖��Ɍ���Ȃ��c�厖�Ȏ��E�̐S�Ȏ��ւ̊ԐړI�Ή��E���S�E��c�ɂ��ė������ʂ��A���̂��́A�k�́E���{�́E���Ӎ����̎p���낤�B(�������č����ӎ����E����߂��ė��������܂�)
�@�����̂悤�ɌJ��Ԃ����A�V�l�c�q���c��҂����̈����N�������E���́B(�ނ���k�̗����ɗႦ��Ȃ��)�����ɂȂ��錴���E�N�����A����ȂƂ���c�B���ȁE�ɖ��ȓ��{�E���Ӎ��Ƃɂ��`���I�E�`���I�Ή��̌J��Ԃ��c�ɂ���(������)�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���������Ă��E�ǂ�Ȏ��������Ƃ��Ă��c����(=�Ƒ�)���{���ɋ��߂Ă�����́i���Ƃ̐������܂߁j�c�����T���o���E�˂��~�߂鎖�������c
�@�w �l�ނ́@��Ƒ� �x
�@�ł���Ƃ����A�����ړI�ł���A���ł���A���ׂĂ͂������A������Ƃ��������A�̂ɖ����ׂ����B
�@����Ȃ����ẮA�ǂ�ȋ����Ȑ����ƁE�w���҂�����Ă��A���E���a�ɂ͉i���ɂȂ���Ȃ�(������ł����āu�g�v�͒D���Ă��A�u�S�v�܂ł͒D���Ȃ�)�B�@�@
�@���������͂��u�G�v�������Ȃ���̐����c�����̂��ׂĂ��u�G�v�Ƃ����悤�ȁc�k�̐l�������A����Ȏ����ɖ������Ă���Ƃ͓���A�v���Ȃ����A�k�̍s�ׂ��A�k�����̐ӔC�ł���Ƃ́A�ǂ����Ă��v���Ȃ��B
�@�Y���Y���E�Y���Y���ƊԐړI�Ή����J��Ԃ��ė��������ɂ��A�傢�ɐӔC������B
�@�ǂ��܂ōs���Ă��肪�Ȃ��E�ړI�̂Ȃ��S�����(=�S���̒T�荇��)�͂����A���̕ӂ�ŏI��ɂ��ė~�����B�@�@
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����B
�@�w�n�͕������Ă��A�������邱�Ƃ͂ł��܂���B�x
�@�w���N�������a������ΐ��E���a�����A���N���������ꂳ���ΐ��E�����ꂳ���̂ł��B�x�@
�@���فc�����c���̃X�P�[���͂��܂��܂��Ƃ��Ă��B���̌���̋�J�͓����҂łȂ���Δ���Ȃ����̂ł���Ƃ��Ă��B��т��Č����鎖�A����́c�����̂��ׂĂ��w�t�����x�ł���Ƃ��������B�������k�Ɍ���Ȃ��c�uI S���v�Ȃǂɂ��ʂ���c�q���ɂ����Ĕ��鎖�B
�@
�@�C���������ԋ߂ɍT�����A�I�o�}�哝���ɂƂ��āc
�@���̎��������A�A�W�A�́E���E�̐擱���Ƃ��āA�ɗ́E�q�ϓI����Ŋ��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���ꂼ�������(����)�ɓ����E�Ō�̎g���ł���ƁA���ɂ͎v����B
�@�����A��������������Ǝp���A�V�����w�������a�����Ă���邾�낤���c�ǂ����낤 !?�@�@�@�@(2016�N)
���NjL���@�����I�����s�b�N�����ڂ� �c���I�f�W���l�C���E�I�����s�b�N ��O�ɂ����@
�@
�@���ꂼ��ɁA�m�̓������킸�A���̍��Ȃ�̎��������������Ă���A���̂��̐��E�̎���B
�@����Ȓ��Łc
�@����E2020�N�������I�����s�b�N�c!
�@�����A(�����Ǝ���ς���Ă������{)�A���������I�����s�b�N�𐢊E�����X���i���Ǝ~�߁A����E�^�����̂ɂ́A�t�Ɍ˘f���̂悤�Ȃ��̂��o���Ă��܂����Ƃ����A���̎�������ǁB
�@���E����́A���ꂾ���̗]�T��������(=���҂����߂�)�~�߂�ꂽ�Ƃ����A�V�̊肢�ł���A�����w�����x�������Ƃ��������낤�� !?�@
�@�����A���̑O�Ɂc
�@�Q�O�P�U�N�E�Ċ��I�����s�b�N�̊J�Òn�́A�u���W�������I�E�f�E�W���l�C���B
�@�u���W���Ƃ����c�Ȃ�Ƃ����Ă��A���I�̃J�[�j�o���I
�@�v���A�{���ɕs�v�c���C�x���g���Ǝv���B�ǂ�Ȏ���ɂ��ڌ����������̂��肩�ł͂Ȃ������(1723�N�c?)�A�����I�c�Ƃ������A���ɂ͉����A�I�����s�b�N�̋ɒv�̂悤�ȁE�W�听�̂悤�Ȃ��̂��v�킹��\�������邯��ǁH�@�i���j
�@�ǂ�ȉ��y���p�ӂ���A��������čs���̂��c!?�@�A�e�l�E�I�����s�b�N���琔�����P�Q�O�N���Ƃ����A�����ے��I�E�ۗ��I�ߖڂ̐��� !!�@�Ȃ��A�u���W���Ȃ̂��c!�@(���Ȃ݂ɁA2004�N���A�e�l�E�I�����s�b�N����́A12�N��!)
�@���������A���̓��{�́c�w���x�c�ƁA�w���x�c���A�����ɒ��a�����E����グ��ꂽ�A���������w���g���ǂ�x�̃C���[�W�ɒʂ�����̂�����悤�ȁB�l�ԂƂ����̂́A���͂������A���Ƃ��u���v�ł����Ă��A���ꂾ���ł͂Ȃ��Ȃ��l�ڂ��������͓���A�u���{�E�C�L�v����ԁA�Ƃ悭�����邯��ǁB�����͂������A���ł͐��E���o�Ŏ~�߂��Ă���Ƃ����A���̑f���炵���A���y���w�E�~�x��c�I
�@�Ƃ�����A����ɂƂ��ẮA���߂Ă̊J�Òn !�@
�@�ėՂ̃L���X�g�̐[���v���̍��߂�ꂽ�� �E�u���W��!�@
�@���{�ɂƂ��Ă��A�[���E�ǂ������Ō��ꂽ�� �E�u���W��!
�@����ȍ��ׂƂ����A���G�Ȑ��E��ɂ����āc�ǂ����A�C�Y�����s�m���ɂ́A�܂��}�X�E���f�B�A�ɂ́A���́A���I�f�W���l�C���E�I�����s�b�N�ɂ��c��������Ƃ��Ă̂���J���������A���͂̐S�ł����Đi�s�����E����グ�čs���Ē��������ƁA�S����v���B�@�������A�C�����Ă��������邾�낤���́A�S�����m�̏�ŁB
�@�����āA�����I�����s�b�N���c�V���Ȏ���E2021�N�Ɍ������A���n���E���� !?�@
�@�����̖����̂��߁A���E�̖����̂��߂ɁA����ׂ��A���I�����s�b�N�̐�����S����肢�A�F���Ă��܂��B�@(2015�N)
���NjL���@�W��}����������g�߂ΕK�����Ă��W �����Y�E�����̓}��\
�@�@�u�c���̂��߂ɂ́A�V�}�����̂��x�X�g���B�V�}�ɂ��Ȃ���ΈӖ��͔�������B��������̐��}�łȂ��ƁA�M�Ƃ݂͂Ȃ��Ȃ����낤�B���Ԃ͂Ȃ����A���̋C�ɂȂ�Γ�����Ƃł͂Ȃ��B�Q���������l������A�I���̎��ɓ͂��o������B�I����̒����������I�ɂ͑�ς����A���f����B�v�@(�����V���E�u�����^�v�����)
�@�ƁA�����\�͋����B�@
�@�v���Ɂc
�@���������A���Ȃ��A�̑O�Ɂc��}�ɂ́E��}�Ƃ��Ă̖���������̂ł���A��`�ɂ����ď����ł��݂��̋��ʓ_�����o���E��v�c�����Ċ|�����(=�哯���فE�哯�c��)�A�K�R�I�Ɂu�^�}�̎��v(=�ŊJ��)�����シ��A���ス����Ȃ��̂ł���c���ꂱ�����A�����݂̂Ȃ炸�E�C�O���ɑΉ�������{���E��}(�������A���Y�}���܂߂�)�Ƃ��Ă̑��݈Ӌ`������̂ł���c���������̂悤�ȁA��}���o���o���̏�Ԃł́A���̈Ӗ����Ȃ��C������B�܂��āA�ǂ�ȍ��x�Ȑ���E���v���f���Ă��A�y�䂪�s����ł́A���H�͖������B�@
�@�����������̊��҂́c����܂ł̂悤�ȁA�`���E���O�́u�^�E��}���c�E���_�v�ł͂Ȃ��c�J���ꂽ�u�^�}�ԓ��c�v�ł���c�܂����Y�}�����܂߂��E�J���ꂽ�u��}�ԓ��c�v�ł���c���Ɍ�҂̕��ɂ͊��҂�����̂�����B
�@
�@���{���Y�}�̖��i��������邯��ǁc����ȁA(�ǂ���������) ���ׂƂ������{�̏ɂ����āA����ɂ́E����Ȃ�̑��݈Ӌ`������Ǝv���A�V�̔z�������m��Ȃ��B
�@�������A���߂ĕ����Ă݂���!�@
�@����́c(�v�������������킹�Ē������) ���{���Y�}�ɂ́A���̓��{�̏�O�ɂ��āA�{���ɐg���o�傪����̂��ǂ����A�Ƃ��������c!?�@
�@�{���Ɏ��}�̐�����������Ǝv���A����ێ������ł͂����Ȃ��A�܂��ǂ�Ȃɓ}���������悤�ƁA�����ւ̃r�W�����������Ȃ��̂ł���A�܊p�̖��i�����̖��ɂ������Ȃ��B
�@�������������Ŋ撣��Ƃ����̂́A�ƒ�ɒu��������Ɓc
�@����͈ꌩ�A����?���т��E���n?�ɊÂc�����Ă��̂��߂ɂ͑��̈�ƈ�����悷�Ƃ����O�ꂳ���M(������)���͂��邯��ǁc
�@�������A�Ƒ��Ɍ��킹��Ɓc����͐e�̐g����ł���A�u�q���v�Ɏv���āE�����u��ρv�Ȃ̂����m��Ȃ����c�K�������A�Ƒ��S���̔[���E����(=���̑��d)�ɂȂ���Ƃ͌���Ȃ��̂ł�? �Ƃ������ƂɂȂ�c!?�@
�@���߂āA���̓O��Ԃ�����}���ɗ��߂��A�������ł��Љ�E�_��������Ȃ���(=�Љ�̌����E���ݕt�����펯�_�ɂ��ڂ�����)�A���̖�}���{���̓��c�E���_���d�˂Ȃ���c�Ȃ݂鎖���܂߁c�������Ɍ�������簐i(�܂�����)���ė~�����ƁA�S����v���B
�@
�@�u�����Đ��܂ꂽ�l�Ԃ̐�(����)�v �Ɓc�u���ʁv�c�Ƃ̋�ʁE���ʁB�@��V�ƌ�V�c��V(=���R�̗~�])�����ے肵�Ă��Ȃ����A�����������͂Ȃ��̂��A�������͂���̂��A�Ƃ����B
�@�������́A���̖�}�ɂ������鎖���Ǝv���B
�@���ꂼ�ꂪ�E���ꂼ��ɑ哯���فE�哯�c���̐S�ŁA�ړI�̂��߂ɂ͐���ρE�v�����݂ł͂Ȃ��A���Ƃ�����ł����݊��ׂ��ł���(=����������)�c���ꂱ�����e�̗����ɗ������A�{���̐���(=�Ǝ��E�ƌv�̐萷��)�Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@
�@�}�X�R�~�ɑΉ����邽�߂̒��ۓI�E�V��I�ȁA�u�^���v�E�u���v�c�u�^���v�E�u���v�c�̌J��Ԃ��ł͂Ȃ��A�����Ƃ��̍��{���e�Ɍ��y���ׂ���(=�Ȃ��^���Ȃ̂��E�Ȃ����Ȃ̂�)�B
�@
�@����肱��́A(����)�擱�I����́A���f�B�A���̂ɂ��������鎖���Ǝv���B
�@���ʘ_���܂Ƃߏグ�邾���ł́A�^�E��}�̈Ӗ����E�������̈Ӗ����E���f�B�A�̈Ӗ����Ȃ��C�����邵�A�������ɓ`����Ă�����́E�S�����Ă������͉̂����Ȃ��B(�v������)�i�s�̂��߂́A�����ƁA�A�C�f�B�A�͂���͂��� !�@
�@�������C�O��i���̐����̐��Ɣ�r���Ă݂Ă��c���{�̐����̐����́A���̍��{���猩�����ׂ����㌗�ɂ���̂ł͂ƁA���͎v���Ă݂邯���?�@��(��)��ł܂����̂ł͑O�ɐi�߂Ȃ��A�Ɠ��������Łc�_��Ȃ����āA�i���Ȃ� !?�@�@�@(2014�N)
���NjL���@�w�Ԉ��w���x�ւ̒�����Ӂc���ׂĂ��O�i�̂���!?�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�^���ɂ���A���ɂ���A���ՂȘ_�]�̐ςݏd�˂̉ʂĂɎc���ꂽ���̂ɂ́A���Ƃ������B�@
�@�u�Ԉ��w�����v�Ɏn�܂����w�����V���x�̌������A�����E���_�������̂��̒��Łc�}�X�R�~�ɂ���āA��ȕ����Ɉ��������Ă���B�@
�@�����V�����A��V���̂悤�Ɂc�����炸�E�G�炸����{�Ƃ��E���b�g�[�Ƃ��ēW�J���Ă����Ȃ�A���x�̂悤�ȑ����ɂȂ鎖���Ȃ������̂����m��Ȃ��B��肻�̂��̂����J����鎖�͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@���僁�f�B�A�Ƃ����̂́c�\�����ɂ͂��܂��܂Ȏ��_�E�ϓ_�c����E�L��ɂ킽����邯��ǁA���̖ړI�Ƃ���Ƃ���́c�ɂ߂Ē��ۓI�Ƃ������c�ǂ�������A�|�C���g����܂�Ȃ��E�͂߂Ȃ��c
�@�ނ�ɂƂ��đ厖�Ȃ��ƁB����́A�����̉��������A�u����ێ��v�u�����ҁE�w�ǎ҈ێ��v�ł���A�������̎v�z�ł��邩�̂悤�ɍ\���c�L���E�c�����b�g�[�Ƃ��c
�@�����Ă���́A���̎��X�̐����^�}�̐����̐��ɂ������悤�ȁE�ʂ���悤�Ȃ��̂�����B
�@�ނ�́A�܂��`�𐮂��A���܂��܂Ȗ��E�ۑ�����܂��܂Ȋp�x���玟���玟�ւƌ��y�E�Njy�͂��邯��ǁA���ʂƂ��āA�u���̊j�S�v�ɂ͋ɗ͐G��鎖�͂Ȃ��c���H�E�����E�͏o���Ȃ��c�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ȁB
�@(�����Ƃ�����́A��V���Ɍ���Ȃ�����ǁB)�@
�@�����āA�J����ɑ��Ắc�u�j��^�̍\�����v�ɂ���āA�Љ���̈��萫������čs���c�v�Ɩ��w�����E�ے肵�c���s�̑����~�߂Ă��܂��A�C�f�I���M�[�E�w�ғI���z�B���ׂĂ͌���ێ��E���L�������ҁE�w�ǎ�(�g�D�[)�ێ��̂���?
�@�u���f�B�A�̔��W�v���A�t�����v�̉���E�ށA�Ƃ�����������̂����m��Ȃ��c���܂��܂ȗ���̌�����E���܂��܂Ȋp�x����E���L�������邠�܂�A���H���� �C�f�I���[�O�����������Ƃ����A����B
�@������A�����O��Ƃ��đ�����Ȃ�c���x�������V�����Ԉ��w����̌�ɂ��w�����E���̂��߂̍����x�Ƃ����s�ׂ́c
�@�L���E�E����ێ��c�ł͂Ȃ��A��̊j�S��˂����E�Ђ����玟�̒i�K�ւƕ�����i�߂čs�����߂ł���A���̂��̂����Ɂw���l�сx�ł���E�w���ȁx�ł���Ǝ~�߂�ׂ��ł͂Ȃ����ƁA���ɂ͎v����B
�@���̖��̂�������m��Ȃ��l�Ԃ����o�����鎖�ł͂Ȃ��A�Ǝv���l�������吨���邾�낤�B
�@�������c�@
�@���܂��܂ȕ��ʂ���E���܂��܂ȕ���̐��Ƃ̐l�������o�ꂵ�A�c�_�E���_���邯��ǁc���̍R�c�E���c�̖ړI������Ȃ��A�Ȃ��Ȃ����_�Ɏ���Ȃ��A�܂Ƃ܂�Ȃ��c??
�@����ɂ́A�ނ�̗v������ӂ��̂��̖̂ړI���B���Ȃ��̂ɂȂ�c�₪�ẮA����ނ�Ȃ܂܂ɏ����čs���c���̂��̑����̒��ŁA���ɂ͉���������Ȗ������z�������B
�@�u���v�v�Ƃ́c���_�������邽�߂̃p�t�H�[�}���X�ł���A�P�Ȃ�L���b�`�t���[�Y�ł���A���̉��ɂ������(=�{��)�́A���v�̎��H�ł͂Ȃ��A�u�����ێ��v�ł���A�u�g�D�[�����v���ł���c
�@�������������Ă��A�u���������v�v���n�߂Ƃ���c�u�Љ�ۏ�E����Łv�c�u�_�Ɓv�c�u�����v�c�u�����n�v�c�u�f�v�v�c�u�k�Ёv�c���́u�X�����c���v�������A(�����ɂ����)�����n�b�L�����Ȃ��A���̕���������܂�Ȃ��A�Ƃ������悤�ȁB����ȏ�Ǝ��Ă���B�@
�@�����Ă��̐��_��(=���f�B�A�Ƃ́E�����ƂƂ́c)�A�ǂ����E�������㐶�Ɉ����p����E���ł��ˑR�Ƃ��đ����Ă���̂ł���c���ꂪ���{���x�z���鐭�E�E���僁�f�B�A�̎��Ԃł���E�{���ł���c���̎���ɂ��J��Ԃ��ė����A�Ђ�����A�w�{���x�w�p���x����邽�߂̑�E����?�ł���Ǝv���B
�@��̉ۑ���L���E�Njy���c�₪�Đl�X�̊S�����ꂽ���A�܂����̓��E�ۑ肪�A�܂�ŗ����ƁE���s�̂悤�ɕ�����ł͏����E������ł͏����c�����ɑ��Ă��A�g�D����邽�߂ɂ͂ǂ�Ȕᔻ�E���]�������Ƃ�Ȃ��A���������u���ۓI�E�����v���J��L�����E�J��Ԃ���čs���B�@(=����̎�ς���邽�߁E�q�ς��Ă���?) (=����I�����͂��ׂāu���̌�v�B�u���̑O�v�ɂ͂��Ȃ�?)
�@����������c�L���E�c�Ƃ����̂́A �������邽�߂̗^�}�E���僁�f�B�A���������Ƃ������c�h���Ƃ������B
�@(�ǂ����������c���̓��{�̐����̐��E�I�����x�ł͎d���Ȃ��Ƃ͂����B)�@
�@(�����āA���܂��܂ȉۑ�̂��̍����ɂ́c���̏ꍇ�A����������ł���B)
�@�����炻����v���ƁA���x�̂��́u�Ԉ��w�����E�폜���v�Ƃ����傫�ȓ��E�ۑ������\�I����Ƃ����A���̖ړI�́c!
�@�����ŎZ�̂��ׂĂ���蕥���A�P������ł��낤�A��Љ�̍������o��̏�Łc
�@����̓��{�̂�����A�܂��؍��ւ̐��������j�F���ւ̓]���̗v���c(=�L�������ւ̌������������a�V�c�̐��E�Ɍ������������~���錾�Ƃ����A���ƓI�E���E�I���x���E��B�@�Ԉ��w����Ƃ����A�����I�E�W�c�I���x���E��B)
�@�����ւ���ʥ�����ƁA����𗝉����Ăق����Ƃ����S���B�Ђ��Ă��A�W�A�́E���E�̑O�i�E���W�̂��߂�ړI�Ƃ�����̂ł���c
�@���Ȃ��Ƃ��E����v���Ƃ��c����ȁA����Όl�I�v�]�E���_�E���_���A���ʂ́E�G���̃g�b�v������A���̕����ɂ��藬����Ă��Ắc������͂��̖������̊j�S���O��A�����̑O��ɕ�(�Ȃ�)���A���僁�f�B�A�E�^�}�����ɂ���āA�܂��܂��A�L���E�E����ێ��c�Ɉ��ݍ��܂�A�B���Ȃ܂܂ɏ����čs���ɈႢ�Ȃ��A�Ƃ����c
�@������x�����E�O��̂��ƂɎ��H���ꂽ���̂ł͂Ȃ��������낤���B
�@�ԈႢ��F�߂鎖�͐h���B�������A���̎p���E���ӂ́A�����̎q�������ւ̉e�����l����Ɓc����͑厖�Ȏ����ƁA���ɂ͎v����B���ꂪ�Ȃ�������A�l�Ԃ́E���Ƃ͐������Ȃ��B
�@���߂āA���a�V�c���u�������~���錾�v���v���Ԃ��Ă݂Ă��c
�@���������c���ɂȂ���(=����)�A���́u�Ԉ��w���v����荹�������Ƃ��������́A���͂ƌ����A�w�������~���錾�x�Ƃ������l�ρc����ɑ���A���̂�����E�������E���f�B�A�̂�����c�����u�O�ꂳ�v(=�Â�)�ɖ�肪����������Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�؍������ɗ��܂�Ȃ��A�A�W�A�̊e���ɂ��ݒu�����(���ꂽ)�Ƃ����A�u�Ԉ��w���v�B���{�����悵�āA�푈�Ƃ����C���[�W�@���Ȃ�����A���̖��͑������낤�B
�@�܂��܊p�́A�����͂������A���E�Ɍ������w�����V�c�̕��a�v���x���A�Ȃ��Ȃ��e�Ղɂ͓͂��Ȃ��B�@
�@�Ƃ͂����c���̖�肪�u�����������ƊE�E���_���ÂɐU��Ԃ��Ă݂�Ɓc!?
�@������ꐺ�́A���𑵂����悤�ɁA���������V���̕����A
�@�u��肠�����́A�]������B�v
�@�Ƃ����������������B���ɂ͂��ꂱ�����A���{�����f�B�A�E���_�������ł���E�{���̂悤�Ɏv��ꂽ�B
�@���_�̖{���́c�L���E�c�̕����]���A�n���������A���̐ςݏd�˂ɂ��A���̂悤�ɖ��Ȗ�肪���܂�ɗ��܂��čs�����̂��Ɓc���̐S��ł͑����Ă���ɈႢ�Ȃ��B���{�l�̎v�z�ς́A�����Ď̂Ă����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B(����!)�@
�@�Ȃ�c
�@���܂��܂ȍR�c�E���]�̗��̒��Ƃ͂����A�����V���ɂ͂����u��ꐺ�v�d���Ă��炢�A�O�i�̂��߂̗�(����)�Ƃ��āE��������̏d�v�������o���Ă��炢�A�����܂ł��ړI����O��鎖�Ȃ��A�Ђ����玟�Ɍ�������簐i(�܂�����)���Ăق����B�@
�@������E�Ӎ߂͈ꌩ�A�Љ�ɔ�Q��^���E��ނ��Ă���悤�ɉf�邯��ǁA�����͑S���̋t�ł���c!
�@�B�ς���c�����(���̍Г��)�A��������ƌ���E���������l�߂��A��̑傫���i�W�ł���A���K�E��������E�o���邽�߂ɗ^����ꂽ�A�]���̎��ł���E�����ł����A�����Ƃ��炵���_�]�ɘf�킳��Ă͂����Ȃ��Ƃ����A���̗��Ԃ��ł����c������A�u��ނ�!�v �Ƒ�����l�Ԃ��������Ȃ̂ł́c�ƁA���͂��̂悤�ɑ����Ă��邯����c!?�@
�@�W�����}���Ԃ���!�W�Ə����Ȃ���A�����ɏ��������߂�ꂽ�c���́A�����̎p����������!�@���ꂱ�����A���v�Ȃ̂��B�@�@�@�@�@(2014�N)�@
�@���NjL���@�����S���ł� �w���c�v�ȁA�L���E�E���M��������Ɩʉ�x �̃j���[�X������
�@2014�N3��10���`14���ɍs��ꂽ�A�����u�ʉ�v�Ƃ́A�����������������̂��낤?�@���E�k�ǂ���̒�Ăōs��ꂽ���̂Ȃ̂��낤?�@��������ʏ����ɂ́A�ʉ��Ɏ���܂ł̃v���Z�X�E������S������Ȃ��c�j���[�X�ŏ��߂Ēm�炳�ꂽ�B������A�P�Ȃ�u��������̃j���[�X�v�̒��̈�Ƃ��āc!?
�@�ǂ�ȃv���Z�X�ł���A�����ƂȂ�A���߂āA�ʉ����̂��̂������Ƒ��d���A�O���ȑΉ��ł͂Ȃ��A�����ǂ����Ă������ł���A�O���E�f�v�S�����Ƃ��c�����܂ł������������s���A��������������Ώ������ׂ��������̂ł� ?
�@�����̎��̂悤�ɁA�Ƃ܂ł͊��҂��Ȃ�����ǁc���Ƃ������ړI���ǂ�ȓ��e���܂�ł��悤�Ɓc�܂��k�ɑ���A�Ċւ̋C�����E���{�̗���̖�肪�������Ƃ��Ă��c�������u�f�v���̏d�v���v�������鐭�{���l����ƁA����̂��̑Ή��ɂ́A�ǂ�����a�����o����B
�@(�����ł͂Ȃ�)���{�����Ŏ�ނɉ������O���̃R�����g���A(�}�X�R�~���܂߂�)�ɂ߂Ď����I�E�`���I�ƌ��킴��Ȃ��悤�Ȉ�ۂ������c���ɂ����ẮA�R�����g�ǂ��납�A�p���������Ȃ������c�f�v����ɑ������{�̖{�����_�Ԍ����悤�ȋC�������̂́A���������낤���B
�@�����I�̍ŏd�v�ۑ�̒��̈���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��A���̖��B
�@���̂Ȃ�c���̖�肪���Ƃ�����ł��O�i����A���������ł͂Ȃ��u���E�̏�v���ς�鎖�ɂ͊ԈႢ�Ȃ��A��������E�ۑ肪�A�X�Ɉ�E��O�i���čs�����ɂ͊ԈႢ�Ȃ��̂�����!�@�@
�@�ėՂ̃L���X�g�͋����A�w�V���̍ŏ��P�ʂ́@�ƒ�x �ł���ƁB
�@�q�ǂ�(=���j)���ǂ�ȑʁX�����ˁE�������Ă��c�q�ǂ���������l�̗͂ŕ����������E�����鎖�͕s�\���B
�@�k���̗������u�q�ǂ��v�ɗႦ��͕̂s�ސT������ǁA���A�̗��j=��蒼���̗��j(=�_�̈Ӑ})�ɂ����Ă��̂悤�Ɉʒu�t�����Ă���̂�(=������w�����čs������)�A�������u�q�ǂ��v(���j)�Ƃ����đՂ����B�@
�@���������c(�U��o���ɖ߂��čl���Ă݂Ă�)�c���N���������f�́A�k�̈Ӑ}�ł��E���̈Ӑ}�ł��A�������A���{�̈Ӑ}�ł��E�A�����J�̈Ӑ}�ł��Ȃ��c���ׂĂ��V�̈Ӑ}�ł���E���A(=����)�̂��߂̗��j�I�K�R�ł���c�Ƃ����Ƃ��납��o�����Ȃ���Ε����͐i�܂Ȃ��̂ł���B
�@(�����ɂ�������j�I�������̗��c�u���́@�p���̐S���@�킴�Ƃ������Ȃɂ���v�@�u�_�́@�킴���J�C���̕������͔����@�A�x���̕������݂̂����ꂽ�v )�@
�@���͂Ɍb�܂�E���߂���̂����Ȃ���A���͔�r�I�ȒP�ɐ������邯��ǁc����Ɋ��҂�����̂��傫���E�[���ł������قǂ��̌��͒��������́A�Ƃ����̂������Ȃ̂ł�
!?
�@���̏�E���̏�̏��������ł͂Ȃ��A���݂����E���݂��̖{���ɔ���ɂ́A�S�����ɂ́A�ǂ����Ă����E������B�@�S�����ł����āA������x���_�ɖ߂�A���E�s���A������E����������A�����܂ł��o���̗����ɗ����Č��ߒ����ׂ��ł���c���͂�A�w�f�v���x�����{���Ƃ��������A�ނ����k���ɂƂ��āu���ǂ����܂ꂽ���v(=���̑傫�ȋ]���E����)�ł��鎖�����@��(=����⑊��̐S���������͂���E�v�����) �A���݂��̎�ςł͂Ȃ��A���E�k(�E��)�̋�������Ƃ��Đi�s������ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�@(�V�g������(�w��p��)�E�A�����J�ɂ��܂ł������Ă��Ă͂����Ȃ�!�@�������Ȃ��Ă�!)
�@�Ⴆ�c�k���Ƃ̂�������Ƃ������c�ɂ���A���{�̎��q���̐l�������A���n�ɔh������Ƃ��c!?�@
�@�k�E���͂��Ƃ��A�āE���E���c�̎��Ԃ����Ă��A���̂悤�ɑΉ��o����̂́A
�@�u�푈�E�R���Ƃ��Ă̐����������Ȃ��A���{�̎��q���v
�@�����ł͂Ȃ����낤���B�������A�w�����̑��ݖړI�x�����߂Č������E�������ׂ����Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�I���Ȍ�����������c�o���ɂƂ��āA���Ƃ��ǂ�ȔߎS�ȁE�s���Ȍ��ʂ��҂��Ă��悤�Ɓc�u���A�����̉Ƒ��������ɂ���̂�?�@�����Ă���̂�?�@����ł���̂�?�@����������Ȃ�
!?�v �Ƃ�������́A�܂����B
�@�܂��āA��������l�̐l�Ԃ��s���s���ɂȂ��Ă��A�S���Ԃő{���ɓ�����Ƃ����c�l�ނ͈�Ƒ��c�Ɖ]����A����Ȍ���ł���A���X���B�@( ��l�͖��l�̂��߂Ɂ@���l�͈�l�̂��߂�
)
�@���ɂ��Ďv���c���܂��܂ȗ��_�E���������c�u�����������L�ƒ��ږʒk�����A����v�c�́A����ς�A�����ȂƎv��!�@
�@��������ӂ��ꂽ�A�u�Ԃ̎v���Ƃ͉��������̂��c�����Ƃ��A����͂��{�l�ɕ����Ă�����Ȃ����̂Ȃ̂����m��Ȃ��B �_�݂̂��m��B���ׂẲ́A�����ɉB����Ă���ɈႢ�Ȃ��B
�@(���͗��_�E��������B�v�������ׂĂ����E����B�@�S���Ȃ���E�V�͓����Ȃ��B)�@
�@�Ƒ��Ƃ����̂́A�L�����Ƃ��E�s�����Ƃ��A�������Ƃ��E�`�����Ƃ��c�������݂ł͂Ȃ����낤���B�@
�@�������̉���Ȃ��A�����������̔\�͂ł́A����Ȓ��ۓI�Ȓ�Ă����o���Ȃ�����ǁc�c�B�@�@�@(2014�N)
���NjL���@�c�����ȑ��́u�R��w�V�ݕs�F���v�ɑ���}�X�R�~�̎p��
�@�����A�c�����ȑ����u�s�F�����v�����Ȃ�������A���̖��́A�����̊ԂŌ`���I�ɁE�����I�ɏ�������c���_�͂������A�������{�ɂ��E�}�X�R�~�ɂ��A���̖ڂɐG��鎖�͂Ȃ��A���炭�A�s�F�̃t�̎����m�鎖���E�l���鎖���Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B
�@�ɂ��S�炸�c�}�X�R�~�́E��}��(���E�����})�A�����Ȃ���̌��E�����ł����ĘA���̃g�b�v�Ɍf���A�������ĂĂ���B
�@���Ȃ��Ƃ��������S���鐢�_�ɂ́A�c�����ȑ��̕s�K�ؔ������Ƃ��E���̃p�t�H�[�}���X�ɂ́A������A���̒�R�������Ȃ����A�s�����ȂǕ����Ȃ��i��������O�̌����ł���E���̊O���Ȕᔻ�̍Č��ł���E�V���ł���c!�j�B
�@�ނ���A��w�ݒu�E�w�Z�@�l�R�c��?�Ƃ����c��������Ȃ��H�@���{�ɂ͊֗^���Ȃ�?�@�܂�ŕ��ȑ�������Ȃɒu���ꂽ�悤�ȗ���Łc�}�X�R�~�̉�����Ȃ����ނɑΉ����邻�̎p�̕��ɁA��قLj�a���Ƃ������A�뜜�̂悤�Ȃ��̂����o����c!�@
�@���������A�i�܂����k���ȂǂȂ��������̂悤�ȁj���̂��̐[���ȓ��{�̏ɋt�s�����A���̑�w�ݒu�E�w�Z�@�l�R�c�c���ĉ����낤!?�@���́A����Ȗ������ׂĂ��o���オ�������_�ł����āA�\���i�v�]�j�Ȃǂ���̂��낤�H�@�F����̂��펯�Ȃ�A�\�����邻�̈Ӗ����E�^�ӂ�����Ȃ�!?�@���c�@���ł���A�l�����Ȃ������� !�@
�@�}�X�R�~�E��}�͉��́A�����������������{�I�ۑ�ɋC�t�����A�G��悤�Ƃ͂��Ȃ��̂��낤 !?�@
�@����������哱�I���p���[�h�̒��̈��ł���c�ق�̈�p�H�@�@�@(2012�N)�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���̃y�[�W�̐擪�ցj